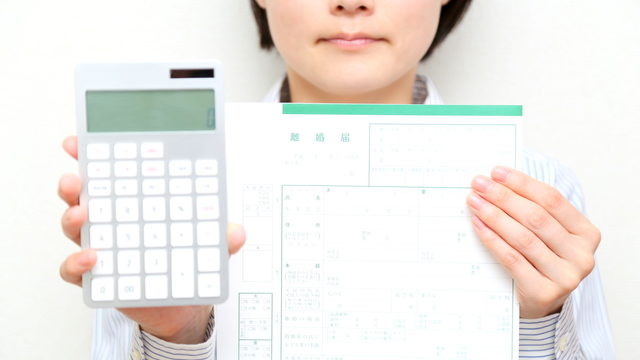離婚を決意したのであれば、離婚で取り決めるべきことについてしっかりと見通しを立てておく必要があります。財産分与や慰謝料といったお金の問題、子の親権、養育費などについてしっかりと認識しておかないと離婚後の生活が立ちいかなくなることも考えられます。
今回の記事では、女性側(妻側)が離婚を決意した時に知っておくべき法的知識について弁護士の目線から解説します。離婚を検討している女性の方はぜひ参考にしてみてください。
慰謝料とは
01.慰謝料はかならず請求できるわけではない
世間では、「離婚の際は、妻側(女性側)から夫側(男性側)に対し必ず慰謝料を請求することができる」と認識されていらっしゃる方がおりますがこれは誤りです。
条件不問で妻側から慰謝料を請求できるわけではありません。
02.慰謝料とは?
そもそも慰謝料とは何なのでしょうか?
こと離婚における慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金(損害賠償金)です。
相手方に離婚の原因がある場合、こちら側は相当の精神的ショックを受けて大きな苦痛を感じます。この目に見えない精神的な苦痛を慰めるために支払われる損害賠償金が慰謝料なのです。
すなわち、慰謝料が発生するには離婚する夫婦のどちらか一方に相応の悪い点(責任)があって、それによりもう一方が精神的に傷ついた(ショックを受けた)という事情があることが前提となります。
この悪い点のことを専門用語で有責性といい、どちらにも有責性がなければ慰謝料は発生しません。また、こちら側が一方的に悪いようであれば慰謝料を請求できないどころか逆に請求されることとなります。


慰謝料を請求できるケース
慰謝料を請求することができるのは、相手に有責性がある場合です。
たとえば夫側が下記の行為を行っている場合には、夫は婚姻関係(夫婦関係)を破綻させてもよいという考えを持っていたと評価できますので、夫側に有責性が認められることとなります。
- 不倫相手と性行為を行った
- 暴力を振るわれた(DV)
- モラハラ被害を受けた(精神的DV)
- 生活費を払ってもらえない(経済的DV)
- 家出した
01.不倫相手と性行為を行なった
夫が不倫相手(配偶者以外の女性)と性関係を持った場合、不貞(法律上の不倫)が成立しますので夫に対し慰謝料を請求することができます。

02.暴力を振るわれた(DV)
夫から暴力を受けていた場合、家庭内暴力(DV)に該当する可能性が高いです。DVの被害に遭っていた事実は相手方に有責性を認めるものとなるので、慰謝料を請求することができます。

03.モラハラ被害を受けた(精神的DV)
DVは身体的な暴力だけに限られません。
継続的に侮辱されたり異常に束縛されるなどのモラハラ被害(精神的DV)を夫から受けた場合についても、これを理由として有責性が認められるので慰謝料を請求できる可能性があります。
04.生活費を払ってくれない(経済的DV)
DVには経済的なものも存在します。
妻側が専業主婦やパート勤務であるため収入が低いというケースにおいて、夫側が十分な生活費を払わないようであれば経済的DVに当たる可能性があります。
経済的DVの被害に遭っていた事実も相手方の有責性を認めるものとなるので慰謝料を請求することができます。
05.夫が家出した
夫婦には同居義務があります。
正当な理由なく夫が家出した場合にも、有責性が認められ慰謝料が発生する余地があります。
慰謝料の相場
離婚における慰謝料の金額は事案等によって異なりますが、50~300万円の金額となる事例が多数です。

慰謝料を請求できないケース
以下のようなケースでは夫婦の一方にのみ有責性が認められるとはいえないので、慰謝料を請求できる可能性は低くなります。
- どちらが悪いというわけではないが協議によって離婚することにした場合
- 性格の不一致を理由として離婚することにした場合
- 相手方の実家との不和を理由として離婚することにした場合
- 宗教や政治信条が大きく異なることを理由に離婚することにした場合
- 子どもの教育方針で対立したことを理由として離婚することにした場合

財産分与を求める際の注意点
離婚の際には、財産分与がなされることがほとんどです。
特に収入がないもしくは低い妻側からすれば、財産分与で受け取る額は離婚後の生活資金となります。妻側はどのくらい財産分与を受けることができるのかをしっかりと把握しなければなりません。
また、熟年離婚の場合は夫婦で築いた財産が大きくなっているケースが多数です。高額ゆえにトラブルになりやすく熟年離婚の際の争点になることが多数です。
以下、財産分与のポイントについて確認していきましょう。
01.財産分与とは
どの財産が財産分与の対象となるのかしっかりと確認しましょう。
実は財産分与の対象となる財産は、『夫婦が婚姻中に共同で形成した資産』に限定されております。
『婚姻中に』とあることから夫婦の一方が独身時代から保有していた財産は対象になりません。
また、『共同で形成した』とあることから夫婦の一方のみに起因する事情で獲得した財産についても対象とはなりません。たとえば親からの遺産(相続財産)については『共同で形成した資産』とは言えないため財産分与の対象とはなりません。

02.財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となるものとしては、以下のものが挙げられます。
- 現金、預貯金
- 株式などの有価証券、投資信託、債券
- 車
- 保険(解約返戻金のあるもの)
- 自宅などの不動産
- 貴金属
- 各種の積立金
- 退職金
退職金について
退職金は、以下の条件を満たす場合に財産分与の対象となる可能性があります。
- 離婚後10年以内に定年等を理由に退職予定である
- 公務員や上場会社へ勤務している会社員など退職金が支給される見込みが高い
離婚後も働き続ける予定の場合は、退職金見込み額の全額を財産分与対象とするのではないので注意しましょう。また、勤続年数のうち婚姻年数(婚姻から別居まで)に対応する部分のみが財産分与の対象となる点にも注意しましょう。
03.財産分与の割合
財産分与の際の分与割合も重要なポイントです。
法律上、分与割合は基本的に夫婦で2分の1ずつとする運用が定着しております。そのため、協議によって離婚するケースでは半分ずつに折半するのが公平といえます。
なお、夫側が医師や経営者など一般人とはかけ離れた高収入を得ている場合には、財産形成の寄与度合から財産分与を折半とするのは男性側に不利であるとし妻の財産分与割合が減らされることがあります。
相手が財産隠しをしたときの対処方法
財産分与は夫婦が婚姻中に共同で形成した資産を夫婦折半で分ける手続きです。
そのためには「婚姻中に共同で形成した資産」を特定する必要がありますが、この際には財産隠しに注意をしなければなりません。ある金融機関口座に200万円あるにも関わらずその口座の存在を伏せられてしまった場合、その資産について分与の対象とすることが出来ず受けることが出来るはずの財産分与を受けられなくなってしまうためです。
特に夫側が収入や資産を管理している場合には、財産隠しのリスクが高いといえます。財産隠しを予防するため以下の対応をしておきましょう。
01.同居中に相手の財産資料を集める
離婚前の段階で夫婦が別居するケースは往々にしてありますが、別居を始めてしまうと夫側の財産に関する資料を集めることが難しくなってしまいます。
そのため、同居している段階で夫名義の通帳や保険証券、不動産や株式などについての資料をできるだけたくさん用意しておきましょう。それぞれの資料についてコピーをとったりメモを残したりして後に確認できるように対処しておくようお勧めします。
02.弁護士会照会を利用する
夫側が財産を隠して開示しないがために財産分与の対象となる財産を確認できない場合には、弁護士照会を利用することで調査できる可能性があります。
弁護士会照会とは弁護士が弁護士会を通じて各機関へ情報照会を行って回答を求める制度であり、照会を受けた機関には法律上の回答義務があります。この照会制度を利用することで夫の保有財産をチェックできる可能性があります。

なお、弁護士会照会は弁護士でないと利用することはできません。
03.裁判所からの職権調査嘱託を利用する
訴訟提起している場合には、裁判所から調査嘱託を行なってもらえる可能性があります。職権調査嘱託とは裁判所による情報照会制度です。
調査嘱託を受けた金融機関は取引履歴等を開示してくれますので夫の財産資料を収集することが可能となります。
なお、弁護士会照会や職権調査嘱託を利用するためには弁護士に依頼することが必要不可欠です。夫が財産隠しをしているかも、と疑う余地のある場合には弁護士までご相談ください。

財産を使い込まれた場合はどうなる?
夫側が財産を管理している場合、財産分与の対象となる預貯金などを使い込まれてしまうリスクもあります。勝手に不動産を売却処分する可能性もあります。
使い込まれてしまった場合、財産分与額はその分減ってしまうのでしょうか?
そんなことはありません。別居後に使い込まれた財産が財産分与の算定に影響を与えることはないからです。
財産分与の基準時は別居時とされております。別居後の夫の使い込みで財産が減少していたとしても、その減少分は考慮せず別居開始時に存在した財産を2分の1ずつで分配することとなります。使い得が許されることはないので安心しましょう。
とはいえ、実際に使い込まれてしまうと回収が困難となるリスクがありますので使い込みの予防策を講じておくべきでしょう。その予防策は仮差押です。
仮差押とは、相手名義の資産を仮に差し押さえて凍結する手続きです。
不動産や預貯金、証券口座などを仮差押えすると、相手は売却や抵当権設定、入出金等をすることができなくなりますので、使い込みや換価処分を防ぐことが出来ます。夫による財産使い込みが不安な方はぜひ利用するようお勧めします。

女性側は必ず親権をとれるのか?

世間一般では「子どもの親権者は女性がなるもの」と考えられておりますが、これは間違いです。女性の方が親権者になりやすいということは事実ですが必ずしも親権者になれるわけではありません。
特に最近では育児に積極的に参加する父親も増えてきております。子どもが小学校以上になってくると父親にも親権が認められやすくなってくる傾向があります。

母親として親権を取得したいのであれば、上記のリンクを参考に必要な方策を講じておきましょう。
主として育児を行うのはもちろんのこと、子どもと一緒に過ごす時間を増やして良好な関係を作る、別居する際に子どもと離れない等の対処をしっかりと取っておきましょう。
親権取得を有利に進めたいのであれば弁護士に相談することをお勧めいたします。

養育費を確実に支払ってもらうには

子どもの親権者になった場合、子どもが成人するまでは確実に養育費を払ってもらいたいと考えるものです。
しかしながら最後まできっちりと養育費が支払われるケースは少ないというのが現実です。養育費を確実に支払わせるために以下の対応をしておきましょう。
01.取り決めをする
離婚時に養育費の取り決めをしておくことが重要です。何も決めずに協議離婚してしまった場合、養育費が支払われる可能性は極めて低くなります。
養育費の相場はお互いの収入状況により決まります。こちらの養育費の算定表をもとにあてはまる数字を調べて、相手に伝え養育費についての合意をとりつけてください。
02.公正証書を作成する
養育費の取り決めをしたら必ず公正証書を作成しましょう。
公正証書を作成しておけば相手が支払を怠ったときに強制執行(差押)することが可能となります。
相手が会社員や公務員であれば給料を差し押さえらることが出来ますし、預貯金や保険、不動産などの資産をも差押えることが可能です。
また、公正証書を作成しておけば相手にも「支払わなければ差し押さえられる」というプレッシャーをかけることができ、不払い予防の効果も期待できます。
03.不払いがあれば強制執行を行う
養育費が支払われなくなったら公正証書にもとづいて強制執行を行いましょう。
なお、強制執行を行うには地方裁判所への申立てが必要となります。1人で対応するのが難しい場合には弁護士へご依頼ください。

04.状況が変わったら金額を変更する
養育費の金額は離婚後の状況の変化に応じて変更することができます。
たとえば男性側の収入が上がったときや子どもが15歳以上になったときに増額を要請するケースです。
正当な事情があれば相手に養育費の増額を要請しましょう。応じてもらえない場合、家庭裁判所に対し養育費増額調停を申し立てれば増額してもらえる可能性があります。
年金分割

年金分割の手続きも忘れずに行なっておきましょう。
特に合意分割が適用されるケースでは、相手の合意がないと年金分割できません。協議の際に年金分割についても合意してもらいましょう。分割割合は公平に2分の1とするのがお勧めです。
また離婚が成立したら、年金事務所へ行って年金分割の申請(標準報酬改定の申請)をしなければなりません。離婚後2年以内に手続きをしないと権利が失効するので、早めに手続きを行いましょう。
合意分割の場合には、元夫にも年金事務所に一緒に来てもらわなければなりませんが、公正証書で年金分割の合意をしていれば、妻一人でも手続きができます。
この意味でも離婚公正証書は非常に有用なので、協議離婚する場合には必ず作成しておくようお勧めします。
離婚後の面会交流にも注意

離婚後、子どもとの面会交流について元夫とトラブルが発生するケースがあります。

よくあるのは以下のようなパターンです。
- 元夫が強硬に面会交流を求めてくる
- 女性側が再婚したことで、元夫との面会交流に消極的になる
法律上、面会交流はできるだけ積極的に行うべきと考えられていますが、子どもの都合を無視した無理な方法で実施すべきではありません。父親が自分の都合を押しつけている場合には断って別の方法を設定できます。
一方で母親が再婚したからといって面会交流をやめることはできません。親同士で話し合い、子どもにとってベストな面会交流を実現する必要があります。
面会交流でトラブルになった場合、弁護士を間に入れて交渉したり調停を利用したりするとスムーズに解決できるケースが多々あります。お困りの際にはお早めにご相談ください。
最後に
離婚に際しては考えておくべきこと、対応すべきことが多々あります。対応をしなかったり対応を誤った場合には今後の生活に大きな影響を与えかねません。
「一人で対応するのは難しいな」とお考えの方は弁護士に手続きを依頼しましょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では離婚事件に力を入れて取り組んでおります。離婚を検討されている方は是非一度ご相談ください。



_妻が離婚を決意したときに知っておくべき全知識~財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費~.jpg)