- 離婚したいけれど、どのように進めればよいか分からない
- 相手が離婚に応じてくれない場合、どうしたら良いのか?
- 相手が不倫していたので慰謝料を請求したい
- どうしても親権を獲得したい
- 財産分与はどのくらいもらえるのか?
配偶者との離婚を決意したとして、事前に考えておかねばならないことはたくさんあります。急いで離婚を進めてしまうと大きな不利益を受けて後悔するケースもありますので注意が必要です。
今回の記事では、離婚の進め方、慰謝料、親権や養育費等、「離婚したい」と考えた際に有益となる情報について弁護士がわかりやすく解説します。
離婚の進め方

まずは離婚の流れについて順を追ってみてみましょう。
01.資料・証拠を集める
パートナーと離婚したいと決意したとしても、何らの準備をせずいきなり相手に対し離婚を切り出すのは得策ではありません。離婚をするうえで不利益となる資料を隠される、相手方に有利となる証拠を準備される等、相手方に離婚に対して備える時間を与えてしまうことになるからです。
まずは交渉に必要な資料、有利となる資料として、下記のような資料を収集しておきましょう。
財産に関する資料
きちんと財産分与がなされるように、夫婦の財産に関する資料は集めておきましょう。
- 預金通帳や口座残高が分かる資料
- 証券口座の残高明細書
- 生命保険証書およびその解約返戻金額が分かる資料
- 不動産の全部事項証明書や査定書
- 自動車の車検証や査定書
- その他財産に関する資料
不貞に関する資料
パートナーが不倫・浮気しているのであれば、不倫に関する証拠も集めておきましょう。
- LINEやメールなどのメッセージの記録
- スマホやPCに保存されている性的な動画や画像
- 交通ICカードの履歴やクレジットカードの明細書
- 電話の通話明細書
- 日記やスケジュール帳のコピー
- 調査会社(探偵)による報告書
- その他不倫していることが客観的に確認できる資料

DVやハラスメントに関する資料
DV(ドメスティックバイオレンス)やハラスメント(モラハラ等)を受けている場合は、被害を受けていることを証明する証拠を集めておきましょう。
- パートナーから暴力を受けている、侮辱されている様子を録音録画したもの
- 暴力を受けて怪我をした場合の患部の写真、病院の診断書
- 配偶者からのモラハラメール
- 被害をうけたことを詳しく記録した日記帳

02.相手に離婚を切り出す、話し合う
手元に充分な資料が揃った時点で、パートナーに離婚を切り出しましょう。
このとき、できるだけ具体的にこちらが希望する離婚条件を伝えることが望ましいといえます。たとえば「家に財産がこれだけあるから半分である〇〇円分受け取りたい」「子どもの親権はこちらで取得したい。養育費はいくら払ってほしい」など。
具体的に条件を伝えれば、相手も検討しやすくなります。
条件が合意に至れば協議離婚となりますが、相手が離婚に対し頑なに反対する場合、提示した条件に応じてくれないということも多々あります。そのような場合は、際は話し合いを重ねる必要があるでしょう。冷却期間をおくために別居するのも1つの方法です。
相手が怒ってしまい話し合いにならない、当事者間での話し合いでは収集がつかないということであれば、専門家である弁護士を間に挟むことも検討しましょう。弁護士を代理に立てれば、以後の配偶者との交渉を弁護士に一任することができます。

03.合意書を作成する、離婚届を提出する
離婚すること、離婚に際しての条件について双方の合意ができた場合は協議離婚合意書を作成しましょう。
協議離婚合意書は、可能な限り公正証書にしておくようお勧めします。公正証書にしておけば、支払義務者が養育費などの支払をしなかったときにすぐに差押えができて便利だからです。
合意書作成後、離婚届に必要事項を記入し、役所に提出すれば離婚成立となります。
04.離婚調停を申し立てる

相手方が離婚に応じない場合、当事者間で離婚条件について交渉しても折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
家庭裁判所の管轄は、住所地となります。パートナーと別居している場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所となります。
調停では、調停委員が間に入って離婚の話合いが進められ、合意ができれば調停が成立して離婚できます。
05.離婚訴訟を提起する
離婚調停でも解決が図れなかった場合は、離婚訴訟を提起します。
訴訟で離婚を認めてもらうには法律上の離婚原因を立証する必要があります。きちんと法的な主張と立証ができれば、裁判所が判決という形で離婚を認めてくれるので、相手が離婚を拒否していたとしても離婚できます。財産分与や慰謝料、親権などの条件で揉めている場合は、各条件について裁判所が判断してくれます。
なお、日本では調停前置主義が取られております。これは端的にいえば、訴訟をする前に調停を行なってくださいね、というルールです。そのため、相手方と意見が一致しないからといっていきなり裁判(離婚訴訟)を提起することはできず、先に離婚調停を行う必要があります。
、DV離婚-320x180.jpg)
以上が、離婚に至るまでの大まかな流れです。なお、9割以上は協議離婚、1割が調停、離婚訴訟まで至るのは1%程度といわれています。
法律上の離婚原因とは

法律上の離婚原因とは、民法の定める離婚理由のことです。以下の5つが該当します。
01.不貞
不貞とは、「肉体関係を伴うパートナーの不倫」のことです。
すなわち、不貞行為があったと主張するためにはパートナーと不倫相手との肉体関係を立証しなければならないのです。
単にデートしていることを示した証拠だけでは肉体関係を証明する資料とはなりません。肉体関係を立証する証拠としては、たとえば性行為尾をしているときにふざけて撮影した動画や写真、不倫当事者が肉体関係があったことを認めた書面(自認書)、等が挙げられます。
LINEやメールなどのメッセージ、クレジットカードの明細書、スケジュール帳の記録などは間接的な証拠にしかなりませんが、たくさん集めることによって不貞を証明できるケースもあります。
02.悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、「婚姻関係を破綻させてやろう」という意図を持って相手を見捨てることです。下記のような仕打ちを配偶者から受けていたということであれば、悪意の遺棄が成立します。
- 一家の大黒柱による生活費不払い
- 正当な理由のない家出
- 不倫相手との同棲
- 実家に戻ったまま夫婦の家に帰ってこない
- 元気なのに働かない
- 生活費を使い込む
03.3年以上の生死不明
配偶者が3年以上生死不明な状態が続いている場合も、法律上の離婚原因となります。
生死不明であることが要件なので、生きていることは明らかである場合は要件を満たしません。
また、パートナーが行方不明になってから7年が経過している場合は失踪宣告をすることも可能です。失踪宣告を受けた相手は「死亡」したとみなされるので、婚姻関係は終了し、遺産相続が発生することとなります。
生死不明になって7年が経過しているケースでは、①離婚して財産分与を受け取る、②失踪宣告して遺産相続する、のどちらが得になるかをしっかりと検討する必要があります。専門的な知識が必要となる場面ですので、どうすればよいかわか習い際は弁護士までご相談下さい。

04.回復しがたい精神病
配偶者が重度の精神病を患っているケース、たとえば統合失調症や躁うつ病、偏執病などを患い、「重度で回復の見込みがない」と医師に判断されているケースも法律上の離婚原因となります。
ただし、相手が精神病になったからといってすぐに法律上の離婚原因として主張できるものではなく、「一定の期間、献身的に看護してきた」ことが必要になります。
また、精神病のパートナーが離婚後に生活できる目途が立っていることも要求されます。精神病の相手を放り出すような場合は、法律上の離婚原因とは認められません。
05.その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

上記の4つに直接該当しなくても、上記に準じるような重大な事情があって夫婦関係を継続するのが困難なほどに破綻しているときは、法律上の離婚原因とは認められる可能性があります。
DVやモラハラ
配偶者からDVやモラハラの被害を受けている場合は、離婚原因として認められます。これらは相手の人格を無視した強度に違法な行為だからです。
長期間の別居
長期間別居状態が続いている場合も離婚原因として認められます。別居期間が5年以上経過している場合は認められる傾向にあります。
家庭を放棄している
パートナーが家庭を放棄している場合は、離婚原因として認められる場合が多いです。下記のような事情があると、家庭を放棄していると判断されます。
- 宗教活動などにはまりすぎて家に帰ってこない
- 毎晩のように外に出歩いて家事も育児もしない
- パチンコ等のギャンブルに嵌り、家にお金を入れない
夫婦がお互いにやり直す意思を失っている
夫婦がお互いにやり直す意思を失っている場合は、法律上の離婚原因が認められる傾向にあります。
セックスレス
健康で若い夫婦にもかかわらずセックスレスとなっていて、これについて当事者の一方が大きな不満を抱えている場合、法律上の離婚原因と認められる可能性があります。
ただし、セックスレスだからといって必ずしも認められるわけではなく、個別の事情に応じて判断されます。たとえば高齢のケースや体調が悪いなどの身体的事情が存在する場合には離婚原因とはならないのが通常です。

別居中の生活費について

離婚の前段階として別居する夫婦は少なくありません。別居の理由としては、パートナーとの同居が苦痛となった、冷却期間をおくため、など様々です。
別居すると婚姻費用が発生します。婚姻費用とは、夫婦が分担すべき生活費のことです。夫婦はお互いに扶助し合う義務を負っており、その義務は夫婦関係が終了するまで、すなわち離婚が成立するまで続きます。
夫婦の一方が専業(無職)で他方が一家の大黒柱といったケースでは、別居から離婚成立時まで生活費を送金しなければなりません。

01.婚姻費用の金額について
婚姻費用の金額については、家庭裁判所が基準を定めています。2019年12月の金額改定によって増額されていて、受け取る側に有利に変更されています。
02.婚姻費用の取り決め方
別居前に婚姻費用についての取決めをしておきましょう。
婚姻費用について合意ができなかった場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てれば調停のおいて婚姻費用についての取決めができます。相手が支払を拒絶したとしても、審判で支払命令を出してもらえます。
03.婚姻費用の仮払も可能
生活に窮して緊急を要する場合には、婚姻費用仮払などにより審判前に支払を受ける方法もあります。
離婚の際に決めておくべき事項6つ
について.jpg)
離婚するときには、きちんと離婚条件を取り決めておきましょう。離婚時に決めておかないと、離婚後にトラブルとなる可能性が高くなります。
離婚時に決めておきたい離婚条件は、以下の6つです。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割
なお、親権については事前に定めていないと、そもそも離婚できません。離婚届に親権者を書く欄があり、記入しないと届を受け付けてもらえないからです。
その他の条件については離婚に必須ではありませんが、後々困らないためにきっちり話し合って決めておきましょう。
以下ではそれぞれの意味や定め方について解説していきます。
財産分与
財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚時に清算することです。
婚姻中は夫婦の財産の多くが共有状態になっています。しかし、離婚後は他人になるので共有にはしておけません。そこで財産分与によって清算する必要があるのです。
01.財産分与の対象になるもの
財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦が協力して積み立てた財産です。
以下のような財産のうち婚姻中に夫婦が協力することで形成したものが財産分与の対象となります。
- 預貯金
- 現金
- 車
- 積立金
- 不動産
- 株式、投資信託
- ゴルフ会員権
- 生命保険(解約返戻金つきのもの)
- 動産類(絵画や貴金属など)
各財産の名義は問いません。夫婦どちらの名義であっても「婚姻中に夫婦が協力することで形成した財産」であればすべて財産分与の対象になります。「自分名義の預金は、無条件で財産分与から外せる」などと考えている方がいらっしゃいますが、これは間違いです。夫婦で協力することで形成したものと認められるのであれば、口座名義を問わず分与の対象となります。
財産分与の対象とならない財産
「婚姻中」という要件があることから、婚姻前に形成した財産については財産分与の対象とはなりません。「独身時代から持っていた財産」は財産分与の対象外となります。
また、「夫婦が協力して形成した」という要件があることから、「夫婦の一方が親族から相続した財産」や「夫婦の一方が親族から贈与を受けた財産」も財産分与の対象外となります。
02.財産分与の割合は基本的に2分の1ずつ
財産分与は、原則2分の1ずつで分与します。夫婦の一方が専業であるケース、双方の収入に差があるケースでも分与割合は2分の1です。
ただし、一方の特殊な能力や資格などによって通常をはるかに超える高収入を得ているケースなどでは、財産分与の割合が修正される可能性があります。たとえば、一方が医師で病院経営をしており高額な収入を得ているケース、敏腕経営者で通常の会社員をはるかに上回る収入を得ているケースなどでは、その方の取得割合が大きくなることが多いです。
03.財産分与の基準時
財産分与を行う際は、基準時にも注意が必要です。どのタイミングの財産の評価額を基準に財産分与をするか、は財産分与に大きな影響を与えるからです。
原則は、以下のタイミングを財産の評価基準時とします。
- 原則は離婚時
- 離婚前に別居した場合は別居時
別居が開始となると以後の夫婦の家計は別となるので、その時点で財産が固定されるためです。
なお、別居後に相手が財産を使い込んだとしても「別居時に存在した財産の半額」を請求できます。ただし、使い込まれると資産が失われて実際に支払わせるのが難しくなるので、使い込まれないように仮差押などによって対応することが望ましいです。
仮差押え等は専門的な手続きとなるため、弁護士に依頼して進めることを推奨いたします。相手による財産使込みが心配な方は、お早めにご相談下さい。

慰謝料

離婚する際、相手方に慰謝料を請求できるケースもあります。
01.慰謝料とは
慰謝料は、(不法行為にもとづき)精神的に損害を被ったときにこれを慰謝するための損害賠償金です。パートナーに不法行為があってこれにより精神的苦痛を受けたケースにおいてはじめて発生するものであるため、離婚時に必ず発生するものではありません。
02.慰謝料が発生するケース
離婚時に慰謝料が発生するのは、以下のような場合です。
- 相手が不倫した(肉体関係がある場合)
- 相手が悪意の遺棄をした
- 相手からDVやモラハラ行為を受けていた
03.慰謝料が発生しないケース
逆に以下のようなケースでは慰謝料は発生しません。
- 性格の不一致で離婚する
- 子どもの教育方針が違うので離婚する
- 相手と政治や宗教が異なるので離婚する
- 長期間別居していることを理由に裁判上で離婚が認められた
04.婚姻期間による慰謝料の相場

慰謝料の相場はケースによって異なります。たとえば、不倫で慰謝料請求するときには、以下のような金額が相場です。
婚姻期間が1~3年
婚姻期間が短いと慰謝料は比較的低額になります。100~150万円程度が相場となるでしょう。
婚姻期間が4~9年
婚姻期間が4~9年程度の場合、だいたい150~300万円程度となります。婚姻期間が長くなるにつれて慰謝料が高額化する傾向があります。
婚姻期間が10年以上
婚姻期間が10年以上になると、慰謝料は300万円程度となります。極めて悪質なケースでは500万円などの高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
05.慰謝料が高額となる事情

婚姻期間以外の事情によっても慰謝料の額は変動します。たとえば、以下のような事情があれば慰謝料の額は高額となるでしょう。
- 不倫の期間が長い
- 不倫が頻繁に行われていた
- 不倫が悪質で夫婦関係を破綻させようとする意図があった
- 不倫にお金を使い込んで生活が逼迫した
- 不倫相手と同棲した
- 不倫相手が妊娠、中絶、出産した
- 未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
- 不倫された被害者が精神病になった
不倫を前提とした事情を列挙しましたが、このほかにもDVやモラハラ等の事情により慰謝料が高額となるケースがあります。
自分のケースではいくらの慰謝料を請求できるのか知りたい方は、お気軽に弁護士までご相談下さい。

親権

離婚する際、子どもの親権者については必ず決めなければなりません。

01.親権の内容
親権は、子どもと一緒に住んで監護養育を行う身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権から成り立っています。また、親権者は子どもの教育方針を決定したり懲罰を与えたりすることも可能です。
婚姻時は夫婦の共同親権となっていますが、離婚した場合は片方の親にしか親権が認められないので、離婚時に父母のどちらを親権者にするかを決める必要があります。
なお、親権者を定める必要があるのは、子どもが未成年のケースのみです。子どもが成人している場合はそもそも親権自体が認められません。
02.親権者を決める方法
親権は、基本的に父母が話し合って決定します。
どちらを親権者にするか決めたら、その人を親権者として離婚届に記入して提出します。そうすると指定された親が親権者となり戸籍にもその旨が記載されます。
協議では決められなかった場合、家庭裁判所で離婚調停を行う必要があります。調停では調停委員が間に入って話し合いを進めたり、家庭裁判所の調査官が調査を行って現状を確認したりします。
離婚調停においても親権者についての話し合いが決裂した場合は、訴訟によって裁判所に親権者を決めてもらう必要があります。判決で離婚する際には裁判所が法的判断基準にもとづいて親権者を決定します。
03.親権者の判断基準

裁判所は、親権者を判断する際、以下のような基準を採用しています。
- これまでの養育実績の高い方を優先
- 離婚時に子どもと同居している方を優先
- 子どもが乳幼児なら母親を優先
- 離婚後、子どもと長い時間を共に過ごせる親を優先
- 子どもとの関係が良好な親を優先
- 離婚後、相手との面会交流に積極的な方を優先
- 離婚後の子どもの養育方針が明確で信頼できる人を優先
- 健康状態が良好な方を優先
- 経済力がある方を優先
- 親権者がフルタイム勤務の場合、監護補助者(子どもの祖母など)がいると有利になる
訴訟で親権者争いをする場合、調査官による調査が必ず行われます。調査官の意見は裁判官が判決を書く際に非常に重視されるので、親権を獲得したいのであれば調査官へのアピールが鍵となります。
子どもの親権を勝ち取るには、紛争が起こった当初から適切な行動をとり続ける必要性が高く、初動を誤っただけで後々取り返しがつかなくなるケースも多々あります。
相手と親権争いが起こりそうな方は、離婚協議を始める前に弁護士までご相談下さい。

養育費

未成年の子どもがいるのであれば、養育費も取り決めておきましょう。
養育費は、子どもの監護や教育のために必要な費用のことです。親が親である以上当然に支払わねばならない費用であり、子どもが成人するまで支払い義務が続きます。
また、養育費は離婚後すぐに請求できるので離婚前にしっかりと取り決め公正証書に内容をまとめておくことを推奨します。
01.養育費の額について
養育費の金額は、夫婦それぞれの収入状況に応じて決まります。支払う側の収入が高ければ高額になり、支払いを受ける側の収入が高ければ低額になります。
また、子どもの人数が多いと金額が上がり、子どもが15歳以上になった場合にも増額されます。
養育費についても婚姻費用と同様2019年12月に金額が全面改定されて、引き上げられています。今後取り決めをするときにはこちらの新しい算定表を使って計算してください。
02.養育費の終期や学費について
養育費を取り決める際、いつまで支払いを受けられるのか、高額な学費がかかったらどうすれば良いのか、と心配される方は多いです。
支払終期については、原則は「子どもが成人する月まで」となります。
ただし、当事者間の合意があれば延長も可能です。たとえば、子どもが大学に進学する見込みが高いのであれば、大学に進学した場合には22歳になった年の次の3月まで養育費を支払うなどと定めてもかまいません。
また、学費について月額の養育費と別途支払う約束もできます。たとえば大学に入学したら入学金と授業料は父親が負担すると定めることもできますし、学費は父母が折半すると定める方法もあります。
養育費の支払終期や学費の支払方法については、父母それぞれの経済状況や子どもの置かれた状況、就学への希望などをもとにケースバイケースで取り決めると良いでしょう。
面会交流

子どもが小さい場合は、面会交流についても定めておきましょう。
面会交流とは、子どもの監護養育権者にならなかった親(非監護親)が子どもと会うことです。親子である以上、たとえ親権者・監護者とはならなくてもはお互いに交流する権利が認められています。

面会交流について約束をしておかないと、離婚後に面会交流調停や面会交流審判が起こってトラブルになる可能性があるので、必ずお互いの希望を確認した上で約束しておきましょう。
01.面会交流の方法、モデルケース
面会交流の方法について、法的なルールはありません。違法行為さえしなければ、どのような会い方も可能です。子どもの年齢や状況、お互いの居住場所などの状況に応じて決めると良いでしょう。
面会交流の方法としては、以下のようなモデルケースが挙げられます。
- 月1回、午前10時から午後5時までの面会
- 月2回、うち1回は土日に宿泊する面会を行う
- 夏休み、冬休みには旅行に行く
02.面会交流の注意点

面会交流を取り決める際は、子どもの都合を優先しましょう。
たとえば面会交流のために子どもに無理に習い事をやめさせたり大切な部活の試合を休ませたりすると子どもは悲しみます。楽しく面会できませんし、そのうち子ども自身が「会いたくない」と言い出すでしょう。
また、相手へ悪感情を持っているために「会わせたくない」と考える親権者・監護親もいらっしゃいますが、子どもにとって相手親は半身(親)であることを忘れてはなりません。相手親との関係を続けることが子どもの健全な成長につながるケースもよくあります。頑なすぎる態度はとらない方が良いでしょう。
03.面会交流を拒絶できるケース
以下のような事情があれば、面会交流を拒絶できる可能性があります。
- 相手が子どもに暴力を振るうおそれがある
- 相手が子どもを連れ去るおそれがある
- 相手が子どもに違法行為をさせるおそれがある
ただし、自己判断で面会交流を断るとトラブルのもとになります。弁護士による法的な見解を聞いておくと、お互いが納得しやすくなるので、この点でお悩みであれば弁護士にご相談下さい。

年金分割

夫婦のどちらかが会社員や公務員の場合は、年金分割についても取り決めておきましょう。
年金分割とは、婚姻中に払い込んだ「年金保険料」を分割する手続きです。年金そのものが分割されるわけではありませんが、婚姻中に払い込んだ年金保険料を按分することにより、将来の年金額が調整されます。
相手の給料が高い場合には年金分割を行うことによって受給額が増えますし、こちらの給料が高い場合に年金分割をすると受給額が減額されます。
年金分割には「3号分割」と「合意分割」があります。
01.3号分割
3号分割は、専業主婦などの「3号被保険者」が利用できる年金分割で、相手の同意がなくても年金分割の手続きができるものです。
2008年4月以降の3号被保険者に適用されます。3号被保険者とは、健康保険や年金で「相手の扶養に入っている人」です。
2008年4月以降ずっと3号被保険者だった人は、離婚時に相手と話し合いをしなくても離婚後に一人で社会保険事務所に行って年金分割の手続きができます。
02.合意分割
合意分割は「3号分割以外の年金分割」です。3号被保険者ではない人や、2008年3月以前から婚姻している人は合意分割しないと年金を分割してもらえません。
合意分割するときには、夫婦の双方が年金分割に合意する必要があります。その際「按分割合」も0.5(2分の1)までの範囲で自由に設定できます。
裁判所としては年金分割割合を0.5とすべきと考えているので、合意によって決めるときにも0.5にするようお勧めします。
03.年金分割の方法
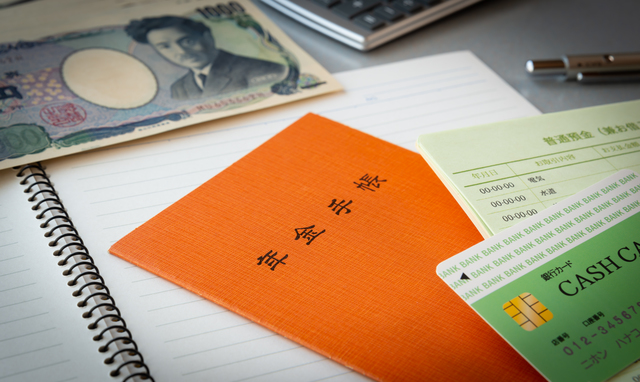
3号分割の場合
3号分割の場合、離婚後に3号被保険者が年金事務所に行けば一人で手続きできます。「標準報酬改定請求書」を書いて提出すれば、将来の年金額が自動的に調整されます。
合意分割の場合
合意分割の場合、まずは夫婦で年金分割について取り決めをして合意書を作成する必要があります。離婚後に夫婦で年金事務所に行き、二人で標準報酬改定請求書を作成して提出すれば年金分割の手続きが完了します。
ただし、離婚時の年金分割に関する合意書を公正証書にしておけば、単独でも申請可能です。離婚後に相手と年金事務所に行くのが難しい場合などには、公証役場で年金分割に関する合意書を作成しておくと良いでしょう。
離婚後の戸籍について

01.離婚後の戸籍は2種類から選ぶことができる
離婚すると、戸籍が変わります。
日本では女性が男性の戸籍に入っていることが多いので、以下、女性が男性の戸籍に入っていたケースで説明いたします。
このようなケースでは、離婚後、妻側が夫の戸籍から出ることになるのが一般的です。その際、妻側は、①新しく自分一人の戸籍を作るか、②実家の戸籍に戻るかを選べます。
基本的にどちらでもかまいませんが、離婚後も婚姻時の姓を名乗りたい場合には(これを「婚姻続称」と言います。)、自分一人の戸籍を作る必要があります。
02.子どもの戸籍に要注意
離婚の際は、子どもの戸籍に注意しましょう。
離婚時に母が親権者になったとしても、離婚後の子どもの戸籍は父親のもとに残ったままとなり、子どもの苗字(姓)も父親と同じとなります。
子どもの戸籍や姓を母親に揃えるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きをしなければなりません。
子の氏の変更許可申立てが認められて、家庭裁判所で審判が出て審判書を役所に持っていくことで、はじめて子どもの戸籍を母親の戸籍に入れられます。戸籍を母親のものに揃えた場合は、子どもの姓も母親と同じものになります。
なお、子どもの戸籍と母親の戸籍を揃えるには、母親を筆頭者とする独立した戸籍を作る必要があります。戸籍制度では「3世代」を同一の戸籍に入れることができないので、母親が実家の戸籍に入ったままでは子どもを母親の戸籍に入れられません。
子の氏の変更許可の審判書を持って子どもの戸籍を変更するとき、一緒に母親の新戸籍を作ることもできるので、離婚後いったん実家の戸籍に戻った場合にはまとめて手続きしましょう。
相手が離婚に応じない場合の対処方法

相手と離婚したいと希望しても、相手が離婚に応じないケースがあるものです。
そんなときには以下のように対処しましょう。
01.説得する
まずは、相手方に離婚に応じるよう説得してみましょう。
その際「なぜ離婚したいのか」「どうしても復縁できないのか」などしっかりと意思を伝えます。当初は軽く考えていても、こちらの決意が固いことがわかれば相手も離婚に応じる可能性があります。
02.別居する

同居したままでは相手の考えが変わらない場合、いったん別居するようお勧めします。別居すれば相手にとっても「配偶者のいない生活」が現実化し、「離婚」を真剣に検討せざるを得ない状況となるからです。
なお、子どもの親権を獲得したい場合、別居時には子どもと離れないことが大切です。家を出るなら必ず子どもを連れて出ましょう。
03.婚姻費用を請求する
収入が少ない場合等には、別居して相手に婚姻費用を請求しましょう。相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所で婚姻費用分担調停をすれば支払を受けられるようになります。
婚姻費用は離婚時まで支払義務が続くので、相手にとっては離婚しない限り毎月の高額な支払が必要な状況となるため、「離婚しよう」という判断に傾きやすくなります。
04.離婚調停を申し立てる
別居後話合いをしても相手が離婚に応じないなら、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停では調停委員が間に入って離婚の話合いが進められます。第三者から説得されれば、相手も離婚に応じる気持ちになりやすいものです。
ただし、こちらが「なぜ離婚したいのか」などの理由や離婚すべき状況をうまく説明できないと、反対に調停委員から「離婚を思いとどまってはどうか?」と説得されてしまうおそれもあるので注意が必要です。調停を有利に進めるには弁護士に依頼する方法がお勧めです。
05.弁護士に協議を依頼する

調停をしなくても、別居後弁護士に離婚協議を依頼すればスムーズに離婚できるケースが多々あります。弁護士が間に入れば、相手と直接話をする必要はありません。相手も「弁護士を立てられたらもはや離婚を避けられない」と思い、離婚を受け入れるケースが多いからです。
相手が離婚に応じてくれずお困りの方は弁護士に依頼することも検討しましょう。
まとめ
離婚を進める際には相手に離婚を切り出す前からの綿密な準備が必要です。相手の対応次第でこちらが取るべき手段も変わってきます。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では多数の離婚事案を解決してきた実績があります。離婚で不利にならないため、離婚後に後悔しないため、慰謝料や財産分与を少しでも多く獲得するためにもまずは一度ご相談下さい。





















