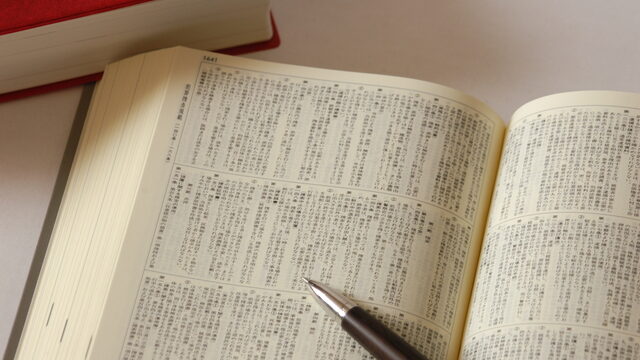ある人が逝去された際、相続人はその人が有する財産についてプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)のどちらも相続することとなります。
相続財産が負債だらけの場合は相続放棄という制度を利用することが有効です。相続放棄をすることで放棄者ははじめから相続人ではなかった扱いとなりますので、故人の相続財産の一切を相続することがなくなります。それゆえに相続によって負債を負うという事態を避けることができるのです。
しかし、この相続放棄は必ずしも認められるものではありません。相続発生後の行動次第では相続放棄をすることができなくなってしまうことがあります。どのような行為をしてしまうと相続放棄が認められなくなってしまうのか正しい知識を身に付けておきましょう。
今回の記事では、相続放棄とは何か、相続放棄が出来なくなってしまうケース等について弁護士が解説します。相続放棄を検討されている方は是非参考にしてみてください。
用語の解説
01.用語の確認
まず最初に相続に関連する用語を確認しましょう。
相続
相続とは、亡くなった人の財産上の権利義務を承継することを言います。
被相続人
被相続人とは、亡くなった人のことを言います。
相続人
相続人とは、被相続人の財産(相続財産)を相続する人のことを言います。
相続財産
相続財産とは、被相続人が有していた財産上の権利義務の一切のことです。現金や預貯金といった正の財産はもとより、銀行に対する負債や滞納している税金などの負の財産も相続財産となります。
02.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産についての権利義務の一切を放棄する意思表示のことをいいます。
相続放棄が認められた場合、その人は初めから相続人ではなかった扱いとなるので相続財産に一切関与しません。すなわち正の財産も負の財産も一切相続することはありません。
たとえば、多額の負債を残した被相続人を相続してしまうと、相続後に「自分が作ったわけでもない負債」を返済しなくてならなくなってしまいます。経済的にも精神的にも苦しくなるでしょう。このような場合、相続放棄をすればそもそも負債を相続することもないので今まで通りの生活を送ることができます。
正の財産だけを相続することはできない
相続の場面において、正の財産だけを相続し負の財産については放棄する(一切相続しない)ということは出来ません。そんな虫の良い話は無いということです
なお、限定承認(正の財産の範囲内でのみ負の財産を相続する)と混同してしまいがちですが、限定承認は正の財産も負の財産も相続していますので、正の財産のみを相続したというわけではありません。
03.相続放棄はどうやって行うのか
相続放棄は、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をすることで行ないます。
これもよくある誤解なのですが、家庭裁判所に申述せずに単に「自分は相続放棄します」と主張しただけでは相続放棄は成立しません。家庭裁判所に対し相続放棄の申述をしてはじめて相続放棄の効果が生じるのです。
なお、相続放棄の申述は、被相続人(亡くなられた方)の住所地または相続開始地の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書を提出する形で行ないます。
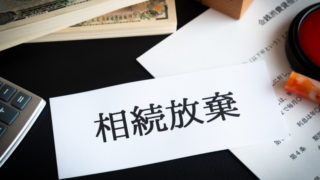
相続放棄が出来なくなるケース
相続財産が負債超過の場合には非常に有効となる相続放棄ですが、必ず認められるわけではありません。
- 熟慮期間を経過した
- 単純承認が成立するような行為を行なった(法定単純承認)
上記のケースでは相続放棄は認められません。正の財産も負の財産もひっくるめて相続してしまうことになるので注意しましょう。

熟慮期間

まずは熟慮期間について確認しましょう。
01.熟慮期間とは
熟慮期間とは、相続人が相続について相続放棄するか限定承認するか単純承認するかを決めるための猶予期間(考慮期間)です。
熟慮期間を経過してしまった場合、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理しません。すなわち熟慮期間を経過すると相続放棄が出来なくなってしまうということです。熟慮期間には注意しましょう。
02.熟慮期間はいつまで?
熟慮期間は「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」です。
多数のケースにおいて自分のために相続があったことを知った日は、「被相続人の死亡を知った日」と重なります。被相続人が死亡した事実を知ったら早急に相続について検討しましょう。
相続財産について調査し、正の財産がどの程度あるのか負の財産がどの程度あるのかをしっかりと確認したうえで相続するのか相続放棄するのかを検討しましょう。
相続財産の調査がうまく薦められない場合は弁護士に相談することを推奨します。

03.熟慮期間経過後の相続放棄が認められるケース
熟慮期間(相続があったことを知ってから3ヶ月)を経過していても、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。
相続人に相続財産が存在しないと信じていたケース
以下の両方の条件を満たす場合には、例外的に相続放棄が認められます。
- 被相続人に相続財産が全くないと信じていた
- そう信じることが相当と認められる事情があった
たとえば、生前に相続人と交流がまったくなく被相続人が生活保護を受けていると聞いていた場合には遺産がないと信じてもやむを得ないといえるでしょう。このような場合は熟慮期間を過ぎていたとしても相続放棄することができる可能性が高いといえます。
相続財産の一部を知っていても相続放棄できるケース
遺産の一部を認識していたとしても例外的に相続放棄できるケースがあります。
それは「自分が相続する財産がないと信じていて、かつそう信じることに相当な事情がある場合」です。
たとえば、遺産があると知っていたがそれらはすべて特定の相続人が相続する内容の遺言書が遺されていて、自分が相続する財産はないと信じていた場合は熟慮期間が経過していても相続放棄が認められる可能性があるといえるでしょう。
単純承認

01.単純承認とは
単純承認とは、被相続人のすべての権利義務を承継することを承認することです。特別な手続きは不要です。
熟慮期間を経過すれば自動的に単純承認をしたことになります。
02.法定単純承認とは
熟慮期間中にある行為をしてしまうと法律上当然に単純承認が成立してしまうことがあります。これを法定単純承認といいます。
法定単純承認に該当する行為を行なった場合、相続人の意思に関係なく単純承認を選択したとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなってしまいます。
相続放棄を検討するのであれば、法定単純承認に該当してしまう行為は避けなければなりません。
03.法定単純承認が成立する行為
法律上は、以下のようなことをしてしまうと法定単純承認が成立すると規定されています。
- 相続財産の全部又は一部を処分した場合(民法921条1号)
- 熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合(民法921条2号)
- 相続財産を隠匿・消費した場合(民法921条3号)
なお、①については、相続財産の現状を変更しない「保存行為」をしただけであれば法定単純承認は成立しません。
法定単純承認に該当する行為、該当しない行為を具体的に確認してみましょう。

法定単純承認に該当する行為
以下のような行為は法定単純承認と判断されてしまいます。
01.被相続人の物を引き継いだ
被相続人の所有物であった高価な時計を承継する、被相続人が買っていた高価なペットを引き取るといった行為には法定単純承認が成立します。
相続放棄を検討しているのであれば、安易に被相続人の所有物に手を出したりしないようにしましょう。
02.預貯金を使った、口座を解約した
- 被相続人名義の預貯金を自分のために使う
- 被相続人名義の口座を解約する
- 被相続人名義の証券口座で取引を行なう
被相続人名義の口座に関与する行為の大半が法定単純承認に該当します。相続放棄をするのであれば預貯金には手を付けてはいけません。
03.不動産や車などの名義を変更した

- 被相続人名義の不動産の名義を変更した
- 被相続人名義の自動車の名義を変更した
- 被相続人名義の株式の名義を変更した
被相続人名義の財産の名義変更を行う行為は、法定単純承認に該当します。
04.株式の議決権を行使した
被相続人が株式を保有していた場合に株式の議決権を行使してしまうと法定単純承認が成立してしまいます。安易に議決権行使をしないように注意しましょう。
05.遺産分割協議に参加した
遺産分割協議に参加し、被相続人の財産を受け取る行為や自分以外の相続人に遺産を承継させると決めたりする行為は相続財産を処分したことになるので法定単純承認が成立してしまいます。
相続放棄したいなら遺産分割協議に参加すべきではありません。
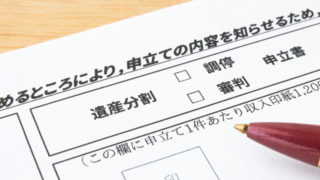
06.遺産を隠した
被相続人の遺産を隠した場合は法定単純承認が成立します。遺産を自分だけが分かる場所などに持ち去った場合も同様です。
相続放棄したいのであれば価値のある宝石や時計などを持ち去ってはなりません。

07.家を増改築した
遺された自宅を改築する行為は法定単純承認が成立する可能性があります。改築は不動産の相続を前提とする行為であり自宅の現状を変更する行為です。相続放棄を検討されている場合は止めておきましょう。
なお、最低限の修繕を行った程度であれば保存行為として法定単純承認が成立しないこともあります。
法定単純承認に該当しない行為
以下の行為であれば法定単純承認とは判断されません。
01.経済的価値のないものの形見分け
経済的価値のないものについての形見分けは処分行為に当たりません。
たとえば、被相続人が身につけていた衣類やアクセサリー、時計(経済的価値のないものに限る)などを形見分けしても法定単純承認は成立しません。
02.食品の処分
被相続人が食品を遺していた場合、放っておくと腐敗してしまいます。そのため、食品を処分しても(食べてしまっても)法定単純承認にはならないと考えられています。
03.被相続人のペットの世話

ペットは被相続人の財産にあたるため、価値のあるペットを相続人が引き取ってしまうと法定単純承認が成立する可能性があります。
他方で引き取り手が見つかるまで世話をするだけであればそれは保存行為に該当しますので法定単純承認が成立する事由にならないとされています。
命あるものは大切にすべきです。被相続人がペットを遺していた場合、法定単純承認をおそれずに必要な世話をしてあげましょう。

04.自宅の最低限の補修
被相続人名義の不動産の老朽化が激しく修繕しないと倒壊しそうなケースで、必要な限度で補修を行う行為は保存行為と評価されますので法定単純承認には相当しません。
05.相続人の資産から被相続人の債務を弁済した
相続人の有している資産から被相続人の債務を弁済しただけであれば法定単純承認は成立しません。
他方で相続財産から被相続人の債務を弁済した場合は、原則として法定単純承認が成立してしまいます。
06.少額の未払いの医療費を支払った
被相続人の遺した財産から未払いの医療費(少額)を支払いをしても法定単純承認に該当しないと判断された事例があります(大阪高決昭和54年3月22日)。
なお、未払い医療費が高額な場合は相続財産の処分に該当して相続放棄できなくなる可能性もあります。自己判断すると取り返しがつかなくなってしまう可能性もあるので迷ったときは弁護士に相談しましょう。
07.死亡保険金を受け取る

被相続人が生命保険に加入していて指定された受取人が相続人である場合、生命保険の死亡保険金を受け取ったとしても法定単純承認は成立しません。
死亡保険金は遺産ではなく受取人固有の財産と評価されるためです。
受取人が被相続人の場合は注意
保険金の受取人が被相続人本人の場合、保険金の受給権は相続財産となります。この場合に相続人が保険金を受け取ってしまうと法定単純承認が成立してしまうので注意が必要です。
たとえば医療保険における入通院に関しての保険金は本人が受取人に指定されているケースが多数です。つまり相続財産に含まれるものとなります。これを受け取ってしまうと相続放棄できなくなってしまいますので相続放棄したい場合は保険金の受取人をしっかりと確かめましょう。
08.葬儀費用を支払った
被相続人の財産から葬儀費用を支払っても法定単純承認になりません。同様に被相続人の財産から仏壇や墓石の購入費用を支出しても法定単純承認にはなりません。
ただし、支出できる金額に限度があります。社会的に見て不相当なほど高額な支出をしている場合は処分行為と判断されて法定単純承認が成立する可能性があります。相続放棄を検討している場合には高額な葬儀費用や仏壇・墓石の購入をしないように常識的な範囲で対応しましょう。
09.仏壇やお墓、仏具などの祭祀財産を受け継ぐ
仏壇やお墓、仏具などの先祖を祀るための資産を祭祀財産といいます。
民法上、祭祀財産は一般の遺産と異なる取り扱いを受けています。祭祀財産を引き継ぐのは祭祀承継者であり必ずしも法定相続人とは限りません。また、祭祀承継者として祭祀財産を受け取っても法定単純承認は成立しません。
遺言や慣習、話し合いなどによって仏壇仏具、お墓などを引き継ぐことになっても相続放棄はできますのでご安心ください。
10.香典や御霊前を受け取る
香典や御霊前は葬儀の主宰者(いわゆる喪主)へ支払われるお金であって遺産ではありません。
そのため、これを受け取っても法定単純承認は成立しません。
また、相続放棄した人が喪主になった際に香典を受け取っても法的には問題はありません。
11.葬祭費、埋葬料を受け取る
葬祭費は国民健康保険や後期高齢者医療制度から、埋葬料は健康保険組合から支給されるものです。
葬祭費や埋葬料については一定の要件を満たす人が受け取れる固有の財産なので相続財産になりません。受け取っても法定単純承認は成立しないと考えましょう。
12.未支給年金を受け取る

未支給年金とは、年金受給者が死亡した際に未払いになっている年金をいいます。
年金は後払いなので、年金受給者が死亡すると死亡した月までの年金が一部未支給となります。未支給年金は一定の要件を満たす親族などが請求して受け取れることができます。
相続人がこの未支給年金を受け取ったとしても法定単純承認は成立しません。
相続放棄しても未支給年金は受け取れます。法定単純承認も成立しないので安心して申請しましょう。
13.遺族年金を受給する
遺族年金とは、年金受給権者が死亡した際に遺族に支給される年金であり、死亡した方の遺族の生活保障のために支給されるお金です。相続とは全く別の制度によって支給されるもので遺族固有の権利と理解されています。
そのため遺族年金を受給しても法定単純承認は成立しませんし、相続放棄した方でも遺族年金の申請ができます。
遺族年金の申請には期限もあるので受給資格のある方は早めに申請しましょう。
まとめ
相続放棄できる場合とできない場合の区別については非常に複雑であり、専門知識がないと適切な判断は困難といえます。
安易な自己判断で行なった行動により法定単純承認が成立してしまったら相続放棄できなくなったり相続放棄の申述が無効になったりしてしまうリスクも発生します。相続放棄を検討しているのであれば、自己判断せずに弁護士へ相談しましょう。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では遺産相続の案件に力を入れて取り組んでいます。相続人の立場になられた方、相続放棄を検討されている方はお気軽にご相談ください。