昨今では「終活」というワードが注目を集めています。終活とは自身の人生の終焉に向けての準備をする活動のことです。
終活の一環として、自分の死後、遺された家族が遺産相続で揉めないように取り計らっておくことが推奨されています。遺言書を作成しておくことで遺産相続でのトラブルが生じないように備えることが可能となります。
遺言の遺し方にはいくつか種類がありますが、その中で最もポピュラーなものは自身で自筆した自筆証書遺言でしょう。
なお、自筆証書遺言を作成する上では守らなければならないルールがあり、ルールを破ってしまうと遺言そのものが無効となってしまうため注意が必要です。
今回の記事では、自筆証書遺言についてのメリットやメリットやデメリット、作成時の注意点などについて解説します。
自筆証書遺言

01.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者本人がすべて自筆で記載する遺言書です。
自筆すなわち自分で記載することが条件となっておりますので、パソコンで作成した文書を印字したものや弁護士や血縁者などが代書したものでは自筆証書遺言としては無効となります。
なお、2019年の法改正により「すべて自筆」の要件の一部が緩和されています。

02.法改正による自筆証書遺言の方式緩和
今までは、自筆証書遺言はすべて遺言者本人の自筆で書かなければならないものとされておりました。
すべてを自筆することはかなりの体力的負担を強いるものです。遺言書を作成する方の大多数が老齢の方であることを考慮すると好ましいとはいえません。また、遺産が多岐にわたる場合にも自筆を求めることは記載漏れや記載不備が発生する要因ともなります。
上記の問題点に対応すべく2019年1月に法改正がなされ、自筆証書遺言の『財産目録の部分』についてのみ下記の対応でも認められることになりました。
- パソコンでの作成
- 代書
- 預貯金について通帳の写しの添付
- 不動産について登記簿謄本の写しの添付
なお、上記の形式で作った財産目録についても遺言者の署名押印は必要です。
自筆以外の方法が認められるのはあくまで財産目録の部分だけであり、財産目録以外の部分は自筆であることが要求されますので注意しましょう。


自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットとしては以下のものが挙げられます。
- ひとりですぐに作成できる
- 費用が掛からない
- 他人に内容を知られずに済む
01.ひとりですぐに作成できる
1つ目のメリットは、ひとりですぐに作成することが可能という点です。
自筆証書遺言は、自身の好きなタイミングで作成することが可能です。紙とペン、印鑑があれば作成できます。
また、作成の際に他者に立ち会ってもらう必要はありませんので、手間をかけずに遺言を作成できます。
他方で自筆証書遺言以外の遺言方法である公正証書遺言や秘密証書遺言では、作成の過程で公証人や証人といった第三者の介在が必要となります。そのため、ひとりですぐに作成できるものではありません。
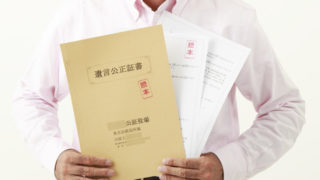
02.費用が掛からない
2つめのメリットは、費用が掛からないという点です。
公正証書遺言や秘密証書遺言ではその作成過程で数万円程度の費用が発生しますが、自筆証書遺言ではその作成過程において費用は生じません。
03.他人に内容を知られずに済む
3つ目のメリットは、遺言の内容を他人に知られずに済むという点です。
公正証書遺言の場合は作成過程において遺言の内容を公証人に知られてしまうこととなりますが、自筆証書遺言及び秘密証書遺言は他者に内容を知られることはありません。
自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットとしては以下のものが挙げられます。
- 無効になりやすい
- 相続の内容について明文化しなくてはならない
- 自筆しなければならない
- 破棄隠匿、変造される可能性がある
- 発見されない可能性がある
01.無効になりやすい
デメリットの一つ目は、無効になりやすいことです。
自筆証書遺言の様式や記載する内容、作成時のルールについてはそこまで難しいものではありません。法律の知識をそこまで有していなくとも作成することはできるでしょう。
ですが、自筆証書遺言は、所定のルールに則って作成されなかった場合にはそのすべてが無効となってしまいます。自身だけで作成すると以下のようなケアレスミスが生じてしまう可能性は否めません。
- 財産目録以外の書面をPCで出力してしまった
- 日付の記載を忘れた
- 署名捺印を忘れた
- 加除訂正の仕方に誤りがあった
たったひとつのミスでも無効となることから、独力で作成した自筆証書遺言には無効となるリスクが内在しているといっても過言ではないでしょう。
02.相続の内容について明文化しなくてはならない
デメリットの2つ目は、相続の内容について明文化しなくてはならないことです。
遺言書は法的拘束力を持つ特別な文書です。書き方が間違っていたり曖昧だったりすると、無効になったり意図したものと異なる解釈をされてしまったりすることがあります。
特に解釈の仕方が割れてしまうような標記・表現であると、それぞれの相続人が自分にとって都合良く解釈したり、都合の悪いことが書かれている相続人が「この遺言書は偽造だ」と言い出したりなどのトラブルに発展することも考えられます。
03.自筆しなければならない
デメリットの3つ目は、自筆しなけれなならないという点です。
老齢の方からすると自筆すること自体が体力を使う大変な作業となります。病気等を理由に自筆ができない状況にあることもあります。
そのような事情があったとしても自筆証書遺言は自筆での作成が要求されます。それゆえに体力面、健康面で不安のある方は自筆証書遺言の作成が困難といえるでしょう。

04.発見されないリスクがある
デメリットの4つ目は、発見されないリスクがあることです。
自筆証書遺言を他者に秘密で保管する場合、遺言書が発見されるまでに時間がかかることがあります。発見されればまだ良い方で誰も遺言の存在に気が付かないままというケースも想定されます。
遺言を確実に発見してもらいたいのであれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に保管してもらうか、遺言書作成の記録が残る公正証書遺言か秘密証書遺言を採用した方が良いでしょう。

05.破棄隠匿、変造のリスクがある
デメリットの5つ目は、相続人等によって破棄隠匿、変造のリスクがあることです。
ほとんどの方は、自筆証書遺言作成後、遺言書を自身で保管します。自宅で保管する方が多いことでしょう。この遺言書を他人が発見した際、遺言の内容が発見者に都合の悪い内容であったら発見者が遺言書を隠したり捨てたりしてしまうかもしれません。都合の良い内容に書き替えられてしまう可能性もあります。
自筆証書遺言の書き方
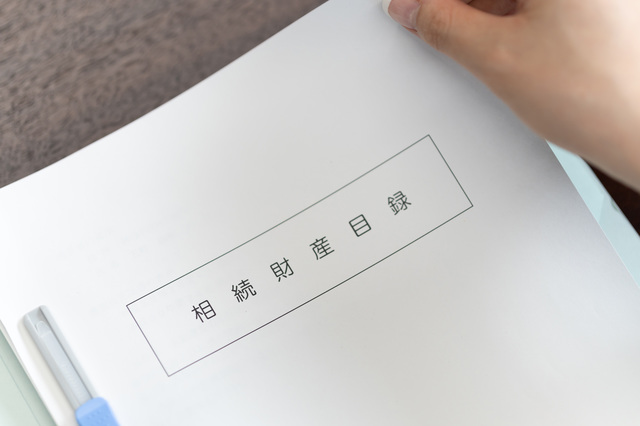
自筆証書遺言の作成方法について解説いたします。
01.雛形や遺言書を作成する
まずは雛形や文例を用意します。
ネットや市販の書籍で雛形や文例を確認することが出来ますので用意することは難しいことではありません。
02.自身の財産を疎明する資料を用意する
自分にはどのような財産があるのかを正確に把握していなければ遺言書を書くことはできません。自身の財産を把握するための資料を用意しましょう。
資料としては以下のものが挙げられます。
- 預貯金通帳
- 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
- 株式の資料
- 仮想通貨の資料
- 生命保険証書
- 家具や芸術品などの動産の明細書 等
03.遺言書を作成する
自筆証書遺言の雛形に従って遺言を書いていきましょう。なお、自筆証書遺言には次の3つを記載しなければなりません。
- 自筆証書遺言を作成した日付
- 遺言の内容
- 本人の署名押印
漏れがあると遺言は無効になってしまいますので注意しましょう。
また、以下の点にも留意しましょう。
- 自筆で作成する
- あいまいな表現をしない
- 必要に応じて財産目録を作成する
①についてですが、財産目録以外は自筆が必須です。自筆以外で対応してしまうと無効となるため注意しましょう。
②についてですが、あいまいな表記があると、遺言書そのものが無効となったり相続人間で争い・対立が起こってしまうことがあります。複数の解釈ができるような表現は避けて作成しましょう。どのように表記するのがベストなのかがわからない方は、弁護士に自筆証書遺言のチェック作業についてお願いすることも検討しましょう。
③についてですが、相続財産が多岐にわたる場合には必要に応じて財産目録を作成しましょう。
財産目録とは、遺言者にどんな遺産があるのかが記載された一覧表のことです。資産と負債、それぞれの内容と合計額を記載し、相続人が遺言書と照らし合わせて確認できるようにしておきましょう。なお、財産目録については自筆でなくともOKです(署名捺印は必要)。

04.遺言執行者を指定する
可能であれば遺言執行者をつけておきましょう。
遺言執行者とは遺言者の死亡後に遺言内容を実行する人のことです。信頼できる弁護士を遺言執行者に指名しておけば相続の手続きはスムーズに進むことでしょう。
なお、遺言執行者を指定する方法としては以下のものがあります。
- 遺言に書いて指定する
- 第三者に遺言執行者をしてもらうよう遺言に書く
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所で遺言執行者を選んでもらう

自筆証書遺言を書くときの注意点

人間である以上、どんなに気を付けていてもミスをする可能性はあります。
一般的な行為であればミスに気付いた時点で間違いを正すことで対応ができるのですが、遺言についてはそうもいきません。
遺言書のミスはほとんどの場合遺言者の死後に発覚するからです。遺言者がもういない以上ミスの訂正は誰にもできません。また、自筆証書遺言でのミスは、遺言書の無効に直結するため、ミスの影響が非常に大きいものとなります。
自筆証書遺言を書くときに特に気を付けてほしいポイントをお伝えします。
01.必ず自分で手書きする
自筆証書遺言は、必ず遺言者本人が自筆(手書き)しましょう。
「何度も言われなくてもそんなことはわかってるよ」と思われるかもしれませんが、これは本当に大切なことです。一部でもパソコンで作った部分や本人以外の書いた部分があれば遺言は無効になってしまいます。
02.曖昧な書き方をしない
自筆証書遺言の内容は、誰が読んでも1つの解釈しかできないような厳密な書き方で記載してください。曖昧な表現や解釈の仕方が割れそうな書き方をしてはいけません。
たとえば「遺産を受け継がせる」という意味の言葉にも「譲る」「相続させる」などのいろいろな表現・言い回しがありますが、遺言書においては「譲る」「渡す」などの表現は避けて「相続させる」「遺贈する」などの表現を使うようにしましょう。
また、どの遺産を誰にどのくらい相続させるのか明確に示さなければなりません。財産目録と遺言書を照らし合わせ、誰が読んでも同じ解釈になる書き方になっているかどうか確認しましょう。
03.加除訂正のルールを守る
自筆証書遺言で書き間違いをした場合の加除訂正のルールも決まっています。
加除訂正のルール
- 間違った部分を二重線で消す
- 書きなおしたいことを吹き出し【{ 】を使って書く
- 余白に消した字数を「〇字削除」、足した字数を「△字加入」と書く
- 加除訂正した部分に署名押印する
上記のルールに従わない方法で対応した場合、遺言書が無効となってしまうので注意しましょう。特に「削除」「加入」の記載や署名押印は忘れやすいので注意が必要です。
さいごに
有効な遺言書を残すことが出来れば、自分が人生の幕を閉じた後、遺された人たちに最後の贈り物をすることができます。誰に何を遺すのかを指定すれば相続を原因としての争いも避けられるでしょう。
逆に遺言が無効となってしまった場合には、相続人間でトラブルが発生する可能性もあります。無効とならないよう正しい方法で遺言を残すべきでしょう。
なお、遺言の内容を確実に実行したいのであれば自力で作成した自筆証書遺言はおすすめできません。「公正証書遺言で対応する」か「弁護士に事前に内容をチェックしてもらった自筆証書遺言」で遺言を残すことを推奨いたします。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、相続問題に注力しており。遺言書の作成等の相談についても広く受け付けております。遺言や相続についてお悩みの方は是非一度ご相談ください。






















