人が死亡すると、亡くなられた方が有していた財産や負債を相続人が引き継ぐこととなります。
相続人が複数人いる場合や相続財産が多岐にわたる場合には、遺産分割によって誰がどの遺産を取得するかを取り決めなければなりません。
今回の記事では遺産分割の進め方について解説します。
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(死亡した人)が残した遺産(財産や負債の一切)を相続人が分割承継する手続きです。
有効な遺言書がない限り、被相続人が残した財産や負債は法定相続人が相続します。
法定相続人とは民法が定める相続人のことであり、被相続人との親族関係に応じて決まります。また、法定相続人毎に遺産の取得割合も定められており、この取得割合のことを法定相続分と言います。
なお、民法には法定相続分(各々の取得割合)については定められているのですが、具体的な遺産の分割方法については定められておりません。どういうことかというと、たとえば遺産として不動産と預貯金、車が残されたとして、どの相続人がどの遺産を取得すべきかについては民法では定められていないということです。そのため、誰がどの財産を取得するのかについては、法定相続人が協議して決めなければなりません。
相続人らが遺産を分け合う手続きを遺産分割といい、遺産分割の内容・方法を決めるための話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産分割を行なって遺産分割協議書を作成しない限り、不動産の名義書換や預貯金の払戻などを行なうことが出来ません。相続が発生したら早めに遺産分割に取り組みましょう。

遺産分割の方法

遺産分割のやり方としては、以下の3種類があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
01.現物分割
現物分割は、遺産をそのままの形で取得する方法です。物理的に分割可能であれば分割することもあります。
たとえばA氏の遺産として資産価値が同等の建物(不動産)が2戸あって、A氏の子2名(X・Y)が相続人である場合、X・Yで建物を1戸ずつ相続するといったやり方です。
また、A氏の遺産として土地が1筆ある場合には、これを2筆に分筆し1筆ずつ相続する方法も現物分割にあたります。
02.代償分割
代償分割は、遺産を相続した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払う方法による分け方です。
たとえばA氏の遺産が1000万円の価値のあるマンション1戸であって、A氏の子2名(X・Y)が相続人である場合、Xがマンションそのものを相続し、XがYに対し代償金としマンション評価額の2分の1である500万円を支払うといったやり方です。
03.換価分割
換価分割は、遺産を売却(換価)することで得た売却金を法定相続人で分け合う方法です。
たとえば、A氏の遺産が1000万円の価値のあるマンション1戸であって、A氏の子2名(X・Y)が相続人である場合、マンションを売却することで得た金額1000万円をXとYとで500万円ずつ(2分1ずつ)取得するといったやり方です。
04.共有のまま維持
分割をせずに共有するという方法もあります。
たとえば、A氏の遺産が1000万円の価値のあるマンション1戸であって、A氏の子2名(X・Y)が相続人である場合、マンションの持ち分をXとYで2分の1ずつとして共有するといったやり方です。
しかし、共有にしておくことはあまり好ましくありません。共有であることは、不動産を活用する際に障害になることがありますし、共有者の間で将来トラブルが生じる可能性もあります。
デメリットを避けるためにも共有にはせずにしっかりと遺産分割を行なっておきましょう。


遺産分割の流れ

遺産分割の流れについても確認しておきましょう。
01.相続人調査を行う
遺産分割について話し合う(協議する)遺産分割協議にはすべての法定相続人が参加する必要があります。そのため、まずは誰が相続人となるのかを明らかにしなければなりません。この相続人を確定させるための調査のことを相続人調査といいます。
相続人調査のやり方ですが、まずは被相続人(亡くなられた方)が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得します。また、被相続人の相続人となり得る方の戸籍を現在戸籍に至るまで取得します。
なお、相続人調査は慣れていない人が行なうと手間がかかります。また、相続人を確定させるには民法の知識が必要です。相続人を確定させることが難しいようでしたら専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。

02.相続財産調査を行う
次に遺産の内容を調べます。遺産分割協議をするためにはその遺産の範囲が明らかになっていなければならないためです。
なお、遺産は正の財産・プラスの財産だけとは限りません。負の財産すなわち負債も遺産にあたります。プラスの財産のみならずマイナスの財産もしっかりと調査しましょう。
03.遺産分割協議を行う

相続人と相続財産を確定させることができたら、遺産分割協議を行ないます。
遺産分割協議とは、法定相続人が話し合いによって遺産分割方法を決定する手続きです。遺産分割協議には相続人が全員参加しなければなりません。参加していない者がいる場合は有効とはなりません。


04.遺産分割協議書を作成する
遺産分割の内容(誰が何を相続するか、どのように相続するか)について相続人全員が合意した場合は、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。
遺産分割協議書は、不動産名義の書き換えや預貯金の払い戻しなどの具体的な相続手続きに必要となる重要書類です。
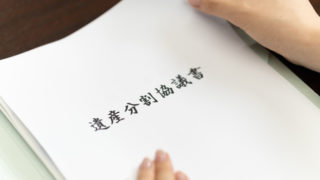
05.遺産分割調停・審判を行う
遺産分割について相続人で話し合いをしても合意に至らなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行ないましょう。
遺産分割調停では調停委員や調停官(裁判官)が関与するので、法律的に妥当な内容の解決をしやすいといえます。調停委員や法律に詳しい調停官が話し合いを誘導してくれるので、おおむね法律の考え方に沿って公平な解決を実現できますし、極端な主張をする相続人がいたらその主張内容が実現困難であることを調停委員から説得してもらうことができます。
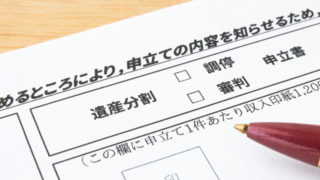
調停でも合意に至らなかった場合には調停不成立となり、遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では審判官(裁判官)が遺産分割の方法を決定します。
審判になると当事者の希望しない方法による分割方法が選択される可能性もあります。たとえば誰が相続するかでもめてはいるものの不動産は残す方向で進めたいと相続人らは考えていたとしても、審判官が換価分割を選択した結果不動産が処分されてしまうこともありえます。
そのため、遺産分割は審判の前段階すなわち話し合いによって解決する方が望ましいといえるでしょう。
さいごに
多くのケースで遺産分割は高額の財産を得る手続きとなります。財産(金銭)が絡む問題であることもあって、遺産分割の場面では相続人で意見が合わずにトラブルになってしまう例が多々あります。
相続手続きに不安がある場合には、相続が「争続」になってしまう前に、専門家である弁護士に相談してみましょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所は、相続トラブルについて多数の解決実績を有しております。相続問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら是非一度ご相談下さい。






















