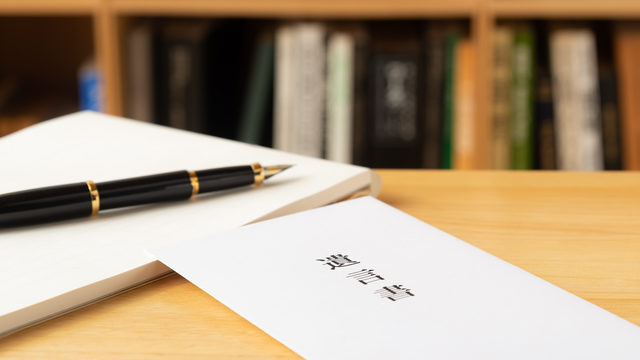相続税対策の方法には生前贈与を利用した節税のほかにも、養子縁組制度や不動産等を利用したものがあります。
今回の記事では、養子縁組制度や不動産、その他の方法を利用しての相続税の節税を達成する方法について解説します。
養子縁組
01.基礎控除
相続税には基礎控除があり、相続人の人数が多いほど基礎控除額が上がります。
相続税の基礎控除
3000万円+法定相続人数×600万円
たとえば相続人が2人なら基礎控除額は4200万円ですが、4人になると5400万円までが相続税非課税となります。
養子縁組をして相続人を増やすことで基礎控除額が上がりますので、相続税の節税を図ることが出来ます。なお、養子による控除は無制限ではありません。
実子がいない場合、相続人としてカウントできる養子は「2人まで」です。実子がいる場合、相続人としてカウントできる養子は「1人だけ」です。
02.養子縁組で節税する際の注意点
養子縁組で節税を図る際の注意点のひとつに相続税の2割加算があります。孫を養子にした場合、孫養子の遺産相続分については相続税が2割加算されることとなります。そのため、状況によってはあまり節税効果を得られないこともあり得ます。事前にシミュレーションしておきましょう。
また、養子も相続人として遺産分割協議に参加しなければなりません。養子の人数が増えたり他の相続人との関係性が薄かったりすると、話し合いがまとまりにくくなる可能性もあります。
相続人たちがトラブルを起こさないよう生前に遺言書を作成しておいたほうが良いでしょう。


不動産を利用しての相続税の節税方法

不動産を使った相続税の節税方法を見ていきましょう。
01.不動産を購入
現金・預金の多い方は、不動産を購入しておくと相続税を節税できる可能性があります。
不動産の相続税評価額は時価より低く、一般的に土地ならおよそ8割程度、建物ならおよそ7割程度にまで下がるケースが多数となっています。たとえば1億円の現金で土地を購入すると、遺産評価額は8000万円程度にまで下がります。
資産評価額が下がれば、その分相続税額も低額に抑えることが可能です。
02.不動産を賃貸
不動産を所有している場合、その不動産を賃貸するとさらに相続税評価額を下げることができます。
賃貸不動産を評価する際は借地権価格や借家権価格を差し引くので、もともとの土地や建物の相続税評価額より低くなるためです。土地の場合にはもともとの評価額の6~7割程度にまで下がるケースが多く、建物の場合には4割程度にまで下げられる可能性があります(不動産の所在地等の条件によって変わります)。
すでに建物を所有しているなら賃貸に出すことで、土地を所有しているのであれば賃貸アパート等を建築して活用するとよいでしょう。
03.賃料や収益不動産を贈与
収益不動産を所有している方は、受け取った賃料や収益物件そのものを子どもや孫へ贈与する方法も有効です。
賃料を贈与する場合、毎年110万円までなら贈与税が非課税なので超過する分のみ贈与税を払えば済みます。
収益物件そのものを贈与した場合、不動産には相続税がかかりません。贈与後の賃料は全額受贈者が受け取るので所得税等もかからなくなります。

債務控除を利用
相続税の債務控除を使って節税する方法があります。
債務控除とは、被相続人の借金などの負債を遺産評価額から減額することです。
01.葬儀代の支払
葬儀代も債務として算入できますので、葬儀に高額な費用をかければ相続税の節税につながります。
もちろん葬儀という行為の性質上、節税のためだけに無理に盛大な葬儀をすべきという意味ではありません。「葬儀代は遺産から控除できる」という知識をもった上で、生前に自分の希望する葬儀を取り決めて予約しておくとよいでしょう。
02.祭祀財産を購入
仏壇や仏具、お墓などの祭祀財産には相続税がかかりません。生前に立派な墓石や仏壇仏具などを購入しておくとその分現金を減らせて節税になります。
なお、相続開始後にお墓等を購入しても相続税の控除は受けられません。祭祀財産を購入するのであれば生前に済ませておく方がお得といえます。また、黄金の仏像など経済的に価値の高いものについては課税対象になる可能性があります。
生命保険を利用する方法

生命保険を利用した節税対策方法も有効です。
01.死亡保険金の控除枠を利用
死亡保険金には以下のとおり、相続税の控除制度がもうけられています。
法定相続人数×500万円
たとえば配偶者と2人の子どもが相続人となる場合、3人×500万円=1500万円までの金額を控除できるので、死亡保険金額が1500万円なら課税されません。
なお、同様の控除制度が死亡退職金にも設定されています。終身保障の生命保険に加入して遺される家族を死亡保険金受取人に指定しておくとよいでしょう。
同族会社などの場合、死亡退職金制度を作っておくと同様の効果があります。
02.生命保険の掛け金を贈与
生命保険を利用した節税方法としては、掛け金を贈与する方法もあります。
この方法を適用するには、相続人などの遺される家族を契約者とし、死亡保険金の受取人も同じ人にします。そのうえで被保険者を被相続人にして、被相続人が死亡したときには家族に死亡保険金が払われるように設定します。
- 契約者:子どもなどの遺される家族
- 被保険者:被相続人
- 保険金受取人:子どもなどの遺される家族
この状態で被保険者である被相続人が保険の掛け金を支払います。掛け金は贈与扱いとなりますが、年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
被相続人が亡くなったときには、家族が死亡保険金を受け取ることとなりますがこれには相続税はかかりません。所得税がかかりますが相続税より低くなるケースが多数です。

配偶者控除
01.配偶者控除
配偶者控除は、配偶者が相続人となるときに以下の大きい方の金額までは相続税がかからないとする制度です。
- 法定相続分
- 1億6千万円
控除額が大きいため、配偶者が相続する場合には多くのケースで非課税になります。
02.配偶者控除の注意点
配偶者控除を適用する場合には、二次相続に注意しなければなりません。
二次相続とは、1人目の被相続人が死亡し(一次相続)、続いて一次相続の相続人となった2人目の相続人が死亡して発生する相続です。
典型的な二次相続としては『父親が死亡して母親と子どもが相続し、その後母親が死亡して子どもたちが相続する』ものです。
父親の一次相続の際に配偶者控除を適用して多くの遺産を母親へ相続させると、母親の二次相続の際にかえって子どもたちに高額な相続税がかかってしまうリスクが発生します。二次相続を予定するケースでは、配偶者控除をむやみに適用せず事前にしっかり二次相続時の税額をシミュレーションしましょう。
土地相続時に利用できる制度
土地を相続する際に忘れてはならないのが小規模宅地の特例です。
被相続人の自宅があった土地、事業用の宅地、賃貸に出していた土地などの相続税評価額を下げてもらえます。自宅の場合であれば330平方メートルまでの部分の相続税評価額が80%減となるので非常に節税効果が高いものといえます。
なお、要件は厳しく、被相続人と同居していなければならない、同居していない場合には自分の家がない『家なき子』でなければならないなどの条件を満たさなければなりません。
また、土地面積が広大な場合「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されて、一般的な評価方法より減額される可能性があります。
他にも以下のような土地の場合は、評価が減額されるケースがよくあります。
- 不整形地
- 道路に接していない土地
- 傾斜のある土地、一部が崖になっている土地
- 道路との間に水路が通っている土地
- 墓地に隣接する土地
- 高圧電線が上空に通っている土地
- 騒音や悪臭のある土地
さいごに
効果的に相続税を節税するには、ご家族の状況に応じた対応が必要です。
また税制は頻繁に改正されるので、常に最新情報をもっていなければ効果的な節税対策はできません。素人判断では効果的な節税対策は困難となるでしょう。相続税の節税対策や申告は、ふだんから相続税案件を多数取り扱っている「相続税に詳しい税理士」に相談するのがベストです。
恵比寿の鈴木総合法律事務所では、相続に詳しい税理士とも提携して積極的に相続案件の解決に取り組んでいます。相続税対策に迷われている方もお気軽にご相談ください。