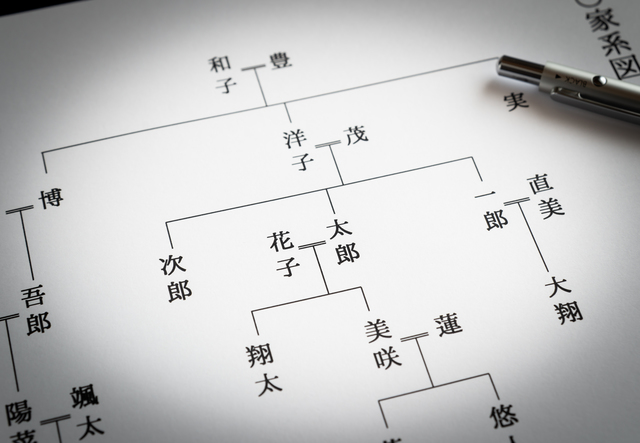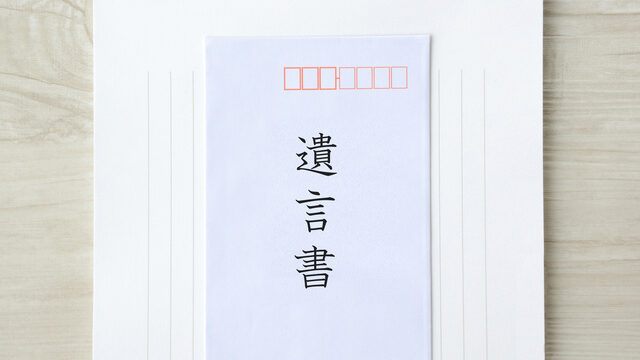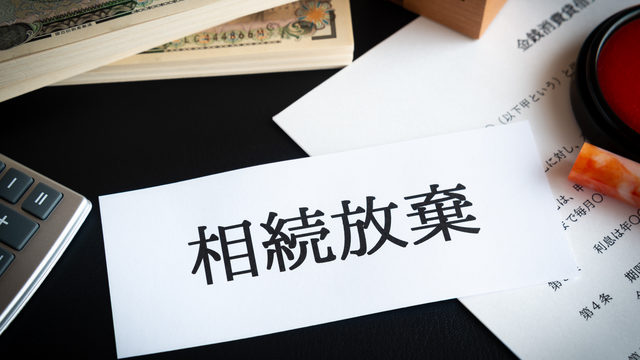人が亡くなった際、誰が相続人となるのかについては、「法定相続人」として法律(民法)で定めれられております。
亡くなられた方(被相続人)の配偶者及び子が第1順位の相続人であり、第1順位の相続人がいない場合等には第2順位の相続人である両親、第3順位の相続人と移っていきます。
これは法律で定められているものであるので、要件を満たす場合は当然に相続人となりますが、法定相続人に該当する方であったとしても所定の欠格要件を満たしてしまうと『相続欠格』となってしまい相続する資格を失ってしまいます。
それではどのような要件を満たしてしまうと相続欠格となってしまうのでしょうか?
今回の記事では、相続欠格となってしまう事由や相続欠格者がいる場合の対処方法について解説いたします。
相続欠格
01.相続欠格とは
相続欠格とは、法定相続人が一定の要件に該当する場合において、当然に相続人の資格を失うことです。相続欠格の要件に該当して相続資格を失った元相続人を「相続欠格者」といいます。
02.効果
相続欠格者になると、相続人ではなくなり、個人の財産を相続する資格を失うことになります。従って、故人(被相続人)の遺産を相続することはできません。
遺産分割協議にも参加できず、遺言による遺贈も受けることはできません。
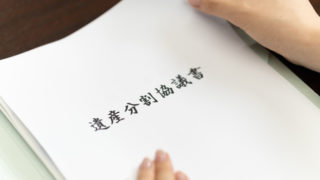
なお、相続欠格者に対しても生前贈与をすることは可能です。死亡保険金を受け取らせることも可能です。「贈与」や「生命保険金の受け取り」は、相続とは関係がないためです。

相続欠格事由
相続欠格事由については、民法891条において以下のように定められています。
(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
01.故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、殺そうとしたりして刑に処せられた
被相続人や先順位、同順位の相続人を殺したり、殺そうとして失敗したりして刑事事件となり「刑罰に処せられた」人は、当然に相続欠格者となります。
なお、「『故意に』殺害した(殺害しようとした)」ことが要件であるため、過失によって死なせてしまった場合には相続欠格とはなりません。
また、被相続人だけではなく、先順位や同順位の相続人を殺害した(殺害しようとした)場合も相続欠格者となります。
02.被相続人が殺害されたことを知って告発告訴しなかった
被相続人が殺害されたと知りながら告発や告訴をしなかった人も相続欠格者となります。告発や告訴が必要なので被害届を出しただけでは足りません。
ただし、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合には告訴や告発をしなくても相続欠格とはなりません。
また、是非弁別能力(良いことと悪いことの区別ができる能力)がない相続人には告訴や告発することを期待できないので相続欠格事由になりません。子どもや障害者のような告訴や告発の意味を理解することが困難で、これを自発的に行うことが期待できない方の場合には告訴や告発をしていない場合でも相続欠格者にはならないと考えられています。
03.被相続人を詐欺、脅迫して遺言書の作成や撤回、取り消しや変更を妨害した
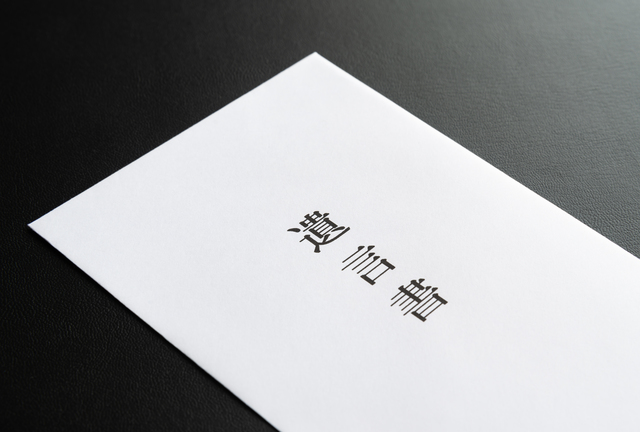
被相続人の生前において、被相続人が遺言書の作成や遺言内容の撤回、取り消し、変更をしようとした際に、だましたり脅迫したり暴力を振るうことで遺言に係る諸行為を妨害した人は相続欠格者となります。
04.詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた
被相続人の生前において、被相続人を騙したり脅迫したり暴力を振るうことで、遺言書を作成させたり、遺言内容の撤回や、取り消し、変更をさせた人も相続欠格者となります。
05.遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した
被相続人が残した遺言書を、「偽造」、「変造」、「破棄」、「隠匿」した場合も相続欠格事由となります。
- 偽造:被相続人の名義で遺言書を勝手に作成すること
- 変造:被相続人が作成した遺言書を勝手に訂正すること
- 破棄:遺言書を破ったり捨てたりすること
- 隠匿:遺言書を隠してしまうこと
06.自己の利益や不利益を避ける目的が必要
上述の相続欠格要件のうち、03~05の事由については、相続人において「自己の利益を得る目的や不利益を避けう目的」が必要と考えられています。
つまり「(相続による)利益を得たい」「(遺言による)不利益を避けたい」という目的がなければ、遺言書を破棄したり隠したり被相続人を脅したりしても相続欠格者になりません。
最高裁において以下のような判決が出ています(平成9年1月28日)。
「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」

相続欠格者には遺留分も認められない
法定相続人には最低限の遺産取得割合である遺留分が認められています。不公平な遺言書によって遺産を全く受け取れなかった場合には、受贈者に対して「遺留分侵害額請求」という金銭請求を行い、侵害された遺留分を取り戻すことができます。

他方で、相続欠格者は「相続人としての資格を失う」ので、相続人に認められている遺留分についても認められません。そのため遺留分が侵害されたとしても侵害請求を行なうことはできません。
相続欠格者と戸籍等
相続欠格者が現れたとしても役所に届け出る必要はありません。また、相続欠格の事実について戸籍に登録されることはありません。
相続欠格と代襲相続
ある相続人が相続欠格者となったとしても、その子どもや孫は代襲相続することが可能です(ただし兄弟姉妹の場合は子どものみ)。相続欠格事由は、行為を行なった本人についてのみ考慮されるべきものだからです。
たとえば、A氏の息子であるXさんが、A氏の遺言書作成を妨害し相続欠格者になったとします。その後A氏が亡くなり相続が開始した際、Xさんは相続欠格を理由に相続人となることはできませんが、Xさんの子供(A氏との関係では孫)は「代襲相続人」としてA氏の相続人となることができます。

相続人廃除について
相続人廃除についても確認しておきましょう。

01.制度の趣旨
相続人廃除とは、被相続人の意思によって非行のある相続人から相続権を奪う制度です。
相続人が被相続人を虐待したり重大な侮辱行為をしたり著しい非行があった場合において、家庭裁判所へ申し立てることでその者を相続人から廃除することが出来ます。
02.廃除方法
相続人廃除は、被相続人が存命中に被相続人自身が家庭裁判所に申立てを行なう方法(生前廃除)と、被相続人の死後、被相続人の遺言に従って遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行なう方法(遺言廃除)の2つがあります。
①被相続人の意思に基づき廃除がなされること、②家庭裁判所への申立を要すること、という点で相続欠格と異なります。
03.戸籍への記載
相続人廃除の場合、排除された相続人の戸籍に、排除された事実が記載されることになります。この点も相続欠格と大きく異なります。
なお、被相続人は、廃除が認められた後であっても相続人廃除の決定の取消請求をすることが可能です。被相続人の死後、遺言によって取消すこともできます。
04.相続人廃除の効果
廃除された相続人は相続権を失うこととなるので、遺産分割協議には参加できず遺留分も認められません。この点は相続欠格と同様です。
05.相続欠格と相続人廃除の違いの一覧表
| 相続欠格 | 相続人廃除 | |
| 被相続人の意思によるかどうか | 被相続人の意思とは無関係 | 被相続人の意思による |
| 原因となる事由 | 被相続人の殺害や遺言書の偽造など法律の定める5つの事情 | 被相続人への虐待、被相続人への重大な侮辱、その他の著しい非行 |
| 手続き | 不要(当然に相続欠格者となる) | 家庭裁判所での手続きが必要 |
| 戸籍 | 記載されない | 記載される(届出が必要) |
| 取消の可否 | できない | できる |
| 遺言で指定できるか | できない | できる |

相続欠格を証明する方法
相続欠格者であることは戸籍には記載されません。従って相続欠格者であるかどうかを公的に証明することは困難なのですが、この点が遺産分割の場面で問題となることがあります。
たとえば遺産分割にもとづいて不動産の相続登記をするときには「相続人全員が参加した遺産分割協議書」が必要となります。他方で相続欠格者は遺産分割協議に参加しません(できません)ので、全員参加の協議書を作成することが出来ません。なぜ相続人全員が署名押印していないのか、相続欠格者を除いた理由を法務局に対し説明できなければ登記申請を受け付けてもらえないこととなります。
こういった場合どのように対応すればよいのでしょうか?
解決策として相続欠格者本人に「相続欠格証明書」を書いてもらう方法があります。「私○○は、被相続人△△(20XX年X年X月死亡)の相続について、民法891条○号の相続欠格者に該当します」という記述、日付、住所含めて署名押印のある書面を用意できれば相続登記を受け付けてもらえるでしょう。
相続欠格者が納得しない場合の対処方法

欠格者本人が被相続人や先順位、同順位の相続人を殺害したり殺害しようとしたりして刑罰を受けている場合には、刑事裁判の判決書をもって相続欠格者であることを疎明することが可能です。
他方で「被相続人を脅して遺言を無理やり書かせた」といった欠格事由は証明することが難しいです。相続欠格者となった本人から「自分が相続欠格者扱いされることについて到底納得できない。自分も遺産分割協議に参加させろ。」と主張されることも少なくありません。
欠格者本人が遺産分割協議に参加させるよう要請してきたときには、他の相続人は共同して欠格者に対し「相続人の地位がないことを確認する訴訟」を提起しなければなりません。あるいは相続欠格者(の疑いのある人)から提起された「相続人としての地位を確認する訴訟」に対し対応する必要があります。
訴訟において(欠格者)本人が相続欠格者である事実を認めてもらうには、その者が相続欠格となった事由を証明しなければなりません。そのためには「被相続人を脅して無理に遺言書を書かせた」「遺言書を破棄したり隠匿したりした」等を客観的に証明する資料(証拠)が必要となります。
立証に失敗した場合、裁判所は相続欠格を認めない判断を下すこととなるので事前に十分な資料を収集しておきましょう。
相続欠格かどうかが争いになって訴訟を行う場合には法律的な主張と立証活動を行わねばなりません。自身で対応することが難しいと考えた場合には弁護士に相談することを推奨いたします。
相続トラブルはお気軽にご相談ください
こと遺産相続の場面においては、相続人の地位を巡ってのトラブルに発展するケースは少なくありません。話し合いで解決できない場合には、訴訟が必要になる可能性もあります。
自分たちだけで取り組むとどのように対応すればよいかわからないケースも多く、トラブルが数年にもわたって続いてしまう可能性もあります。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所は相続手続きにおけるトラブル解決に注力しております。相続に関しお困りごとを抱えている方はお気軽にお問い合わせください。