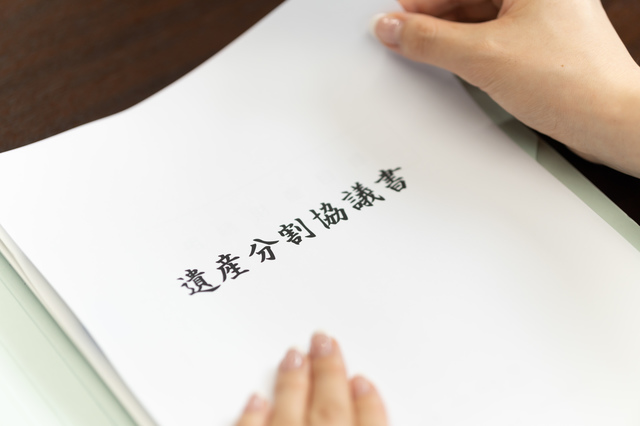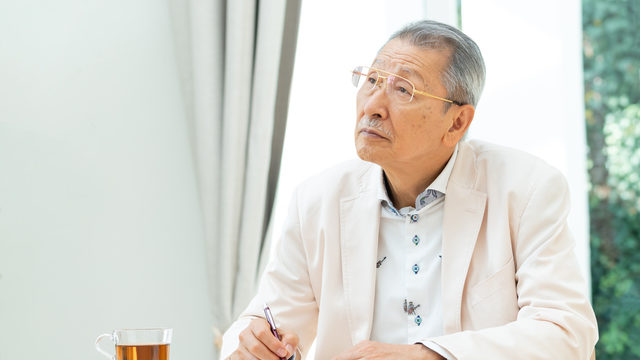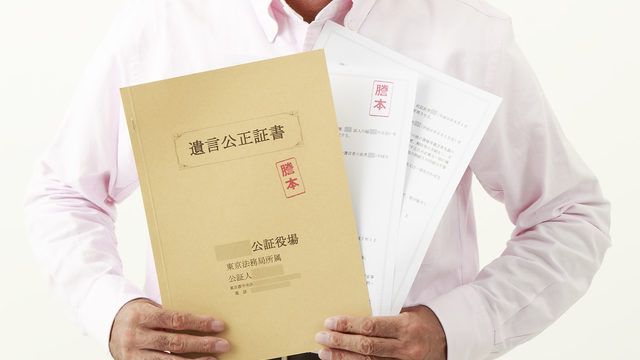人が死亡した場合、死去した方が残した財産について相続が発生します。
遺言がない相続においては、法定相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、相続不動産の相続登記、被相続人の預貯金の解約や名義変更等の場面で必要となる重要書類です。正しい作成方法を押さえておきましょう。
今回の記事では遺産分割協議書の作成方法等について解説します。
遺産分割協議
01.遺産分割協議とは
ある人が亡くなり相続が開始となった際、遺言によって相続方法が指定されていない場合には、法定相続人は相続財産をどのように分け合うのかを話し合う必要があります。
この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
02.遺産分割協議のやり方
遺産分割協議のやり方(開催方法)については、特に決まりはありません。実際に集まって話し合ってもかまいませんし、電話やメール、FAX、手紙などの連絡手段を利用して進めても問題はありません。

遺産分割協議書
遺産分割協議において、相続人全員が遺産の分割方法に合意ができた場合、その合意内容をまとめた書面を作成することとなります。この書面のことを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書が必要な理由
なぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?
01.遺産を正当に承継するために必要
実は、相続の当事者間(相続人間)で遺産分割について合意ができたとしても、それを証明する書面がなければ財産の一部を移転させたり処分することができません。
たとえば相続財産として不動産がある場合、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する(相続登記をする)必要がありますが、ちゃんと遺産分割協議をしたことを証明する書面がなければ相続登記をすることができません。
また、被相続人の銀行口座の凍結解除や名義変更といった場面でも遺産分割協議書が必要となります。被相続人の残した財産について正当に受け継ぐためには、遺産分割協議書は必要不可欠なのです。
02.のちのトラブルの発生を防ぐために必要
相続人間で口頭で合意をしたとしても、後で一部の相続人が「私はそんなことは言っていない」「私はそんな合意はしていない」と言い出してトラブルになる可能性は否めません。
このようなトラブルを防ぐためにも、相続人全員が合意したことを証明する遺産分割協議書を作成しておく必要があるといえるでしょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成する際のポイントを見てみましょう。
01.書式
遺産分割協議書には定まった書式はありませんので、協議の内容が分かるのであれば書式は不問です。
だからといってあまりにフリーダムに記述されてしまうと協議内容が不明瞭となり、のちにトラブルが発生する可能性が高くなってしまいます。
インターネット上や書籍等で遺産分割協議書の草案や見本を確認することができますので、それらを参照して作成するようにしましょう。
02.作成方法
遺産分割協議書は、自筆証書遺言のような「自筆でなければならない」という制限はありませんので、自筆であってもパソコンで印字したものであっても差支えはありません。また、ペンや用紙についても特段の制限はありません。
なお、鉛筆やシャープペンシル等は、後で消すことが容易であるため、使用することはできません。
03.自署・押印
遺産分割協議書の内容に全員が同意したことを約するため、遺産分割協議書には相続人全員の記名押印が必要となります。
記名は『本人の自署』が必要です。
押印に使う印鑑については法律的には認印でも有効とされておりますが、実印の方が高い信用性を得ることができますので実印を使うことを推奨します。
なお、遺産分割協議書が2ページ以上にわたる場合にはページとページの間に契印をします。
04.保存
遺産分割協議書は、相続人全員分の部数を作成します。もちろん全部について全員の記名押印が必要です。記名押印のなされた遺産分割協議書を相続人各人が1通ずつ所持します。

遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書の一例をあげてみます。
01.タイトル
タイトルは、遺産分割協議書とします。
02.項目別の記述
遺産について誰がどの遺産を相続するのかを記入していきます。この際「相続人」と「対象となる相続財産」を明確に特定しましょう。あいまいだと外部に遺産分割協議書を提示しての手続きの場面で受け付けてもらえないことがあります。
03.相続人について
相続人については、「妻・●●●●」「長男・〇〇〇○」というように、『相続人の姓名』と『被相続人との続柄』を書いて特定します。
04.預貯金
対象となる相続財産が預貯金の場合には、以下の事項を記載することで口座を特定します。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座番号
- 名義人
05.不動産
対象となる相続財産が不動産の場合には、下記の事項を記載することで不動産を特定します。
土地の場合
- 所在
- 地目
- 地番
- 地積
建物の場合
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
これらの情報については、対象不動産の全部事項証明書から引用します。
不動産が多数ある場合には、遺産分割協議書の本文と分けて物件目録を作成してもよいでしょう。
さいごに
遺産分割協議は、高額の財産を相続人で分けることとなるのがほとんどです。財産(金銭)が絡む問題であることもあって、相続人で意見が対立しトラブルになってしまう例が多々あります。
相続手続きに不安がある場合には、相続が「争続」になってしまう前に専門家である弁護士に相談してみましょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、相続トラブルにおいて多数の解決実績を有しております。遺産分割協議でトラブルが発生してしまいお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度ご相談下さい。