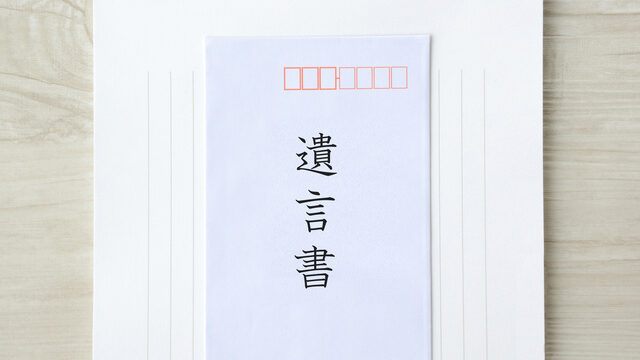被相続人が残した遺産が実は誰かに使い込まれていた・・・。このような事態が判明した場合、相続人はどのような対処をすればよいのでしょうか?
実は使い込まれてしまった遺産は取り戻せる可能性があります。なお、その対処方法は、使い込んだ相手や使い込まれた時期によって異なるので注意が必要です。
今回の記事では、遺産が使い込まれていた場合の対処方法についてパターン別に解説いたします。
遺産の使い込みのパターン(主体別)
遺産の使い込みは、誰が使い込んだか(使い込んだ主体はだれか)によって以下の2パターンに分類することができます。
01.相続人による使い込み
相続人が使い込むパターンです。特に多いのは被相続人と同居していた相続人によるものです。
たとえば、両親と長男が同居し、二男は別居している場合において、長男が親名義の現金・預貯金を使い込んだり、保険を解約することで返戻される解約返戻金を費消してしまったりするケースが典型です。
02.相続人以外のものによる使い込み
相続人以外の人が使い込むパターンです。被相続人のそばで作業を行なっていた人によるものが多いです。
たとえば、被相続人が介護サービスを利用していた場合に、介護者が管理を任されていたお金を使い込んでしまうケースが典型です。

遺産の使い込みのパターン(時期別)
遺産の使い込みは、いつ使い込まれたかによっても分類できます。
01.相続開始前の使い込み
相続開始前、すなわち被相続人の生前に使い込まれるパターンです。
02.相続開始後の使い込み
相続開始後、すなわち被相続人の死後に使い込まれるパターンです。
遺産の使い込みのパターン(財産別)
遺産の使い込みは、何を使い込んだか(使い込んだ財産は何か)によって以下のようなパターンに分類することができます。
01.現金・預貯金
被相続人が自宅で管理していた現金を同居者が着服したり、被相続人名義の預貯金(口座残高)を勝手に出金したり自身の口座に送金したりして費消するパターンです。
02.不動産の無断処分
被相続人名義の不動産を、同居の相続人が被相続人の実印を持ち出して署名捺印し、無断で売却処分等をしてしまうパターンです。
03.収益物件の賃料の横領
被相続人が収益物件を所有している場合に、賃料管理を任されている者が賃料を自分の口座へ入れて使い込んでしまうパターンもよくあります。
04.株式の売却・着服
被相続人名義の株式を勝手に売却し、売却益を自分の口座へ送金するなどして着服するパターンです。
近年ではネット上での証券売買が主流になっていることもあり、ログインパスワードなどを知っている人であれば容易に証券口座にログインして株式の売却や送金処理を行なうことが可能となっています。
05.保険の解約
被相続人が契約している保険を無断で解約し、解約返戻金を着服するパターンです。

請求方法(相続開始前の使い込み)
ここからは使い込まれた遺産の請求方法についてみていきましょう。
まず、相続開始前(被相続人の死亡前)に遺産が使い込まれていた場合の対処方法を確認しましょう。
相続開始前に遺産が使い込まれたケースでは、以下の2つの方法で使い込まれた遺産を請求します。
- 不当利得返還請求
- 不法行為に基づく損害賠償請求
法律上は、「被相続人が有する」「使い込みをした者に対する不当利得返還請求権及び損害賠償請求権」を、「相続人が相続しこれを行使する」という構成になります。
01.不当利得返還請求
不当利得返還請求とは、法律上の原因なしに相手が利益を得てこちらが損失を被ったときに相手に利得の返還を求めることをいいます。
遺産を使い込んだ者は、遺産を使い込む権利がない(法律上の原因がない)にも関わらずこれを使い込むことで利益を得ておりますので、当然に不当利得返還請求を行なうことができます。
02.善意・悪意による違い
民法上は、不当利得返還請求によって請求できる金額は基本的に現存利益に限定されており、現在利益が残っていない場合は返還してもらうことができないとされています。
どういうことかというと、たとえばある人が権利もないのに口座から100万円を出金し、うち60万円を費消してしまった場合は、残っている40万円しか請求出来ないということです。
なお、相手が悪意である場合には現存利益に限定されず不当利得全額が返還の対象となります。さらに利息(遅延損害金)を付することもできます。上記の例でいえば手元に40万円しか残っていないとしても100万円全額を返還請求することができるということです。
ここでいう悪意とは「自分が無権利者であること」を知っていたこと(認識していたこと)をいいます。遺産の使い込みの場面では、ほとんどのケースにおいて使い込みをした人は「自分が無権利」と認識しているでしょうから、使い込まれた額の全額の返還及びこれに対する遅延利息を請求することができます。
03.不法行為に基づく損害賠償請求とは
不法行為にもとづく損害賠償請求とは、相手が故意過失にもとづく違法行為をしてこちらに損害が発生したときにその損害賠償を求めることをいいます。
遺産の使い込みは明らかに違法行為であり、通常は故意によって行われていることから不法行為に基づく損害賠償請求を行使することができます。
04.請求できる範囲
使い込みが被相続人の生前になされた場合には、被相続人が有する不当利得返還請求権及び不法行為に基づく損害賠償請求権を相続しこれを行使することとなります。
そのため、相続人が単独で使い込まれた遺産の全額を請求できるものではありません。相続した請求権を行使しているので、請求することができるのは『使い込まれた遺産額のうち、自分の法定相続分に相当する額』に限定されてしまうのです。
たとえば子ども3人が相続人のケースにおいて、長男が相続開始前に遺産を300万円分使い込んだケースを想定します。このケースで二男が長男に対し請求できるのは100万円ですし、三男が長男に対し請求できるのも100万円です。二男単独で全額を請求することはできません。

請求方法(相続開始後の使い込み)
相続開始後に遺産が使い込まれたケースでは、遺産分割協議や遺産分割調停といった遺産分割の過程で使い込まれた遺産について処理することも可能です。
昨今の民法改正により、共同相続人が全員合意すれば遺産分割前に処分された財産についても遺産に含めて遺産分割の対象にできるとされました(民法906条の2)。他の共同相続人が「使い込まれた遺産も含めて遺産分割する」と納得すれば遺産分割協議や調停で使い込み問題を解決できます(使い込んだ相続の同意は不要)。
相続開始後の使い込みの場合、遺産分割協議で使い込み問題を話し合うのが得策といえるでしょう。

遺産が使い込まれた際に対応すべきこと

遺産の使い込みが発覚した際は、以下のように対応を進めましょう。
01.証拠集め
まずは証拠を集めます。証拠がなければ相手が使い込みを認める可能性は低いです。また、裁判になる可能性もあるので使い込みを証明できる証拠は必須と言えるでしょう。
相手が使い込んだ証拠としては以下のようなものが必要です。
- 被相続人名義の預貯金取引履歴(預貯金が使い込まれたケース)
- 証券口座の取引履歴(株式を売却処分されたケース)
- 賃貸借契約関係書類(賃料を横領されたケース)
- 不動産の全部事項証明書(不動産を売却処分されたケース)
- 保険会社からの通知書、解約請求書などの書類(保険を無断で解約されたケース)
- 使い込んだ本人の預金口座取引履歴等
被相続人名義の口座の取引履歴や保険に関する書類等は、相続人であれば照会できるケースがほとんどです。また、不動産の全部事項証明書は法務局に申請すれば誰でも取得できます。そのため、これらの書類についてはそこまで手間なく収集はできるでしょう。
他方で使い込んだ本人の預金口座取引履歴等は、本人が自発的に提出しない限りは取得が困難です。個人情報保護法の関係もあって、個人が他人の取引履歴の取得はすることはでき、ません。
なお、このような場合であっても弁護士であれば取引履歴を取得できる可能性がありますし、調停や訴訟を申し立てた際には裁判所から照会してもらえる可能性もあります。証拠集めに限界を感じた際は弁護士に相談してみましょう。
また、遺産の使い込みを主張した際、相手(使い込み者)から、「被相続人が自分で使った」「自分で解約した」などと反論される可能性があります。このようなケースでは「被相続人は意思能力や体力が低下していたので、自身で自発的に使ったとは考えられない」という事実を立証できる証拠を集めておく必要があります。
本件については以下のような証拠が有効です。
- 病院のカルテや診断書などの記録
- 看護日誌
- 介護事業所に残された介護に関する記録
- 介護日誌
- 要介護認定を受けたときの記録、診断書などの添付書類
入通院していた病院や利用していた介護事業所や役所などに開示を依頼し、できるだけたくさんの証拠を集めまておきましょう。
02.話し合い
十分な証拠が揃ったら、相手と話し合いを行ない、使い込み分の返還を求めましょう。相手が使い込みを認めた場合は返還方法について取り決めます。使い込み者が相続人である場合には遺産分割協議の中で話し合うことも可能です。
03.合意書、遺産分割協議書を作成
使い込んだ遺産の返還金額や返還方法が決まっても、口約束だけでは守られない可能性があります。あとで約束した・約束してないの水掛け論になることもあります。
これらのリスクを回避するために、合意内容については必ず書面化しておきましょう。遺産分割の協議の中で処理した場合は、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
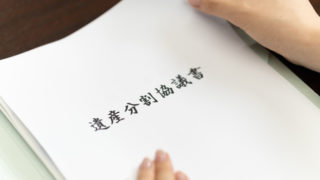
04.調停による解決
話し合いで解決できない場合、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割調停では、使い込み問題と遺産の分け方の両方を話し合って決めることができます。調停委員が間に入ってくれるので、自分たちだけではもめてしまうケースでも解決しやすいのがメリットです。
ただし、調停では結論を強制できないので、双方が納得しなければ不成立になります。
05.遺産分割審判
調停が不成立になった場合、手続きは審判へ移行します。
審判になれば、審判官が使い込み問題の解決方法も含めて遺産分割方法を決定してくれます。相手が納得しなくても使い込みの証拠があれば、使い込まれた遺産の返還を受けられるでしょう。
ただし、証拠が不十分である場合は使い込みが認められなかったり、全額の返還を受けられません。有利な審判を出してもらうためにも事前の証拠集めが非常に重要です。

06.訴訟
相続発生前に遺産が使い込まれた場合は、遺産分割調停等では使い込み問題を解決できないことがあります。また、相続人ではない者に使い込みをされた場合はそもそも遺産分割協議で解決することができません。
このような場合は訴訟を起こして解決することになります。不当利得返還請求訴訟または不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起しましょう。なお、1つの裁判で両方の請求原因を立てることも可能です。
証拠によって使い込みを立証できれば、裁判官が相手に使い込んだ遺産の返還命令(金銭支払い命令)を出してくれます。
なお、訴訟は非常に難しい手続きです。自力で対応すると思わぬ不利益を被ることもあるので弁護士に依頼されることを推奨します。
07.訴訟だけでは完全解決にはならないことも
「相続人に該当する者」による「相続開始前の使い込み」については、訴訟によって返還命令が出るのは「使い込まれた遺産に関する法定相続分」に限られます。遺産全体の分割方法については別途相手と協議しなければなりません。
なお、遺産分割協議や調停は訴訟と並行して行ってもかまいませんし、訴訟の終了後にあらためて遺産分割協議や調停を行うことも可能です。
時効について

使い込まれた遺産を取り戻す際、時効に注意する必要があります。

01.不当利得返還請求権の時効
不当利得返還請求権の時効は、以下のいずれか早い方の時点で成立します。
- 権利行使できると知ったときから5年
- 権利行使できるときから10年
使い込みを知ったときから5年、または使い込まれたときから10年が経過した時点で請求できなくなってしまいますので注意が必要です。
02.不法行為に基づく損害賠償請求権の時効
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は以下のとおりです。
- 加害者と損害発生を知ってから3年
- 不法行為時から20年
遺産の使い込みを知ってから3年、あるいは遺産使い込み時から20年が経過したときに時効が成立します。
以上のように、不当利得返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求では時効成立までの期間が異なります。遺産の使い込み時期が古く、長期に渡って使い込みに気づかなかった場合には不法行為に基づく損害賠償請求の方が有利といえます。
なお、相手に債務を承認させたり訴訟を起こしたりすると時効の完成を阻止することができます(時効の更新、完成猶予)。時効が近い場合は、時効の更新を達成できるように動かなければなりません。
03.遺産分割協議
遺産分割協議には時効はありません。そのため、「相続開始後」に「相続人」に遺産を使い込まれた場合であればさほど時効を心配する必要はないといえます。
とはいえ遺産分割の時期が遅れれば時効以外にもさまざまなリスクが発生しますので、放置することなくできるだけ早めに対応されることをお勧めします。
さいごに
遺産が使い込まれた場合はまず証拠を集めなければなりませんが、証拠集めには手間も時間もかかります。また、証拠を集めて相手と話し合おうとしても使い込みを否定されるケースがほとんどです。
遺産の使い込みのような相続トラブルを確実にかつスピーディに解決するには弁護士によるサポートが必要です。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、遺産相続トラブルの解決に注力しており、その高い解決実績を有しております。遺産の使い込みトラブルでお困りの方がおられましたら是非一度ご相談ください。