売掛金や貸付金といった金銭に係る債権のお持ちの方は、債権の時効についても気を配っておく必要があります。
時効とは、ある出来事から一定の期間継続した事実状態を尊重し、今の状態が法律的に正当でないとしてもこれを正当な法律状態と認めることをいいます。
お金を支払ってもらうという債権をお持ちの場合に債権を一定期間請求していないと、債権そのものが時効消滅してしまうこととなります。
この時効制度ですが、昨今の民法改正によりその内容が大きく変更されました。
今回の記事では、民法の改正により時効制度、特に消滅時効の制度がどのように変わったのかについて解説します。
時効
時効とは『ある出来事から一定の期間が経過した事実状態を尊重し、今の状態が法律的に正当でないとしてもこれを正当な法律関係と認めること』を言います。簡潔に言い換えれば『一定期間継続した事実があればその状態を正しいものとして認めましょう』ということです。
時効には、取得時効と消滅時効の2種類があります。
01.取得時効
取得時効は、一定の期間以上モノを持っている(占有している)と、そのモノの所有権を得ることができる制度です。
たとえば他人の所有するマンションを自分のマンションだと疑わずに所有していた場合、時効期間の経過でマンションの所有権を時効取得することができます。法律的には他人のマンションですが、長年継続した事実関係を根拠として所有権を時効取得することになるのです(取得時効の成立にはほかにも要件がありますが、本記事では割愛します)。
02.消滅時効
消滅時効とは、一定の期間請求をしなかった場合に、その請求権が消滅してしまう制度です。
たとえば他人にお金を貸してこれを返してもらう権利を有していたとしても、時効期間の経過をもってその権利が消滅し、他人にお金を請求することができなくなってしまいます。正確には請求すること自体はできますが、他人から「時効の援用(消滅時効が成立してますという主張)」をされてしまうため、請求しても払ってもらうことができなくなります。
正当な権利に基づいて他人にお金を払ってもらうことが出来る債権を「金銭債権」と言いますが、日常生活の中で他人に対して金銭債権を取得する場面は多々あります。
- 知人にお金を貸した → お金を返してもらう権利
- ある会社で労働した → 賃金(給料)を支払ってもらう権利
- 取引先にモノを卸した → 売掛代金を支払ってもらう権利
これらの金銭債権を有していたとしても、支払を受けることもなく請求もせずにいた場合は、時効(消滅時効)が成立してしまいます。時効が成立してしまうとその債権の回収が困難となってしまいますので未回収の債権の回収には早めに着手する必要があります。
について-320x180.jpg)
除斥期間
時効と似ている制度として、除斥期間があります。
除斥期間とは、一定期間が経過すると当然に権利が消滅してしまう制度です。時効と異なり債務者による援用は不要です。
また、時効では、時効の更新や時効の完成猶予の制度により、時効の進行を止めたり巻き戻しを図ることが可能ですが、除斥期間については進行を止めるようなことはできません。ある事実から一定期間経過で当然に消滅することとなります。
債権の種類によっては、時効と除斥期間の両方が適用されるケースもあります。このような場合、時効期間だけでなく除斥期間もしっかりと検討して債権回収に臨む必要があるので注意しましょう。

民法改正による時効制度の変更

2020年4月1日に施行された改正民法により、債権の時効についての法的ルールが大きく変更され、2020年4月1日以降に発生する債権については新しい民法による時効制度が適用されることとなります。
以下、旧民法と新民法を比較しながら、時効制度の変更点について確認しましょう。
旧民法における消滅時効
まずは旧民法における時効制度を確認しましょう。旧民法下では、債権の原則的な時効期間は10年間とされていました。これを民事時効といいます。
また、債権の種類によっては以下のような異なる時効期間が適用されていました。
- 飲食店や宿泊施設、大工や左官工などの債権…1年
- 弁護士や生産者、卸売商人や小売商人などの債権…2年
- 医師や薬剤師、助産婦、工事の設計者や施工業者などの債権…3年
- 商取引によって発生した債権(商事債権)…5年
上記のものは、時効期間が10年よりも短いことから「短期消滅時効」と呼ばれておりました。
また、給与や残業代などの賃金請求権については労働基準法において時効期間が2年と定められていました。
改正民法における消滅時効
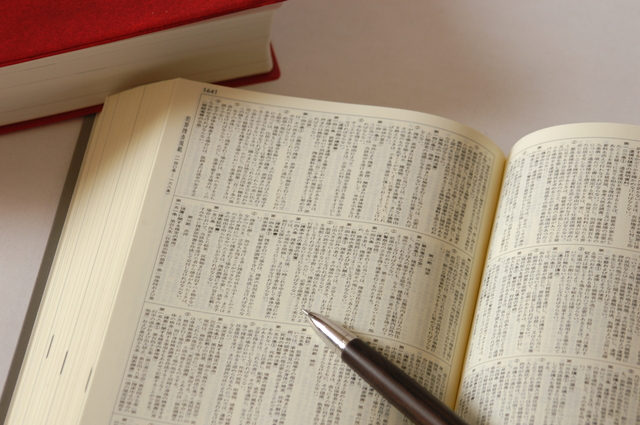
2020年4月1日から施行された改正民法での消滅時効について確認してみましょう。
01.短期消滅時効の廃止
改正民法では短期消滅時効が廃止され、以下の期間を経過することで消滅時効が成立することとなりました。
- 債権者が請求できることを知ってから5年(主観的起算点)
- 債権者が請求できる状態になってから10年(客観的起算点)
主観的起算点から5年、または、客観的起算点から10年のどちらかが成立した時点で債権が消滅することとなります。
02.主観的起算点
消滅時効は、『債権の種類を問わず、』『債権者が』『(債務者に対し)債権を請求できると知ったときから5年』で時効が成立します。
ここでいう『債務者に請求できると知ったとき(権利を行使することができると知ったとき)』のことを主観的起算点といいます。
03.客観的起算点
場合によっては債権者が債権を請求できる時期が到来した事実に気づかない(知らない)こともあります。このようなケースでは『債権を請求できる時期が到来してから10年』で時効が成立します。この『請求できる時期』のことをを客観的起算点といいます。
04.賃金債権
2020年4月に労働基準法が改正され、賃金債権の消滅時効は「当面の間は3年」とされました。
これまで2年だった時効期間をいきなり5年に延長してしまうと、企業が多額の残業代を返還しなければならなくなり経済的な影響が大きすぎると考えられたことから、企業側にかかる負担を考慮して経過措置を設けたものとなります。
これはあくまで経過措置であり、近い将来においては民法と同様に時効期間が5年に延長される見込みです。

改正法の適用時期
すべての債権に改正民法が適用されるわけではありません。改正民法が施行された2020年4月を挟んで適用が異なります。
具体的には、2020年4月以降に生じた債権については改正民法が適用され、2020年3月以前に発生した債権については旧民法が適用されます。
たとえば、病院で未払いの診療報酬であれば、2020年3月までに生じたものについては、発生時から3年以内に回収しなければなりません。
未回収の債権がある場合にはいつの時点で発生した債権なのか検討し、正しく時効期間を計算する必要があります。
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効
今回の民法改正により不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効についても変更がありました。
不法行為にもとづく損害賠償請求権とは相手の故意または過失による違法行為によって発生した損害についての賠償請求権です。
たとえば交通事故に遭った場合や不倫された場合の慰謝料が典型ですが、商取引において相手が非常に悪質な犯罪行為などを行った場合にも不法行為にもとづいて賠償金請求できる可能性があります。
01.旧民法での時効
旧法では、不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は以下のように規定されていました。
- 損害及び加害者を知ったときから3年(時効)
- 損害発生時から20年(除斥期間)
02.改正民法での時効
改正民放では、不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は以下のように改正されました。
一般の不法行為
- 損害及び加害者を知ってから3年(時効)
- 損害発生時から20年(時効)
生命または身体に対する不法行為
- 損害及び加害者を知ってから5年(時効)
- 損害発生時から20年(時効)
旧法では「損害発生時から20年」の期間制限は除斥期間とされていましたが、改正民法下では時効に変わりました。これにより損害発生時から20年以内に完成猶予や更新の手段をとれば時効の成立を防ぐことができようになります。
また、生命または身体に向けられた不法行為の場合、主観的起算点による時効期間が5年に延長されます。たとえば殴られて怪我をした場合、人身事故の被害に遭った場合などには、相手方と損害発生を知ってから5年間、賠償金を請求できるということです。
時効を止めて債権回収する方法
時効の進行を止める方法などについて確認していきましょう。時効の成立を止める方法としては、完成猶予と更新の2種類があります。
時効の完成猶予
完成猶予とは、時効の成立を一定期間先延ばしにすることです。猶予されている間は時効が成立しません。あくまで先延ばしにする(延長する)効力しかなく、時効期間を巻き戻す効力まではありません。
なお、旧民法では時効の停止と呼称されておりました。
時効を完成猶予させる方法には以下のようなものがあります。
01.基本的な方法
- 債務者へ請求(内容証明郵便を推奨)
- 仮差押や仮処分
上記のアクションをとると時効期間は6ヶ月間延長されます。延長となっている間に訴訟や調停などを起こしより確実に時効を止める必要があります。

なお、債務者への請求によって時効の完成猶予をさせたい場合には、証拠を残すために必ず内容証明郵便を使いましょう。口頭や普通郵便で請求しても、相手から「請求されていない」と否定する可能性があるからです。請求した証拠がない場合は、「時効が成立した」とみなされてしまうリスクがあります。内容証明郵便を使えば手元に控えが残りますし、請求した日時や相手に送達された日時も証明できるので(配達証明をつけた場合)、このようなリスクは生じません。
また、勘違いしやすいのですが、内容証明郵便で時効を先延ばしにした場合、再度内容証明郵便を送っても時効を先延ばしにすることはできません。完成猶予できるのは1回だけなのでご注意ください。

02.債務者との協議
債権者と債務者が『書面で』権利について協議を行うことを合意した場合には、合意時から1年間は時効が完成猶予されます。相手と話し合えるようであればこういった対応も検討しましょう。
03.訴訟提起や差押の申立
以下のような場合にも時効が完成猶予されます。また、裁判手続きが進行し確定すれば時効が更新されることとなります。
- 訴訟や調停などの裁判手続きを申し立てた
- 差押などの強制執行手続きを申し立てた
裁判手続きを途中で取り下げてしまった場合は、時効の更新が成立することはありません。
時効の更新
時効の更新とは、時効期間を当初に巻き戻してあらためて数え直しをすることです。更新された場合はその時点から再度5年の期間が経過しないと時効が成立しません。時効期間のリセットと考えていただいて結構です。

時効を更新させるには以下の方法があります。
01.債務承認による更新
債務者本人が債務を認めた場合は、時効は更新されます。
なお、相手が口頭で債務を認めても、後に「そんなことは言っていない」などと言い出すおそれがあります。債務承認をさせるのであれば必ず書面を作成しておきましょう。「債務承認書」「債務弁済に関する誓約書」といったものを作成して署名押印してもらいましょう。
また、相手が債務について一部でも支払った場合は、「支払います」などと言わなくても債務承認したことになります。もし支払いを受けたのであれば、後々に備えて支払いを受けた証拠を残しておきましょう。
02.確定判決による更新
訴訟の判決や支払督促の仮執行宣言が出たとき、強制執行を終えたときなどにも時効が更新されます。
相手が債務の存在を認めない場合には、訴訟を起こして時効を更新させる方法が有効です。
長期間支払われていない債権がある場合には、早めに弁護士に依頼して訴訟を起こしましょう。
03.更新後の時効
時効が更新された場合、その後はどのくらいの期間を経過すれば時効が成立するのでしょうか?これについては債務承認か確定判決による時効の完成かによって異なります。
債務承認による更新の場合
債務承認によって時効を更新した場合には、基本的に更新後の時効期間は5年です(ただし主観的起算点の場合)。
確定判決による時効の完成の場合
支払命令の判決が出て確定した場合には、更新後の時効期間は10年になります。
裁判を繰り返していれば半永久的に時効を成立させないことも可能です。すぐには債権回収できない場合でもあきらめる必要はありません。
債権回収は弁護士へお任せください
未回収の債権がある場合は、時効の完成前に回収する必要があります。
近年の民法改正により時効に関するルールが大きく変更されたので、時効の完成を止めるには専門知識が必要です。相手に債務承認させるであっても訴訟を起こすであっても弁護士によるサポートが必須となるでしょう。
東京・恵比寿にある鈴木総合法律事務所では、事業者さまへの法的支援や法律顧問業務に力を入れて取り組んでいます。未回収債権を低コストで効率よく回収されたい方がおられましたら、法人様でも個人様でもお気軽にご相談ください。






















