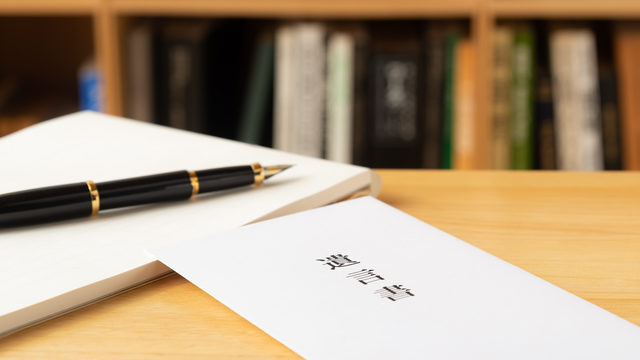遺産相続の場面において、相続人の中に未成年の子どもが含まれているケースは珍しくありません。
相続人の中に未成年者がいる場合、有効な遺産分割を行なうために「特別代理人」を選任しなくてはならないケースがあります。
今回の記事では未成年者が相続人となったときに起こる諸問題と特別代理人について解説します。
行為能力とは
大人(成人)には一人で法律行為を行なう能力が認められています。この能力のことを法律用語で「行為能力」といいます。
遺産分割協議を行なううえでも行為能力は必要です。相続人全員が行為能力を有していれば、各々が単独で法律行為である遺産分割協議を進めることが可能です。
制限行為能力者とは
民法においては、下記の人を「制限行為能力者」として扱っております。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
上記の類型の人が行なった行為については、法定代理人等によって事後的に取り消すことが可能とされ、有効な行為を行なうには法定代理人の同意が必要とされています。

遺産分割において未成年者がいる場合の問題点
未成年の子ども(以下「未成年者」という)は制限行為能力者であるため、単独では遺産分割協議を有効に進めることはできません。
このような場合、未成年者の親(親権者)が未成年者の代理人として遺産分割協議を進めるのでしょうか?
答えは「No.」です。
相続では、有限の遺産を複数の相続人で分けることとなります。ある人の相続分が増えれば他の人の取り分は減ることとなるため、各々の相続人の利益は相反します。このような双方の利益が相反している関係を「利益相反関係(利害対立関係)」といいますが、これは親子の関係であっても成立します。
親権者は、親権者個人としても未成年者の法定代理人としても遺産分割協議に参加することとなり、双方は利益相反関係に立ってしまうのです。
例を挙げて検討してみましょう。
- A氏(父)が不慮の事故で死亡
- A氏の相続人は、妻であるBさんと未成年の子Cくん、Dちゃんの3名
BさんはA氏の配偶者であることから当然にA氏の相続人です。この状況でBさんが親権者としてCくんの代理人になると、Bさんは自身の相続人としての立場とCくんの代理としての立場の双方で遺産分割協議に臨むことになります。このような場合に、Bさんが私利私欲のためにBさん自身の取得分を増やしCくんの権利を害するようなことがあるかもしれません。Cくんを優先して分配しDちゃんが一切の分配を受けられないことがあるかもしれません。
このような事態を避けるため、未成年者とその親権者が利益相反の関係に立ってしまう相続のケースにおいて親権者は未成年者の代理をつとめることができません。親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議書に署名押印をしても当然に無効です。また、このことは各機関も理解しており、このような遺産分割協議書を法務局に持っていっても登記の受付をしてもらえませんし銀行でも預貯金の払い戻しなどに応じてもらえません。

特別代理人
未成年者とその親権者が相続人になっている場合において、有効な遺産分割協議を行なう(有効な遺産分割協議書を作成する)にはどのようにすればよいのでしょうか?
このようなケースでは、未成年者の「特別代理人」を選任して対応します。
特別代理人とは、未成年者が法律行為を有効に行うために特別に選任する代理人です。選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議書に署名押印することで、有効な遺産分割協議書を作成することが出来るのです。
なお、未成年の子どもが複数いる場合、子ども同士も利益相反関係に立つこととなるため、それぞれの子どもについて個別の特別代理人が必要となります。
特別代理人の選任方法

特別代理人の選任申立をする際は、まず「特別代理人選任申立書」を作成します。
誰を特別代理人候補者とするかを申立前に決め、候補者の了承を得ておきましょう。
準備が整ったら未成年者の住所地を管轄する裁判所で申立てをします。申立には以下の書類が必要となります。
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人の候補者の住民票か戸籍附票
- 遺産分割協議書案
なお、費用として、収入印紙800円、連絡用の郵便切手が必要です。
特別代理人選任時の注意点
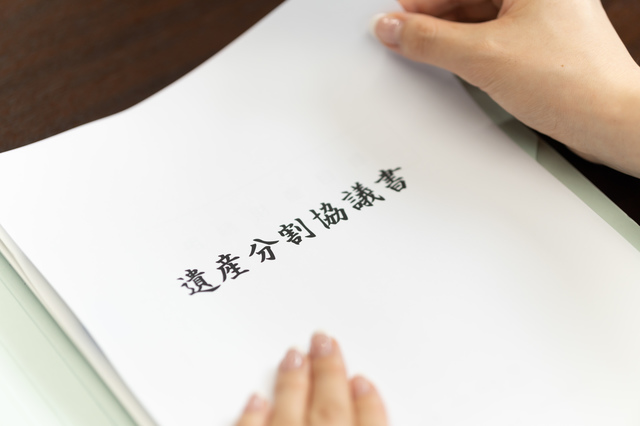
01.遺産分割協議案の提出はなぜ必要?
上記のとおり、特別代理人の選任申立てをする際にはは遺産分割協議案を添付する必要があります。
これはなぜでしょうか?特別代理人選任後にはじめて遺産分割協議を行なうという流れではダメなのでしょうか?
本件の制度の趣旨からすると「遺産分割協議によって未成年者が害されることがない」ようにする必要がありますが、特別代理人を選任してから自由に遺産分割協議を行うとした場合、この点を達成できない可能性があります。そのため、「遺産分割協議によって未成年者が害されることがない」ことを選任段階から裁判所に確認してもらうために事前に協議書案の提出が要件付けられているのです。
02.好ましい配分割合
遺産分割協議書案においては、未成年者は法定相続分に従った遺産配分にしておくのが好ましいです。これであれば各相続人に公平なので裁判所から問題視されることはありません。
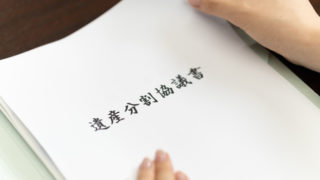
なお、事案によっては親権者に多くを相続させた方が良いケースもあります。たとえば主たる相続財産が不動産だけであれば未成年者の親が全部を相続した方が良いでしょう。また、生活費や教育費などの支払に充当するため、親権者が被相続人の預貯金の大部分を相続するのが好ましいということもあるでしょう。
このような場合は、法定相続分に従っていない配分であっても遺産分割協議書案が認められる可能性が高いです。もちろん相応の説明が必要となります。対応に不安があるようであれば弁護士に相談してみましょう。

相続放棄する場合
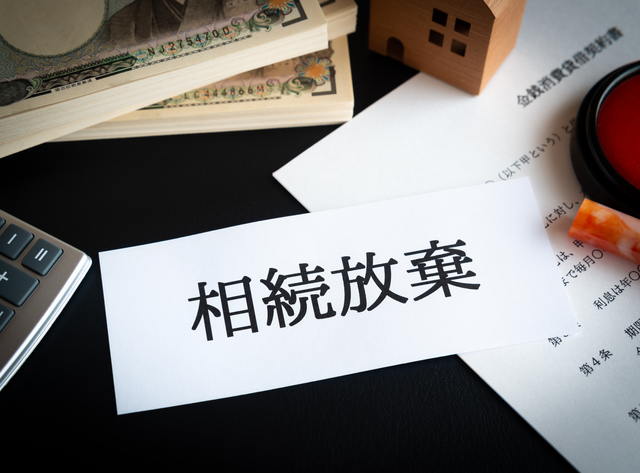
未成年者が相続人となるケースにおいて、相続放棄についても注意が必要です。
相続放棄も法律行為であるため、未成年者は単独で相続放棄できません。相続放棄するのであれば親権者が未成年者の法定代理人として行うことになります。
この相続放棄も未成年者とその親権者との利益が相反してしまう可能性があります。特に問題になるのは親権者が相続放棄しない場合です。
未成年者には相続放棄させて親権者が単独で相続するとなれば、本来であれば未成年者の取得分となる部分を明らかに害します。
そのため、親は相続放棄をせずに子どもだけに相続放棄させる場合にも特別代理人の選任が必要となります。
また、複数の未成年者が相続人になっている場合において、一部の未成年者にのみ相続放棄をさせる場合も未成年者同士の利益が相反することとなるので特別代理人の選任が必要です。
他方で未成年者も親権者も全員が相続放棄する場合には、利益は相反しないので特別代理人の選任は不要です。親権者は単独で自身と相続放棄ができますし、未成年者の法定代理人としての相続放棄もできます。
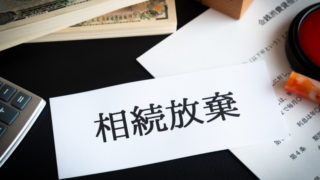
さいごに
未成年の子どもが相続人となっているケースでは、一般の相続の場面とは異なる対応が必要となることが多々あります。対応を誤ってしまうと不利益を被ることもあり得るので注意しましょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、相続問題に注力しております。未成年者がいる状況での遺産分割協議の進め方に不安を抱えていらっしゃる方、特別代理人の選任申立について疑問がある方は、是非一度ご相談ください。