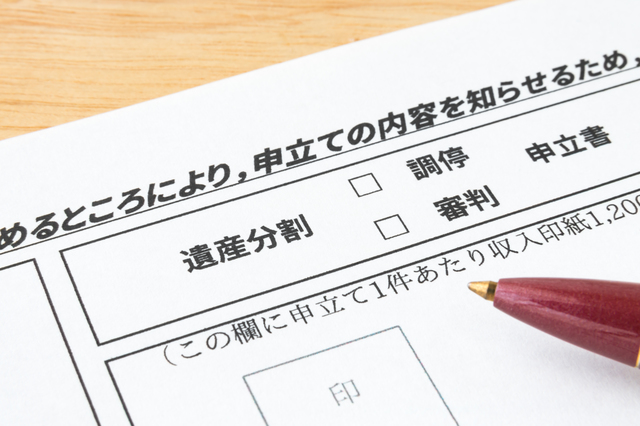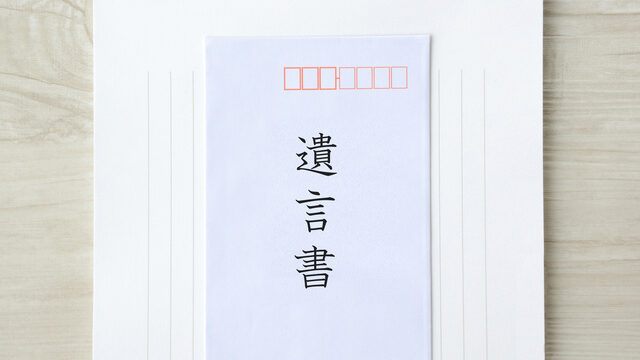相続人が被相続人の遺した遺産をどのように分けるのかについて話し合うことを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議は必ずしもスムーズに進むものとは限りません。
- 相続財産について不満がある
- 寄与分の主張に納得ができない
- 生前贈与が考慮されていない
- 不動産の相続方法で揉める
相続人らにおいて主張が対立してしまうと話し合いでは遺産分割の取り決めができないことも往々にしてあります。
遺産分割協議では解決できない場合には遺産分割調停を利用して遺産分割手続きを進めていきましょう。
今回の記事では遺産分割調停の進め方やポイントについて解説します。
遺産分割調停
01.遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、相続人が全員参加して、家庭裁判所において遺産の分割方法について話し合う手続きです。
相続人だけで話し合う遺産分割協議とは異なり、家庭裁判所の調停委員が間に入ったうえで協議を進めます。
自分の意見は調停委員を介して相手方に伝えられ、相手の意見は調停委員を通じて伝えられます。揉めている相手と直接話をせずに済むので、お互いに感情的にならずに話を進めることができます。
調停が成立すると、裁判所が調停調書を作成します。調停調書があれば、不動産の登記(名義変更)や預貯金の解約払い戻し、出金や名義変更などの相続手続きを実行することが可能となります。

02.遺産分割調停を行うタイミング
遺産分割調停を行うのは、相続人らによる遺産分割協議が決裂したタイミングが適切です。
以下のような理由によって遺産分割協議が決裂した際には調停を申し立てたほうが良いでしょう。
- 不動産の分割方法について合意ができない
- 特定の相続人が寄与分を主張している
- 特別受益の持ち戻し計算について争いがある
03.遺産分割調停では解決できないケース
以下のような問題については、遺産分割調停では解決することはできません。
- (ある人が)相続人かどうかでもめている
- 遺産の範囲に争いがある
①のパターンとしては「相続人の息子である」と名乗り出た者が本当に息子であるのかが不明な場合があります。②のパターンとしては、隠し財産があると疑われる場合や預貯金の使い込みがある場合などです。
このようなケースではまず相続人や遺産の範囲を確定する裁判(訴訟)を行い、前提となる問題を解決しておく必要があります。


遺産分割調停のメリット
遺産分割調停を行なうことのメリットとしては以下のものが挙げられます。
01.法律的に妥当な解決ができる
相続人だけで話し合いを行なう遺産分割協議の場合、知識不足から特定の相続人が有利になったり特定の相続人が不利になったりしてしまうケースが多々あります。
他方で遺産分割調停においては、調停委員や調停官(裁判官)が関与します。法的知識を有する中立の立場の方が話し合いを誘導してくれるので、おおむね法律の考え方に沿って公平な解決を実現できます。法律の趣旨にそぐわない極端な主張をする相続人がいる場合、その主張内容が実現困難であることを説得してもらうことも可能です。
02.解決案を提示してもらえる
のリスクと解決方法.jpg)
相続人だけで話し合いを行なう遺産分割協議の場合、互いが自身の主張を声高に主張し収集がつかなくなってしまうケースが往々にしてあります。
遺産分割調停では、調停委員と調停官が事案に応じた解決案を作成して当事者に示してくれます。提示された解決案に対し相続人全員が納得すれば調停成立となるので、問題解決の可能性が高まります。
03.調停調書に強制執行力がある
遺産分割の内容によっては、特定の相続人が別の相続人に代償金を支払う内容にする場合があります。たとえばある人が不動産を単独で相続し、その代償金として相応額を他の相続人に支払うケースなどです。
このようなケースにおいて代償金を分割払いとした場合、将来支払われない(不払いとなるリスク)が想定されます。
実は、遺産分割調停で調停が成立した場合に作成される調停調書は債務名義となります。債務名義には強制執行力がありますので、代償金の不払いがあった場合には調停調書をもって相手の財産を差し押さえることが可能となります。


遺産分割調停のデメリット
遺産分割調停を行なうことのデメリットしては以下のものが挙げられます。
01.全員が合意しないと解決に至らない
遺産分割調停も話し合いの手続きであるため、当事者全員が合意しないと成立しません。
調停委員や裁判所が解決案の提示や説得を行ないますが、解決案で着地することを強制することができませんので、提示案に反対する相続人がいるケースでは調停は不成立となってしまいます。
02.労力がかかる
遺産分割調停を行なうためには、①申立書を作成し、②戸籍謄本等を揃えて、③申立書及び添付資料を裁判所に提出し、④調停に都度出席して話し合いをしなければなりませんので、かなりの労力を要することとなります。
遺産分割調停の流れ
について.jpg)
遺産分割調停は以下のような流れで進みます。
01.調停申立て
まず遺産分割調停の申立てを行います。
申立ての際には、以下のような書類を作成・収集する必要があります。
- 申立書
- 遺産目録
- 当事者目録
- 相続関係説明図
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産に関連する資料など
上記の書類とともに被相続人1名につき1,200円の収入印紙と連絡用の郵便切手を付けて提出します。なお、必要となる郵便切手は管轄裁判所によって異なります。
管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。相手方が複数いる場合にはそのうちの1人の住所地の家庭裁判所を選んで申し立てることとなります。
02.調停の参加者
遺産分割調停には、法定相続人全員に参加してもらう必要があります。
参加者を、申立人側か相手方が若のいずれかの側に分けなければなりません。共同で申し立てる相続人以外は、全員「相手方」として申立てするのが通常です。

03.調停期日における話合い
申立が受理され調停が始まると、調停期日毎に家庭裁判所に出頭し相手方と話を進めていくこととなります。
1回の期日では解決できないのが通常であるため、都度期日が設定され、話し合いを重ねていくこととなります。期日は通常、月1回程度のペースで設定されます。回数や期間に制限はありません。
04.調停成立
遺産分割の方法について相続人全員の合意が得られれば調停成立となります。裁判所が調停調書を作成し、相続人全員に1通ずつ送ります。
以後、相続人は調停調書を用いて相続手続きを進めていくこととなります。
05.調停不成立の場合(審判移行)
調停で合意に至らなかった場合は、調停は不成立となり、遺産分割審判という手続きに移行します。
遺産分割審判は、審判官に遺産分割の方法を終局的に決めてもらう手続きです。審判官が法律に従って強制的に決定するものであり相続人の賛成・反対は関係ありません。
審判で有利な結果を得るためには適切な主張と資料提出が必要となります。手続きを有利に進めるためには法律の知識や専門的な考え方が必要不可欠ですので、弁護士に手続きを依頼されることを推奨します。
さいごに
遺産分割調停を有利に進めるには、調停委員にわかりやすく自らの希望を伝えて相手を説得してもらう技量が要求されます。弁護士を調停の代理人とすれば適切に権利を実現することが可能となります。また、弁護士を代理人にしていれば審判に移行したとしても優位に進めることが可能となります。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所は、遺産分割トラブルに注力しており、同トラブルについて多数の解決実績を有しております。
これから遺産分割調停を申し立てる方、すでに調停をされている方で手続きを優位に進めたい方はぜひお気軽にご相談下さい。