相続・遺産分割協議の場面で、故人の遺産に土地や建物といった不動産が残されていると、トラブルに発展することが多くあります。これは、不動産が、現金や預金と違って実際に分割するのが困難であること、資産価値が高額となることが多くあること、評価方法によって評価額にブレが生じることといった理由によるものです。
相続不動産の相続方法(分割方法)は「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類に大別され、各方法にはそれぞれにメリットやデメリットがあります。状況に応じて適切な分割方法を選択しましょう。
今回の記事では、相続不動産の分割方法3種類の内容、メリット・デメリット等について弁護士が解説します。
不動産の相続が難しい理由
相続財産に土地や建物、畑や山林といった不動産がある場合、相続(遺産分割)が煩雑となることがあります。その理由としては下記のものが挙げられます。
- 現金や預貯金と異なり、簡単に分割できるものではないこと
- 資産価値が高額(数百万円以上)となることがほとんどであること
- 住居の場合、一部の相続人が今後も住み続けることを希望することがほとんどであること
上記のような事情により、相続人同士で相続方法(分割方法)について話し合っても意見がすんなりと一致することはなかなかありません。ケースによっては訴訟トラブルに発展することも珍しくありません。
また、相続、遺産分割をせずに放置してしまうと単純相続となり、相続人による共有の状態となってしまいます。こと不動産は共有の状態だと共有者が単独で自由に不動産を活用することができません。売却や賃貸活用などの際に他の共有者(相続人)の同意が必要になりますし、各種租税の支払の場面でもトラブルが発生してしまうことでしょう。
不利益を被る可能性がある以上、なるべく早めに不動産の分割方法について手配を取るべきといえるでしょう。

相続不動産の分割方法
相続財産に不動産がある場合に、不動産を分割する方法としては以下の3種類があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
それぞれの分割方法について、確認してみましょう。

現物分割

現物分割は、不動産を相続人の一人が単独で相続する方法です。「長男が実家の土地建物を単独で相続する」ようなケースがこれに該当します。
相続不動産を数筆に分割して、各相続人がそれぞれを相続するパターンもあります。たとえば「土地を2筆に分筆して、1筆を長男、1筆を二男が相続する」といったものです。
01.現物分割のメリット
現物分割のメリットは、他の分割方法に比べて手続きが簡単なことです。相続人の一人が単純に相続すれば良いだけですので、不動産の評価も不要ですし不動産会社に売却を依頼する必要もありません。
なお、相続不動産を分筆して複数の相続人で分ける場合には、測量会社や登記事務所などに依頼して不動産の分筆手続きを進める必要が出てくるため、労力がかかります。
02.現物分割のデメリット
現物分割のデメリットは、不公平な結果になりやすくトラブルに発展しやすいことです。
得てして不動産の資産評価額は高額となることがほとんどです。現物分割により相続人の一人が単独で全部を相続すると他の相続人との関係で不公平になってしまい、他の相続人から不平不満が出て遺産相続トラブルに発展する可能性が高いです。
代償分割

代償分割は、不動産を単独取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払って清算する方法です。この代償金の金額は、法定相続分に応じた額です。
たとえば相続人が兄弟3人(相続分はいずれも3分の1)、相続財産が実家(資産価値3000万円)のみである場合、長男が実家を単独で相続し、その代わりに次男と三男に対し代償金として1000万円ずつ支払います。このように処理することで、兄弟3名とも平等に相続できたこととなります。
代償分割は現物分割の不公平感を解決するための方法といえます。
01.代償分割のメリット
代償分割のメリットは相続人が公平に相続できるということです。不動産を取得した相続人は他の相続人に対し法定相続分に応じた代償金を払うこととなるので、不動産を相続しなかった相続人から金銭的な面での不平不満が出るリスクを低減することができます。
02.代償分割のデメリット
代償分割のデメリットとしては以下のものがあります。
- 代償金を支払うことが出来るだけの資力が必要
- 不動産の評価でトラブルに発展しやすい
①についてですが、代償分割の性質上、不動産を相続する人に代償金を支払えるだけの資力がないといけません。先の例でいえば長男に代償金合計2000万円を支払うだけの資力がないといけないということです。
②についてですが、代償分割をするためには相続不動産の資産価値を評価しなければなりませんが、不動産の評価方法は一律ではありません。査定会社や査定方法によって評価額は変動します。評価額が小さいと代償金として支払う金額が小さくなりますので不動産を相続した側(先の例では長男)が有利になりますし、評価額が大きいと代償金を受け取る側(先の例では二男・三男)が有利となります。
評価額によって当事者双方に有利・不利が生じるため、評価額の算出基準の点でトラブルになることが多々あります。

換価分割

換価分割は、相続不動産を売却し、売却代金を相続人で分け合う方法です。売却代金は法定相続分に応じて分配します。
たとえば相続人が兄弟3人(相続分はいずれも3分の1)、相続財産が実家(資産価値3000万円)だけである場合、不動産を売却処分し、売却代金3000万円を1000万円ずつ相続します。
01.換価分割のメリット
換価分割のメリットとしては次のようなものがあります。
- 公平に分割できる
- まとまったお金がなくても利用できる
- 租税の支払資金を確保できる
①についてですが、換価分割では不動産を売却処分することで得た売却代金を法定相続の割合で分けることになるので、相続人間で公平に分割することができます。不動産評価額算定に関し発生するトラブルも生じることはありません。
②についてですが、代償分割のように不動産を相続した人が代償金を支払うといったことがありませんので、手元にまとまったお金がなくても採用することができます。
③についてですが、不動産を売却できればまとまったお金を受領することができますので、相続税の納税資金等を確保することが可能となります。
02.換価分割のデメリット
換価分割のデメリットとしては以下のようなものがあります。
- 不動産を失うこととなる
- 手数料等により資産価値が目減りする
- すぐに売却できるとは限らない
①についてですが、換価分割では不動産を売却することが前提となるので、当然不動産を失うこととなります。相続不動産が実家である場合は実家を失うということです。喪失感に苛まれることもあります。
また、不動産を処分してしまえばその後に生じる可能性がある利益を享受することはできません。たとえば将来不動産市場が活況となって土地が値上がりしたとしてもその利益を享受することは当然できません。
②についてですが、不動産を売却できた際には仲介業者等に各種手数料を支払うこととなります。相続人の手元に残るのは各種手数料を差し引いたものになりますので、資産価値が目減りすることとなります。
③についてですが、不動産を売却に出したとしてもすぐに買い手が見つかるとは限りません。買い手が見つからなければ売却代金を得ることができず、換価分割を進めることができません。

遺産分割協議が成立しない場合はどうなる?

不動産の遺産分割方法を「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれの方法で行なうかについては相続人が話し合って(協議して)決定することとなりますが、各方法にはメリット・デメリットがあり、相続人らで話し合っても解決できないケースもあり得ます。
遺産分割協議が決裂した場合は家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、調停の場で協議をすることとなります。調停の場で調停委員を交えて話し合っても合意できない場合には「審判」に移り審判官が不動産の遺産分割方法を決定することとなります。
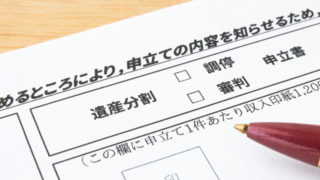
審判では「法定相続割合に応じた解決方法」が採用されるので不公平となりがちな現物分割が行われることはありません。また、共有状態のまま放置されることも基本的になく他の何らかの方法で公平に分割されることとなります。不動産を取得すべき相続人がいない場合や不動産を取得したい相続人がいても代償金を支払う資力がない場合には、競売命令が出て不動産を強制的に売却されるケースもあります。
競売になると一般の売却のケースよりも売値が下がってしまう可能性が非常に高くなります。得られる金額が低くなる可能性が明白である以上、競売による決着にはならないようにしたいものです。
さいごに
遺産相続問題はできる限り自分たちで話し合って解決する方法が望ましいです。審判により相続不動産を競売することとなると得られる金額が目減りすることとなりますし、なにより相続人間で遺恨が残ってしまいます。
相続人間の話し合いでの解決が難しいということであれば、弁護士を間に入れての対応も検討しましょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、相続、遺産分割の場面でのトラブルに対し注力しております。相続における各種トラブルについて広く相談を受け付けておりますので、お困りごとをお抱えの方は是非一度ご相談ください。






















