離婚の際に親権者とならなかった側は、子どもが成人になるまで養育費を支払わなければなりません。
しかし、親権者とならなかった側が約束どおりの養育費を支払うことは少ないのが実情です。7割超の方が取り決められた養育費を払っていないという調査結果もあります。
養育費を払ってもらえない場合は泣き寝入りするほかないのでしょうか?
そんなことはありません。法律において不払いの養育費を強制的に回収する方法が認められておりますので、こちらを利用して養育費の回収を図りましょう。
今回の記事では養育費を払ってもらえない場合の回収方法について解説します。
債務名義について
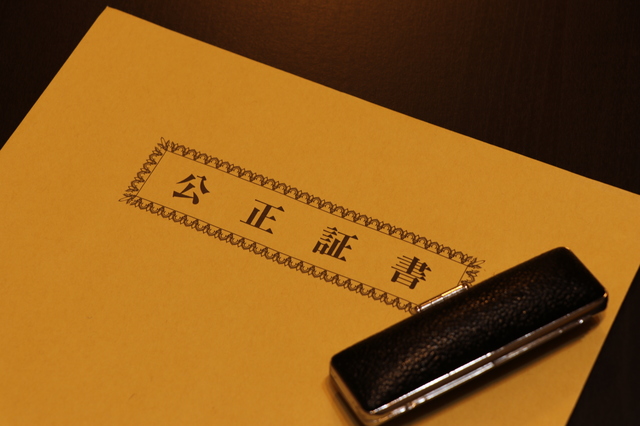
養育費を払ってもらえないときの対処方法は、公正証書や調停調書といった債務名義があるかどうかで異なります。
それでは債務名義とは何なのでしょうか。確認してみましょう。
01.債務名義とは
債務名義とは、強制執行(差し押さえ)を申し立てる際に必要となる書面のことです。
債務名義を有しているのであれば、相手が不払いを起こした際に相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能となります。
養育費のケースでは、公正証書や調停調書などの債務名義を有しているのであれば相手が養育費の不払いを起こした際に相手の給与や預貯金を差し押さえることができ、差し押さえた給与や預貯金から強制的に養育費を回収することが出来ます。
他方で債務名義を有していない場合には、強制執行をすることはできません。相手に支払ってもらうよう督促するか債務名義を取りに行かなければなりません(詳細は後述)。

02.債務名義となるもの
こと養育費については以下の書面が債務名義となります。
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 判決書
- 和解調書
- 認諾調書
①の公正証書は、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。協議離婚の際、養育費や財産分与等の離婚条件等を公正証書で作成していれば、これが養育費についての債務名義となります。
また、②の調停調書は調停離婚を申立て調停が成立した場合に家庭裁判所から送られてくる書面、③の審判書は養育費の審判の後に家庭裁判所から送られてくる書面、④の判決書は離婚訴訟で離婚した際に裁判所から送られてくる書面、⑤の和解調書は離婚訴訟の途中で当事者の和解が成立した際に裁判所から送られてくる書面、⑥の認諾証書は請求の認諾によって離婚訴訟が終わったときに裁判所から送られてくる書面のことです。

債務名義は、公証役場ないし裁判所が介在した手続きを経ないと取得することはできません。
03.債務名義とはならないもの
裁判所や公証役場といった公的機関が関与して作成された書面が債務名義となります。
逆にいえば、当事者間で作成した離婚協議書や養育費に関する合意書が債務名義となることはありません。当事者間で取り決めた書面を基にして差押え等の強制執行をすることはできないということです。
04.協議離婚時に公正証書を作成していた方が良い理由
夫婦の協議で円満に離婚の合意が成立した(協議離婚)としても、その後の養育費の支払が約束どおりになされるとは限りません。
債務名義があれば、養育費の支払いがない場合に差押え手続きに進むことが出来ます。債務名義がない場合は訴訟提起するなどして別途債務名義を得なければなりません。
公正証書をあらかじめ作成しておけばこれを債務名義として利用することが出来るのでスムーズに差押えをすることが可能となります。また、相手方も「公正証書という形で債務名義を取られた以上、養育費の支払いをしなかったら強制執行される」という恐れから養育費の支払(債務の履行)をしっかりと行なうものと考えられます。
協議離婚において公正証書を作成しておくことが推奨される理由はこの点にあります。
_妻が離婚を決意したときに知っておくべき全知識~財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費~-320x180.jpg)
債務名義がある場合の養育費回収手順
公正証書や調停調書、審判書といった債務名義があるケースでの養育費回収の手順は次の通りです。
01.履行勧告、履行命令
家庭裁判所の調停や審判などで決まった事項に従わない相手に対しては、履行勧告や履行命令を利用することができます。
履行勧告は、裁判所から相手に対し「裁判所で決まった約束を守ってください」と促してもらう制度です。なお、履行勧告には強制力がありません。履行勧告に従わない場合のペナルティがないため、相手が支払いを強く拒否している場合には効果を期待できません。
履行命令は、裁判所から相手に対し「裁判所で決まった事項に従いなさい」と命令してもらう制度です。あくまで命令するだけであり強制力はありません。相手が命令に従わない(履行しない)可能性はあります。なお、履行命令に従わない場合、相手は「10万円以下の過料」という制裁を受ける可能性があります。
履行勧告、履行命令には強制力がありません。そのため不払いの養育費回収という点では実効性が薄いと言わざる得ません。そのため、ほとんどの方は履行勧告や履行命令をせずに強制執行手続きを行なっております。
02.差し押さえ(強制執行)
債務名義を有しているのであれば、そのまま差し押さえ(強制執行)の申立を行なうことが出来ます。
差し押さえとは、相手の資産や債権を差し押さえて強制的に現金化する手続きです。
以下のような相手名義の資産や債権を差し押さえることができます。
- 給与、賞与(ボーナス)
- 退職金
- 預貯金
- 保険(解約返戻金のあるもの)
- 不動産
- 車
- 動産
- 株式、投資信託
財産を差し押さえた場合、そこから未払いの養育費を回収できます(換価を要するものである場合は、換価後に回収することとなります)。
なお、給与を差し押さえることが出来れば、将来分の養育費も継続的に回収することができます。相手が仕事をやめない限り養育費を継続して受け取ることができることとなるので非常にメリットがあります。

債務名義がない場合の養育費回収手順
債務名義がない場合、以下のような手順で回収することとなります。
01.相手に請求する
まずは相手にメールや電話などで支払いを求めましょう。相手が無視するようであれば、内容証明郵便を使って請求書を送ってみるのもよいかもしれません。
内容証明郵便は自分で送ることもできますが、弁護士から送れば相手に強いプレッシャーを与えられますし支払いを受けられる可能性が高くなります。
02.公正証書を作成する
上記の請求によって相手が支払いに応じるようであれば、養育費に関してしっかりと取り決め合意内容を公正証書化しておきましょう。公正証書としておけば債務名義を得たこととなるので以後不払いがあった際に強制執行することが可能となります。
03.養育費調停を申し立てる
相手方が支払いに応じないようであれば、家庭裁判所に養育費調停を申し立てましょう。
養育費調停では調停委員が間に入って養育費の話し合いを進めていきます。養育費の金額には相場があり、調停委員は相手方に対し相場に従った金額を払うよう説得してくれます。
養育費調停において、相手が支払いに納得しお互いに合意できれば調停が成立し、数日後に当事者へ調停調書が送られてきます。調停調書は債務名義となるので、相手が約束を守らないときに差し押さえが可能となります。
04.審判に移行
養育費の金額等について調停で合意できなかった場合には、調停は不成立になり審判に移行します。
審判では裁判官が養育費の金額を決めて相手に支払い命令を下します。命令の内容は審判所として当事者に送達されます。審判書も債務名義となりますので、相手が従わないときには給料等の差し押さえができます。大切に保管しましょう。

差し押さえの手順

差し押さえ(強制執行)は、裁判所への申立が必要な複雑な手続きです。具体的な手順をみてみましょう。
01.差し押さえ対象を確定する
差し押さえ対象とする財産は、債権者側で特定する必要があります。
この特定作業は簡単そうに見えますが、実際には難しいことが往々にしてあります。
たとえば給料を差し押さえる場合は、相手方の勤務先を特定しなければなりません。離婚後に相手が転職していたりすると特定が難しいことがあります。
また、預貯金を差し押さえる場合には相手がお金を入れている口座の金融機関名と支店名の情報が必要となります。相手がメイン口座を変えていたりすると特定が困難となることがあります。
他の財産についても同様です。保険を差し押さえる場合には相手が契約している生命保険会社を特定する必要がありますし、不動産を差し押さえるのであれば物件所在地や地番、家屋番号などを特定するための全部事項証明書を取得する必要があります。株式を差し押さえるのであれば取引している証券会社名を明らかにしなければなりません。
夫婦であったころなら生活を共にしているのでこれらを特定しやすいですが、離婚して一緒に暮らしていない場合は、これらを特定することが困難となることが往々にしてあります。
02.第三者からの情報取得手続を利用する
上述のとおり、相手が転職したりメイン口座を変えていたりすると給与や預貯金を差し押さえるための特定が困難となることが多々あります。
この場合はどうしようもないのでしょうか?特定を諦めなくてはならないのでしょうか?
実はそんなことはありません。第三者からの情報取得手続を利用することで相手方の情報を取得することが可能です。
第三者からの情報取得手続は近年の法改正によって新たに導入された手続きで、裁判所が年金機構や市町村役場、金融機関、法務局等の各種機関に対し相手の情報を照会することで相手の勤務先や取引金融機関を明らかにすることができます。

第三者からの情報取得手続を利用することで以下の情報を入手することができます。
- 勤務先
- 取引している金融機関の支店名
- 不動産に関する情報
なお、保険は第三者からの情報取得手続きの対象とはなっておりません。保険を差し押さえるのであれば自力で特定する必要があります。
03.必要書類を準備する
差し押さえの対象が決まったら、強制執行を申し立てるための必要書類を集めなければなりません。
- 債務名義
- 執行文
- 送達証明書
- 差押命令の申立書
- 各種目録
- 商業登記簿謄本
①の債務名義は、調停調書や公正証書、審判書などの書面のことです。審判書や判決書の場合は確定証明書も必要となります。
②の執行文は債務名義を発行してもらった機関に対して申請して発行してもらう書面です。債務名義が調停調書であれば、調停が成立した家庭裁判所に対し執行文の発行を申請しましょう。
③の送達証明書は、債務名義が相手に送達されたことを証明する文書です。債務名義を発行した機関に対し送達証明書の発行を申請しましょう。
④は差押えをするための申立書です。書式に従って作成します。また、⑤についてですが、当事者目録や差押債権目録、債権目録などを作成しなければなりません。必要部数も事案によって異なります。
⑥の商業登記簿謄本ですが、第三債務者たる銀行や相手の勤務先が法人の場合に必要となります。
必要書類の準備や申立書の作成はそれなりの労力がかかります。また、不備があれば差押命令の申立書を受理してもらうことが出来ません。自身では対応が難しいということであれば専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

04.地方裁判所へ申立を行なう
必要書類の準備が出来たら地方裁判所に対し差押の申立をしましょう。
申立書類に不備がなければ、差押命令が発令されて相手の勤務先や金融機関などへ差押命令が送達されます。相手方本人にも差押命令書が送られます。
債権差押命令が発令されたら、第三債務者に連絡して対象財産の差押えを行いましょう。
05.差押え
給与や賞与を差し押さえる場合は、相手の勤務先に連絡します。
なお、差し押さえができるのは、相手の手取り額の2分の1(相手の手取りが66万円を超える場合には33万円を超える全額)です。給与や賞与の全額を差し押さえられるわけではないことにご留意ください。
預貯金を差し押さえる場合は、対象の金融機関へ連絡して差し押さえた預貯金から支払いを受けましょう。債権差押命令が送達された時点で口座は凍結され、相手本人は出金できない状態になっていますので早めに連絡して取り立てましょう。
保険を差し押さえる場合は、保険を強制解約して解約返戻金から取り立てを行います。
なお、不動産や動産、自動車などを差し押さえた場合には、競売を行って売却(換価)する必要があります。競売手続きには手間と費用と時間がかかりますので、即効性を求めるのであれば給料や預金などの債権を差し押さえに行く方が良いでしょう。
06.取立届を提出する
取立が終わったら裁判所へ取立届を提出しましょう。全額回収できた場合には取立完了届を提出します。
1回の差し押さえでは全額回収できなかった場合や不払いが続くような場合には別の機関に対し改めて差し押さえの申立を行ないましょう。
養育費を滞納されたら早めに請求を
相手が養育費を払わない場合はできるだけ早く請求しなければなりません。なぜなら債務名義がない場合の未払い養育費は請求したときからの分しか支払ってもらえないためです。離婚時に養育費の約束をしなかった場合、一般的に養育費調停を申し立てるまでの分は支払われません。離婚時に養育費の取り決めをしても公正証書にしていなければ、養育費の調停を申し立てた月からの分しか払ってもらえない可能性があります。
滞納額が大きくなると相手の支払い意欲も落ちてしまうため、全額回収のハードルが上がってしまうというデメリットもあります。
また、請求を何年も放置してしまうと養育費の請求権が時効にかかってしまい回収できなくなってしまうこともあり得ます。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、離婚や男女問題、子どもの法律トラブル解決に力を入れて取り組んでいます。養育費の不払いについての事案も受け付けておりますので是非一度ご相談ください。




、DV離婚-640x360.jpg)

















