離婚事件の相談者の方から、「調停前置主義とは何でしょうか?」「なぜ訴訟の前に調停をしなければならないのでしょうか?」といった質問を受けることがよくあります。
離婚問題の場合、相手方(配偶者)との対立が深く、話し合いでは到底解決できない状態に陥ってしまっていることは珍しくありません。父母の双方ともに子どもの親権を強く希望している場合、当事者間の話し合いでの解決は困難であるため調停でも解決には至らないことはザラです。
このようなケースであっても「調停しても決裂するのが目に見えているから」と調停を飛ばしていきなり裁判(離婚訴訟)を提起することはできません。日本の司法制度では調停前置主義が適用されるからです。調停前置主義とは「訴訟の前に必ず調停を行ない、調停が不成立となったときに初めて訴訟を提起することができる」というルールをいいます。
今回の記事では、調停前置主義の内容や適用されるケース、例外として調停なしで訴訟提起できるケースについて弁護士が解説します。
調停前置主義とは
調停前置主義とは「訴訟を提起する前には必ず調停をしなければならない」という法律上の原則です。
01.調停とは
調停とは、裁判所で調停委員を介して話し合うための手続きです。調停委員2名と調停官が間に入って当事者間の意見を調整します。
調停を利用すると相手方と直接顔を合わせてやり取りする必要がありません。調停委員会が介在してやり取りをすることになるので、当事者同士が険悪な関係になってしまい話し合いができないケースであっても事態を解決できる可能性は高くなります。
02.訴訟とは
訴訟とは、裁判所へ事件の申立を行ない裁判官に一定の結論を出してもらう手続きです。調停とは異なり話し合いの手続きではありません。
訴訟で有利な判決を得るためには法律的に正しい主張や立証を行う必要があります。調停では法律論に従わずに感情論で希望を出しても通る可能性がありますが、訴訟では法律的に間違っている主張は100%とおりません。
そのため、訴訟では専門的な知識や対応が必要となります。訴訟を有利に進めたいのであれば弁護士によるサポートが必須といえるでしょう。

03.調停前置主義の理由や根拠
なぜ離婚事件には調停前置主義が適用されるのでしょうか?
それは「家庭に関する問題はできるだけ家庭内で解決すべき」「家庭の問題は当事者が互いに譲り合って自分たちで解決すべき」という考え方が前提にあるためです。離婚のような家族の問題に最初から裁判所が介入して結論を押しつけるのは好ましくといえますので、この考え方は相応といえるでしょう。
また、訴訟手続は公開法廷にて行われますので誰でも傍聴できる状況にあります。家庭内の問題を世間に公開することを望まない人も多いでしょう。調停であれば手続きは非公開なので夫婦の問題を第三者に知られることはありません。
このような理由が根底にあって調停前置主義が適用されています。
04.調停前置主義の根拠条文
調停前置主義の根拠条文は、家事事件手続法という法律にあります。
第257条(調停前置主義)
第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
家事事件手続法第257条第1項にて「離婚訴訟などの家庭に関する訴訟を提起する際にはまず調停を申し立てなければならない」と規定されております。これが調停前置主義の根拠です。
なお、この調停前置主義には例外があります。どのような場合でも絶対に調停を先にしなければならないというわけではありません。例外については後の項で解説します。
調停前置主義の対象となる事件

調停前置主義が適用されるのは離婚事件だけではありません。
以下のような事件においても調停前置主義が適用され、訴訟を提起する前に調停を行う必要があります。
- 夫婦の離婚
- 養子縁組の離縁
- 婚姻無効確認
- 婚姻取消
- 離縁無効確認
- 離縁取消
- 嫡出否認の訴え
- 認知の訴え


で離婚!後悔するパターンや損しないための対処方法を弁護士が解説!-320x180.jpg)
調停なしで訴訟を提起したらどうなる?

01.調停をせずに訴訟を提起した場合の処理
調停をせずに離婚訴訟を提起した場合、すなわち調停前置主義を無視した場合はどうなってしまうのでしょうか?
家事事件手続法第257条第2項において以下のとおり定められております。
第257条第2項
前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
調停をせずに訴訟を提起した場合は裁判所が職権で調停にまわしてしまうということです。いきなり離婚訴訟を起こしても裁判所の判断で自動的に調停となり調停手続きが開始されることとなります。
調停前置主義を無視して訴訟を提起しても不適法却下(裁判所が「訴訟の要件を満たさない」として訴えを却下してしまうこと)とはならないことを理解しておきましょう。
02.管轄
離婚調停と離婚訴訟では管轄が異なります。
離婚調停は「相手方の住所地を管轄する裁判所」または「当事者が合意で定めた家庭裁判所」です。
他方で離婚訴訟では「原告の住所地の家庭裁判所」または「相手方の住所地の家庭裁判所」です。合意管轄は認められておりません。
離婚調停をする場合においてお互いの住所地が異なると管轄が遠方となってしまうことに注意しましょう。
03.調停なしに訴訟提起した場合の管轄
調停前置主義を無視して離婚訴訟を起こした場合、どこの管轄の家庭裁判所で処理されるのか?
家事事件手続法第257条第3項において以下のとおり定められております。
第257条第3項
裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
基本的には管轄権のある裁判所で処理されることになります。自分の住所地と相手の住所地が異なる場合において、自分の住所地の家庭裁判所にいきなり訴訟を申し立てた場合、裁判所の判断により調停は相手の住所地にて行われます。
なお、第3項では一定の例外を認めており、「特に必要があるとき」には訴えを受けた家庭裁判所で調停を処理できるとされております。
調停や訴訟の管轄については専門的な知識を要することが多々あるので迷ったときには弁護士へ相談しましょう。

調停前置主義の例外
調停前置主義により離婚事件では基本的に訴訟前に調停をしなければならないのですが、中には例外もあります。根拠となる条文は家事事件手続法第257条第2項但し書です。
第257条第2項
前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
この但し書き部分に該当する調停前置主義の例外について見てみましょう。
01.相手が3年以上生死不明なケース
離婚訴訟においては裁判上の離婚理由(法定離婚事由)がないと離婚を認めてもらえません。
法定離婚事由は民法によって5種類が定められていますが、そのうち1つに3年以上の生死不明があります。

相手方が3年以上生死不明な場合、調停を申し立てたとしても相手が出頭する見込みがほぼありません。そのため、相手方が3年以上の生死不明であることを理由に訴訟提起する場合には調停前置主義は適用されず、最初から訴訟を提起しても受け付けてもらうことができます。
02.相手が刑務所に長期間収容されている
相手が犯罪を犯して刑務所に長期にわたって収監されている場合、調停をして呼び出しても出頭できる見込みはありません。
そのためこのようなケースでも調停前置主義の例外となり最初から離婚訴訟をしたとしても受け付けてもらうことができます。
03.相手に強度の精神障害があって通常の判断ができない場合
法律上の離婚原因には「相手方が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと」というものもあります。「相手方が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと」とは、パートナーの統合失調症や双極性障害などが極めて重度で医学的に回復しがたい状態をいいます。
相手が強度な精神病にかかっていて通常の判断ができない場合には調停をしても合意できる見込みがありませんので、調停前置主義の例外として最初から訴訟を受け付けてもらえる可能性があります。
なお、この場合はこれまで献身的に看護してきたことや離婚後に病人側の生活が保障されていることなどを要件として離婚が認められます。

調停不成立と取下げの違い
調停前置主義における調停の終了ですが、調停が「不成立」となることが必要です。「取下げ」では足らないことに注意しておきましょう。
01.不成立
調停不成立は、合意に向けて双方で話し合いを行なったが結果として合意できなかった場合のことを言います。
「話し合ったけどダメだった」すなわち「調停を行なったけど結果が出なかった」ということで調停自体は正常に終了していることになります。不成立となった場合、不成立証明書が発行されます。
02.取下げ
取下げは、調停を途中で終わらせて「初めから行われなかったこと」にしてしまうことをいいます。
調停自体が行われなかったこととなるため、取下げで調停が終わった場合は調停前置主義の要件を満たしません。不成立証明書も発行されないので裁判所へ離婚訴訟を提起できません。
03.訴訟を予定しているなら調停は不成立で終わらせる
調停後に訴訟提起することを検討しているのであれば、取り下げではなく不成立にするようにしましょう。
合意が難しい調停において、調停委員から「取り下げるように」といわれるケースがありますが、後の訴訟を検討している場合には絶対に従ってはなりません。不成立で終わらせるようにしましょう。
さいごに
離婚調停や離婚訴訟を有利に進めるためには専門的な知識が必要です。自身の判断で対応してしまうと不利な条件を受け入れてしまったり取り下げてしまったりして不利益を受ける可能性があります。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では離婚や男女問題に力を入れて取り組んでいます。離婚問題にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
、DV離婚-320x180.jpg)


、DV離婚.jpg)
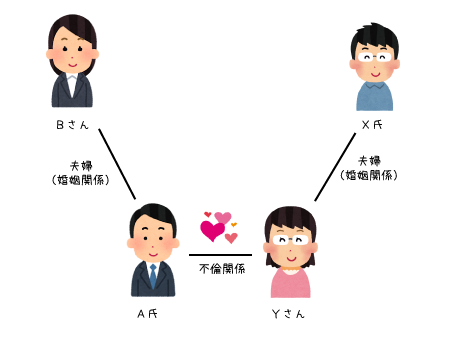
で離婚!後悔するパターンや損しないための対処方法を弁護士が解説!-640x360.jpg)
















