- 長年連れ添ってきたけれど、子どもも独立したので離婚したい
- 定年後は自由に生きていきたいので離婚したい
このような考えをもって熟年離婚を選択肢に入れる方が増えております。
仮に熟年離婚をした場合、その後の生活にどのようなメリットやデメリットが生じてしまうのでしょうか?
今回の記事では、熟年離婚のメリットやデメリットなどについて解説します。熟年離婚を検討されている方はぜひ参考にしてください。
熟年離婚
01.熟年離婚とは
熟年離婚とは、長年連れ添った夫婦の離婚のことです。
何年以上連れ添うと熟年といえるのか、については明確な基準はありません。一般的には20年程度連れ添った夫婦が離婚する場合は熟年離婚といえるでしょう。
02.熟年離婚の件数は大幅に増加
昭和の時代からの推移をみると、熟年離婚の件数は明らかに増加しています。
厚生労働省の人口動態統計によると、昭和60年における「婚姻年数20年以上の夫婦の離婚」は20,434件でした。それが平成28年には37,604件にまで増えています。
03.熟年離婚の割合も増加
熟年離婚がもっとも多かったのは平成17年の40,395件であり、その後10年の間に多少減少しています。
なお、平成17年と平成28年では「離婚の件数」が異なります。平成17年の離婚件数は261,917件でしたが、平成28年は216,805件にまで減っています。全体の離婚に占める熟年離婚の割合をみると、平成17年は15.42%、平成28年は17.34%となるので、熟年離婚率はむしろ増加しているといえるでしょう。
このように、近年の日本には多くの夫婦が熟年離婚している現状があります。

熟年離婚の典型的な例

熟年離婚の典型例を見てみましょう。
01.夫の定年退職を機に妻が離婚を決意
熟年離婚の典型例の一つは、夫が定年退職したのをきっかけに離婚するパターンです。
これまでは日中は会社に行っていた夫が定年退職後は一日中家にいるので、妻としては生活のリズム・ペースが狂ってしまいストレスを感じてしまうようです。夫の定年退職によって退職金も入っているだろうから財産分与をもらって離婚後の生活費にあてよう、という考えも根底にあるのかもしれません。
02.自由に生きるため夫が離婚を決意
従来、熟年離婚といえば妻が求めるケースが多数でしたが、最近では夫側が離婚を希望するケースも増えています。
定年退職を機に第2の人生に期待する男性が多いためです。妻から解放されて自由に生きたいと考えるようで、そこから熟年離婚を検討されます。
03.子どもが独立したので離婚
子どもが小さいうちは、夫婦仲が悪くても我慢するしかないケースも多いでしょう。女性が子どもを抱えて1人親として生きていくのは厳しい現状もあります。
子どもが成人し独立したら「もうこれで離婚しても良いだろう」と考え、熟年離婚を真剣に検討し始める女性も少なくありません。
熟年離婚が増えている社会的な背景

日本における熟年離婚の増加に関しては、以下のような社会的背景も影響していると考えられます。
01.離婚への偏見がなくなった
皆さんの周囲に離婚経験のある方は多いのではないでしょうか?
日本では、ここ数年間で離婚への偏見が非常に小さくなったといえるでしょう。一昔前は「いい年して離婚なんて恥ずかしい」という意識がありましたが、最近では離婚が当たり前になっているように見受けられます。
このような背景もあって、昔に比べて熟年離婚を検討しやすくなっています。
02.稼げる女性が増えた
一昔前は女性が自ら働いてお金を稼ぐのは困難でした。特にシニア世代の女性は仕事をしていないケースが多く、離婚すると生活不安があるのでやむなく結婚生活を続けるケースが多々ありました。
最近では女性の社会進出が進み、仕事を持つ女性が増えています。夫に頼らなくても充分な稼ぎがあるので熟年離婚に踏み切りやすくなっている現状があります。
03.家事ができる男性が増えた

従前は家のことは何一つせずに妻に100%任せる男性がほとんどでした。自分では料理も選択も掃除もできないので、離婚するとたちまち生活の質が低下してしまい困ってしまう方が多かったのです。
最近では定年退職後に料理にはまる男性も増えて、ある程度自分の身の回りのことをこなせるようになっています。こうした社会的背景も男性側からの熟年離婚を後押ししているでしょう。
04.寿命が延びた
日本人の平均寿命はどんどん延びており、男女ともに80歳を超えている現状です。アクティブなシニア層も多く、60歳を超えても自分の好きなことをいろいろ楽しみながら人生を過ごしている方がたくさんいます。
定年退職を迎えた時、この先の長い人生を考えると嫌な相手と過ごすのは苦痛となるでしょう。このような夫婦は熟年離婚をする傾向にあります。
熟年離婚のメリット

01.人生をやり直せる
熟年離婚すると夫婦関係をリセットすることができます。
離婚後は独り身となりますので、海外移住してもかまいませんし趣味に没頭することも可能となります。別の相手と再婚する方もおられますし、籍を入れずに好ましい相手と内縁関係となってパートナーシップを結ぶ方もいます。
このように離婚して独り身に戻ることで人生をやり直すことができるといえます。
02.ストレスのない生活を送れる
気に入らない相手とずっと一緒に過ごすのは大きなストレスとなるでしょう。特に子どもが独立して家を出ている場合などには夫婦2人きりで過ごすこととなるので閉塞感が強くなります。
熟年離婚して独り身になれば相手の嫌なところも目に付きません。ストレスなく生活できるでしょう。
03.相手の実家との親族づきあいをやめることができる
結婚しているとどうしても相手の親族とのかかわりが生まれるものです。配偶者はそれほど嫌ではないけれど、配偶者の親族づきあいが耐えがたい苦痛という方もおられるでしょう。
離婚すれば配偶者との実家とは完全な他人になります。煩わしい親族づきあいを断ちたい方には熟年離婚は大きなメリットがあるといえるでしょう。

熟年離婚のデメリット

01.生活が苦しくなるおそれがある
専業主婦の方やパート勤務の方のような経済力の低い方が熟年離婚すると、後で金銭的に困る可能性が非常に高いといえます。年金分割を受けても月々の生活費に充分な金額にならないケースが多数です。
熟年離婚前に離婚後の生活設計をしっかり行っておく必要があるでしょう。
02.孤独になる
配偶者と離婚すれば当然に独り身になってしまいます。子どもや友人と関わりがあれば良いですが、子どもがいなかったり疎遠であったり、友人づきあいもしていなかったら孤独感にさいなまれるでしょう。
嫌な相手であってもいるのといないのとでは違うものです。離婚前に自分の性格や周囲の環境を見つめ直して1人になっても大丈夫なのかを考えてみましょう。
03.介護を頼れる人がいない
熟年離婚した場合、介護してくれる人がいなくなる可能性があります。
天涯孤独で老人ホームに入るしかないケースもあるでしょう。子どもがいれば頼れるかも知れませんが、余計な負担をかけてしまいます。

お金の問題

熟年離婚で重要なポイントになるのが、お金に絡む問題です。特に財産分与と年金分割は外せない課題となるでしょう。
01.財産分与
財産分与は、離婚時に夫婦の共有財産を分け合う手続きです。婚姻中に積み立てた財産を原則として2分の1ずつに分配します。
熟年離婚の場合、婚姻期間が長いので共有財産も高額になる傾向があります。退職金も財産分与対象になりますので、財産分与の際をこれを含めて計算します。
財産分与を受けるために重要なポイントは以下のとおりです。
- 財産隠しを防ぐ
- 使いこみを防ぐ
①についてですが、相手は財産分与を減らすために、財産隠ししようとするケースが多々あります。たとえば、預貯金や株式などを開示せず、少ない財産を前提に財産分与を計算するのです。そうなったら本来より少額な財産分与しか受けられないので不利益を被ることとなります。
財産分与の際は相手方が財産隠しをしていないかしっかりと調査しましょう。
なお、相手が隠していても、弁護士照会や裁判所への申立をすれば開示を受けられる可能性があります。

また、②についてですが、せっかく財産があっても、相手が使い込んでしまったら分与を受けられなくなる可能性があります。不動産を売却されそうなケース、退職金を使い込まれそうなケースなどでは「仮差押」という方法で凍結させることも可能です。

02.年金分割
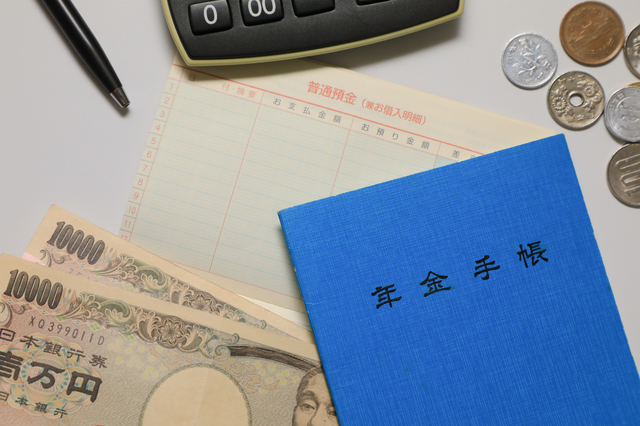
熟年離婚では年金分割も非常に重要です。
年金分割とは、婚姻中に払い込んだ年金保険料を夫婦で分け合う手続きです。夫婦の双方または一方が厚生年金(共済年金を含む)に加入している場合に分割が可能となります。
平成20年3月以前から年金に加入していた場合に年金分割を行うには、分割される人との合意が必要です。これを「合意分割」といいます。離婚前に夫と話し合い、年金分割の合意をとりつけておきましょう。
平成20年4月以降の年金について、被保険者だった場合には合意なしに年金分割を受けられます。これを「3号分割」といいます。この場合、離婚後に1人で年金事務所へ行けば分割の手続きができます。
熟年離婚の場合、合意分割が必要なケースが多いでしょう。相手が分割に応じない場合でも裁判所で決めてもらえるので、あきらめる必要はありません。困ったときには弁護士までご相談ください。
03.慰謝料
相手が不倫していた、暴力を振るわれたなどの事情があれば、熟年離婚でも慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は婚姻期間に比例する傾向があるので、熟年離婚では高額になりやすいでしょう。
ただし慰謝料請求するには証拠が必要です。離婚交渉を始める前に、不倫や暴力などの有責性を示す資料を集めておいてください。

熟年離婚の流れ

熟年離婚は以下の流れで進めましょう。
01.相手と話し合う
まずは相手と話し合ってください。そもそも離婚に応じてもらえないと、協議離婚できません。離婚に応じるとしても、財産分与や年金分割、慰謝料などの諸条件を決定する必要があります。
02.離婚公正証書を作成する
話し合いによって離婚することと離婚条件に合意ができたら、書面化しましょう。離婚の取決めごとは「離婚公正証書」にするようお勧めします。
口約束では守られないおそれがあります。また公正証書でないと、不払いとなったときにいちいち裁判をしなければなりません。
公正証書があれば、滞納されたときにすぐに差押えができて便利です。公証役場に申し込んで公正証書を作成してもらいましょう。
03.離婚届を提出する

公正証書ができたら、役所で離婚届の用紙をもらってきて作成し、提出しましょう。
04.年金分割の手続きを行う
離婚届を提出したら、年金事務所へ行って年金分割の手続きを行いましょう。離婚しただけでは年金分割できないので、忘れずに必ず年金事務所へ行ってください。
合意分割の場合、原則として相手と2人で行かねばなりませんが、公正証書があれば請求者のみで手続きできます。3号分割の場合には、1人で手続きが可能です。
05.離婚調停を申し立てる

話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停委員が間に入って調整してくれるので、合意しやすくなります。
06.離婚訴訟を起こす
調停が不成立になってしまったら、家庭裁判所で離婚訴訟を申し立てましょう。ただ訴訟では法律上の離婚原因がないと離婚が認められません。すぐに離婚できない場合、しばらく別居して時間を置くべきケースもあります。
時機を見て、再度協議や調停を行ったりして離婚を進めていきましょう。
さいごに
熟年離婚で後悔しないためには法律知識や正しい対応が必要です。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、離婚問題に注力しており、多数の解決実績を有しております。熟年夫婦の離婚問題にも精通しております。
長年連れ添ったパートナーとの離婚を検討されている方はぜひ一度弁護士までご相談ください。
、DV離婚-320x180.jpg)




で離婚!後悔するパターンや損しないための対処方法を弁護士が解説!-640x360.jpg)
















