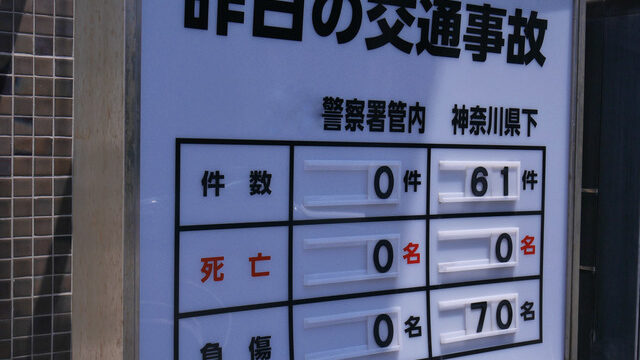飲酒運転による事故が後を絶ちません。有名人が飲酒運転による事故を起こす事例も相次いでおりますので関心をお持ちの方も多いでしょう。
交通事故の加害者が飲酒していたらどのような責任が発生するのでしょうか?また、飲酒事故の被害に巻き込まれた場合はどのように対処すればよいのでしょうか?
今回の記事では、飲酒運転での交通事故について解説します。
飲酒運転の罪

飲酒運転は、道路交通法によって処罰される犯罪です。飲酒運転に適用される刑罰には酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。それぞれの違いを見てみましょう。
01.酒気帯び運転
酒気帯び運転は、呼気1リットル中に0.15㎎以上のアルコールが含まれた状態で運転することです。一般的には交通検問の呼気検査で発覚するケースが多いでしょう。
交通事故が発生したときにも加害者に疑わしい言動があると呼気検査が行われます。飲酒運転による事故(飲酒事故)と判断されれば、飲酒していないケースと比べて処分や刑罰が重くなります。
酒気帯び運転に適用される刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
02.酒酔い運転
酒酔い運転は、酒の影響で正常に運転できないおそれのある状態で運転することです。
呼気中のアルコール量とは無関係で、本人が正常に運転できる状態かどうかによって判定されます。
たとえばまっすぐ歩けず千鳥足になっている、ろれつが回っておらず通常のコミュニケーションをとれないなどの状態になっていたら酒酔い運転と認定される可能性が高くなるでしょう。
酒酔い運転へ与えられる刑事罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑。酒気帯び運転より相当重くなります。
飲酒運転と免許の点数
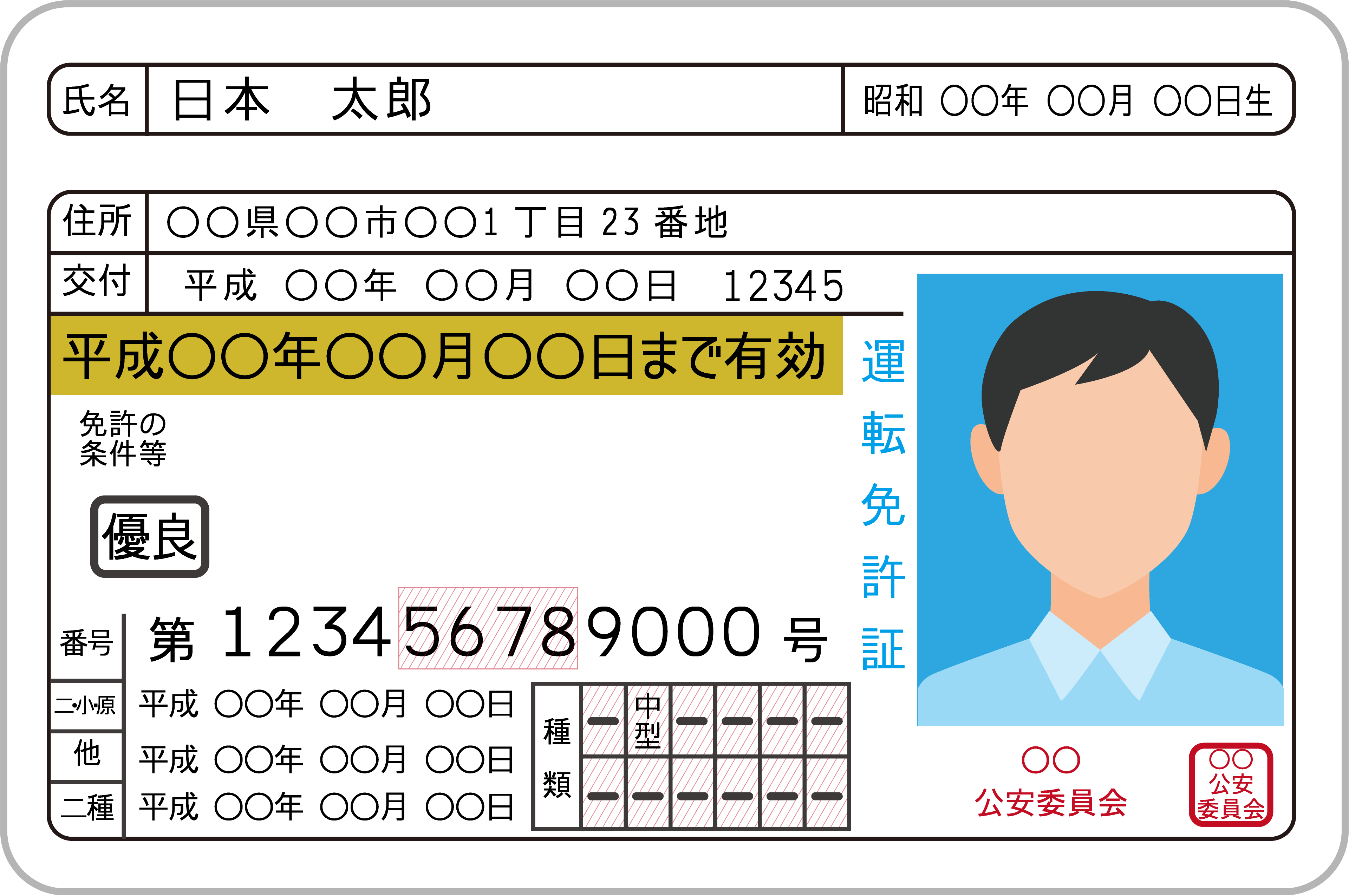
飲酒運転をすると、加害者には免許の点数加算が行われます。
日本の運転免許制度では点数加算方式が採用されており、交通違反や交通事故を起こすと内容に応じて点数が足されます。累積点数が一定に達すると免許が停止されたり取り消されたりする仕組みです。
酒気帯び運転と酒酔い運転で加算される点数が異なるので、みてみましょう。
01.酒気帯び運転の点数
- 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15以上0.25mg未満であれば、13点加算
- 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上であれば25点
酒気帯び運転の場合、呼気中のアルコール濃度によって点数が2段階に設定されています。
比較的少量で13点加算された場合には免許停止90日間となり、多量に飲酒していて25点加算されたら免許取消、欠格期間2年となります。
02.酒酔い運転の点数
- 一律で35点加算
酒酔い運転をすると一気に35点が加算され、免許取消、欠格期間3年となります。

飲酒運転の厳罰化

飲酒運転については厳罰化が進んでいます。刑罰や加算点数が引き上げられているので「たかが飲酒運転」と軽く考えていると重大な処罰や処分を受けてしまう可能性が高いので注意しましょう。
また、ドライバーだけではなく同乗者や車の提供者、酒類の提供者にも処罰規定が設けられています。
以下のような行動は処罰対象とされていますので絶対に行なってはなりません。
- 飲酒したドライバーの車に乗せてもらう
- 相手が酒を飲んでいるとわかっていて車を貸す
- 相手が今後車を運転する予定があるのを知っているのに酒を出す
交通事故の刑事責任

飲酒運転で人身事故を起こした場合に適用されるのは道路交通法違反だけではありません。
自動車運転処罰法にもとづく交通事故の刑事責任も問われます。
交通事故の刑事責任には過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の2種類があります。確認してみましょう。
01.過失運転致死傷罪
前方不注視やスピード違反、ハンドルブレーキ操作不適切などの通常の過失によって人身事故を起こしたときに成立する犯罪です。
刑罰は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金刑です。
02.危険運転致死傷罪
故意とも同視できるような悪質な過失によって人身事故を起こしたときに適用される犯罪です。
刑罰は、被害者がケガをした場合か死亡した場合かで異なります。
- 被害者が死亡せずに済んだ場合には15年以下の懲役刑
- 被害者が死亡すると1年以上20年以下の有期懲役刑
自動車運転処罰法の罪と飲酒運転の罪は併合罪となります。飲酒状態で交通事故を起こすと自動車運転処罰法と道路交通法違反が同時に成立して通常よりも重い刑罰が適用されると考えましょう。
さらに飲酒運転が悪質な場合、危険運転致死傷罪が適用されるリスクも高まります。飲酒状態で車を運転するのは絶対に避けてください。
飲酒事故の加害者はひき逃げするケースが多い

01.ひき逃げしてしまう理由
飲酒運転のドライバーが人身事故を起こした場合、逃げてしまう(ひき逃げしてしまう)ケースが少なくありません。
- 酩酊状態であるために気づかなかった
- 飲酒運転であったことがバレたくないて逃げた
飲酒運転特有の理由としては上記のものが挙げられます。
02.ひき逃げした場合の責任
ひき逃げは、道路交通法違反の重大な犯罪行為です。
道路交通法では交通事故を起こした加害者には被害者への救護義務が課されます(道路交通法72条1項前段)。これを無視して逃げてしまうと救護義務違反となってしまいます。
ひき逃げ(救護義務違反)の刑罰は非常に重く10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科せられます。運転免許の点数も35点加算され一発で免許取消となります。また、飲酒運転の罪と自動車運転処罰法の罪、ひき逃げ(救護義務違反)の罪のすべてが成立するため、非常に重い刑罰が適用されます。
飲酒事故を起こした際は決して逃げてはいけません。


飲酒事故の被害に遭った場合の対処方法

飲酒運転による交通事故に巻き込まれてしまった場合はどのように対応すれば良いのでしょうか?


01.相手の車やバイクの特徴を把握
飲酒運転の加害者は、事故現場から逃げてしまうことが多くあります。事故被害に遭った際は相手の車やバイクの特徴を把握しましょう。
- ナンバー
- 車種、大きさ
- 色
- 傷やステッカーなどの特徴
- 運転者の特徴(背格好、性別、服装、年齢など)
こういった情報をメモしておきましょう。可能であればスマホで写真を撮影しておきましょう。
02.救護を受ける
事故の態様によってはケガを負ってしまうこともあります。自力で無理して立ち上がったりせずに加害者や周囲の人に救護してもらいましょう。必要に応じて救急車を呼んでもらい、病院へ搬送してもらって治療を受けましょう。
03.警察へ報告する

事故の当事者は警察へ報告しなければなりませんが、飲酒運転の加害者の場合は、自分から率先して警察に連絡を取らない可能性があります。このような場合には被害者の立場であっても警察へ通報してください。
警察へ事故を報告しないと交通事故証明書が発行されず、後に被害者が不利益を受けてしまうおそれがあります。
04.病院へ行く
外観上は軽傷で済んでいたとしても事故後は必ず病院へ行きましょう。事故現場では興奮状態になって気づいていなくても後に痛みが出てくるケースも少なくありません。事故直後のMRIが後の後遺障害認定の重要資料となる可能性もあります。
全身を打って骨折やねんざをしたりむちうちになったりしているようであれば整形外科へ行ってください。頭を強く打った場合には脳神経外科へ行くのが良いでしょう。
05.現場で警察を呼ばなかった場合の対処方法
重傷でそのまま救急搬送された場合やひき逃げされてスマホが壊れてしまい通報が出来ずに帰宅した場合など事故現場で警察を呼べないケースも考えられます。
もしも現場で警察を呼べなかったとしても後に警察へ行って被害届を提出しましょう。
被害届は最寄りの警察署でも受け付けてくれますが、できれば交通事故現場を管轄する警察署へ提出するようお勧めします。その方が後の捜査がスムーズに進みやすくなるからです。
被害状況をまとめたメモや証拠の写真などを持参して、警察署へ行き「被害届を提出しに来ました」と伝えましょう。担当部署で手順とおりに被害届を作成して提出すれば事件を受け付けてもらえます。
06.賠償金を請求する
加害者へ損害賠償請求しましょう。治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益、自転車の弁償代などを請求できます。
相手が任意保険会社に入っていれば保険会社と示談交渉を進めましょう。保険に入っていない場合でも自賠責保険へ保険金を請求できます。自賠責で不足する部分については相手方本人に請求すると良いでしょう。

ひき逃げで賠償金を請求できない場合の注意点

ひき逃げされた場合は加害者が不明な状態が続きますので、加害者の保険会社にも加害者本人にも賠償金を請求できません。
そんなときには政府保障事業を利用してください。最低限の自賠責基準によるてん補金というお金を受け取れます。
また、自身の自動車保険で人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に入っているのであれば、自分の保険会社から保険金を受け取れる可能性もあります。
さいごに
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では交通事故に注力しております。飲酒運転絡みの事件の解決実績も多数有しております。
飲酒運転絡みの交通事故に巻き込まれてしまいお困りの方は、是非一度ご相談ください。