交通事故に遭って怪我をした場合、入院や通院、療養が必要になることがあります。
入院や通院、療養を理由に働くことができなかった期間は無給となってしまうので、事故被害者は収入ダウンとなってしまいます。事故被害に遭わなければ収入ダウンにはならなかったといえることから、交通事故被害に遭い休業したことで減収となった方は、休業損害を加害者に請求することができます。
今回の記事では、休業損害とはなにか、休業損害はどのような人に認められるのか、どうやって算出されるのかについて解説します。
休業損害とは
休業損害とは、交通事故被害によって働けなかったことで収入を得られなかった分の損害です。交通事故の加害者に対し請求することができます。

交通事故に遭ってけがをするとしばらく働けなくなります。働くことができなかった期間は無給や減給となり減収が発生しますが、この減収は交通事故被害に遭わなければ発生しなかったと言えますね。
したがって、休業損害は交通事故と因果関係のある損害として加害者に請求することができるのです。

休業損害が認められる要件

すべての交通事故被害者に休業損害が認められるわけではありません。休業損害が認められるのは、事故前に労働をして収入を得ていた人のみです。
例えば、働いていない人(無職の人)については、休んでも減収が発生していないので休業損害は認められません。
01.休業損害が認められる被害者
以下のような方は休業損害を請求することができます。
- サラリーマン
- 契約社員、派遣社員
- 公務員
- 個人事業者
- フリーランス
- アルバイト、パート
- 主婦・主夫(家事労働者)
サラリーマンや契約社員、派遣社員などの給与所得者は、休業損害が認められます。公務員の場合も基本的には休業損害が認められます(病気休暇や休職者制度を利用して減額される可能性あり)。
個人事業者やフリーランスでも収入を立証することができれば休業損害が認められます。
主婦や主夫の方については、現実に誰かからお金をもらっているわけではありませんが、家族のための家事労働に経済的な対価が認められるので休業損害が認められます。
の休業損害の相場、計算方法をパターン別に解説-320x180.jpg)
02.休業損害が認められない被害者
他方で、次のような方には休業損害が認められません。
- 無職の方
- 不動産収入など不労所得で生活している方
- 年金生活の方
無職の方には「仕事を休む」ということが観念できないので休業損害が認められません。
不動産や株式などの不労所得で生活している方も治療で動けないからといって減収が発生するものではないので休業損害は発生しません。年金生活者も同じです。
また無職の方で会っても、近々就職が決まっていて、交通事故被害に遭ったためにその就業することができなくなった場合には、その分の補償を請求することが可能です。
休業損害の計算方法
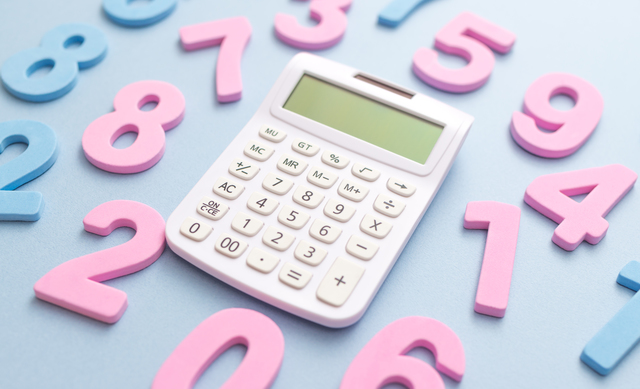
休業損害を計算するときには、基本的に以下のような計算式を使います。
休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
休業損害額を算出する上で確認すべき「基礎収入」「休業日数」について、以下見ていきましょう。
基礎収入とは
(1日当たりの)基礎収入とは、その労働者が1日働いた際に得られる平均的な収入です。基礎収入の算定方法には、自賠責保険の基準と裁判基準の2種類があります。
01.自賠責保険の基準
自賠責保険の基準では、基礎収入は一律で1日6,100円と規定されています。
なお、給与明細書等の客観的資料によって6,100円よりも高額であることを証明することができれば1日あたり19,000円まで上げることが可能です。なお、19,000円が上限であり、仮にこれ以上の収入を得ていることを証明できたとしても19,000円で頭打ちとなります。
また、1日当たりの収入額が6,1000円より低い場合の基礎収入は6,100円となります(6,100円は保障されている)。
02.裁判基準
裁判基準では、実際に働いて得ていた収入を基準に基礎収入を計算します。自賠責保険の基準のような上限(19,000円はありません)。
03.裁判基準で計算する方が有利
2つの基準を比べた場合、裁判基準のほうが有利なものとなります。
高収入を得ている方の場合、自賠責基準だと19,000円で頭打ちとなってしまいます。他方で裁判基準であれば上限がないため、高収入の方でも上限カットされることなく休業損害を請求することが可能となります。
また、主婦や主夫などの家事労働者(現実の収入がない方)の計算においてもかなり変わります。裁判基準の場合、家事労働者の基礎収入については賃金センサスの平均賃金を採用して計算します。家事労働者については全年齢の女性の平均賃金を使用して計算し、その額はおよそ1万円となります。他方で、自賠責基準の場合6,100円(下限値)で計算されてしまうことがほとんどです。10,000円と5,700円を比べればどちらが有利かは一目瞭然ですね。
04.裁判基準で請求するには
保険会社の担当者から提示される示談案は、自賠責基準で計算されていることがほとんどです。そのため、休業損害算定の基礎(基礎収入)において相当の不利益を被ることとなります。
他方で弁護士が示談交渉を行なう場合は裁判基準で計算した金額をもとに交渉・請求済ます。休業損害額の算定に不満がある場合は弁護士に相談しましょう。

休業日数
休業日数は、現実に休業した日数のことです、実際に仕事を休んだ日をカウントします。
サラリーマンなどの給与所得者の場合には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことで休業日数を証明します。
自営業者や主婦の場合、休業日数は自己申告となります。そのため「休業の必要性」が争いになりやすいです。通院した日については「半日は働いたのではないか?」などと言われるケースがありますし自宅療養したと言っても信じてもらえないことがあります。
保険会社から「本当に休業の必要性があったのか」と言われることに備えて、医師に診断書などを書いてもらって休業の必要性を証明できるようにしておきましょう。
休業損害が認められる期間

休業損害が認められるのは、症状が固定するまでの期間です。
症状固定とは、これ以上治療を受けてもけがの状況が改善されなくなった状態です。治療を受けても症状が回復しない、すなわち症状が固定してしまったということで「症状固定」と呼称されます。
症状固定となったらそれ以上治療を施しても効果が得られないので基本的に治療は終了となりますので、症状固定後は休業損害が発生しなくなります。
症状固定後に後遺症が残って働けない場合は、後遺障害の認定を受けて逸失利益(労働能力が低下したことによって発生する減収)を請求することとなります。
事故によって働けなくなった分の減収は、症状固定までは休業損害、症状固定後は逸失利益として請求するものと理解しましょう。
さいごに
正直なところ、保険会社から提示される休業損害額は、専門家である弁護士が算定する金額よりも大幅に下回っていることがほとんどです。
休業損害額が基礎収入と休業日数を掛け合わせた金額であるところ、①基礎収入について裁判基準よりも低額となる自賠責基準を使用する、②休業日数についてもできるだけ日数を減らすようにカウントするため、計算結果が低くなることは自明の理と言えます。
また、自身で保険会社と増額交渉を行なおうとしても、保険会社の方が知識も経験もあることは否めません。情報量が違うわけですから対等な交渉とはならず、適正な増額を達成することは困難と言えるでしょう。
この点、弁護士であれば裁判基準を用いて正当な休業損害の金額を計算し、しっかりとした知識をもって保険会社と交渉を行うことが可能です。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故トラブルにおける保険会社との示談交渉について注力しております。保険会社からの提示内容や計算方法に疑問、不満等がございましたら、お気軽にご相談ください。






















