自身が亡くなった際に、財産をどのように相続させるかは非常に悩ましい問題です。
自身の意思をもって財産を承継させる方法にはいくつか種類があります。その代表的なものとしては遺言書によって相続させる遺言ですが、ほかの手法としては死因贈与があります。
今回の記事では死因贈与について、相続に強い弁護士が解説します。
死因贈与とは
死因贈与は贈与契約の一類型です。死因贈与契約は、「贈与者が死亡したときに、贈与者の財産を受贈者に贈与する」という内容の契約であり、贈与者の死亡により契約の効力が発生し、その効果として受贈者に財産権が移転します。
通常の贈与契約との違い
通常の贈与契約は、贈与者と受贈者との間で「贈与者の財産を受贈者に贈与する」との契約が成立するとその効力が生じ契約が履行されます。なお、通常の贈与のことを死因贈与と対比して生前贈与と呼ぶこともあります。

死因贈与を採用するケース
死因贈与を利用する場面としては、以下のものが想定されます。
- 自分の財産を相続人以外の人に与える
- 財産を与える代わりに一定の条件を付ける(負担付死因贈与)
- 配偶者居住権を設定する

死因贈与と遺贈

死因贈与と混同しがちな制度として遺贈があります。遺贈とは、遺言によって財産を特定の者(受遺者)に無償で譲与することを言います。
この二つの制度のポイントを確認していきましょう。
01.法律行為としては異なる
死因贈与と遺贈は、法律行為の側面からみると大きく性質を異にします。
- 死因贈与=契約
- 遺贈=単独行為
「単独行為」とは、1人の1個の意思表示によって成立する法律行為のことです。相手方の意思に関係なく成立する(表意者の一方的な意思表示で成立する)法律行為であるとお考え下さい。これに対して、「契約」とは当事者同士の意思表示が合致することで成立する法律行為のことです。双方が同意しないと成立しません。
遺贈は単独行為であるため、受遺者(相手方)の意思を問わず成立します。他方で、死因贈与は契約であるため、贈与者と受贈者(相手方)の意思表示の合致があって初めて成立します。受贈者が拒絶すれば死因贈与は成立しないという点に注意が必要です。

02.どちらも撤回が可能

遺言は、遺言者本人が亡くなるまではいつでも何度でも自由に撤回することができますので、遺贈もまた撤回が可能です。また、死因贈与も契約でありながら、遺贈のルールに従うものとされているので(民法第554条)、同じく撤回可能です。
撤回ができないケース
遺贈も死因贈与も撤回ができると述べましたが、負担付死因贈与の場合にはこの限りではありません。
負担付死因贈与とは、贈与する人が亡くなったら特定の財産を相手に譲るが、その代わりに相手は、贈与者が亡くなるまでの間、一定の負担を課せられるという内容の契約です。
負担付死因贈与に基づいて受贈者が負担の全部またはそれに類する程度の履行をしていたのにも関わらず、贈与者がこれを撤回してしまったら負担を履行した受贈者は不利益を被ってしまいますね。
このような不合理を避けるため、負担付死因贈与に限っては、受贈者が負担の全部またはそれに類する程度の履行をした後は、贈与者は死因贈与を撤回できなくなるとされています。
03.どちらも配偶者居住権を設定できる
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属していた建物に相続開始時に居住していた場合に、一定の事由があるときには亡くなるまでその居住建物に無償で居住できる権利を持ちます。この権利を配偶者居住権といいます。
一定の事由というのは、以下の2つの要件を満たす場合です。
- 被相続人が相続開始時において配偶者以外の者とその居住建物を共有していないこと
- 遺産分割(調停、審判)、遺贈、死因贈与によって配偶者居住権を取得するとされたこと
配偶者居住権は、遺贈によっても死因贈与によっても設定可能であり、残された妻(夫)に取得させることができます。

04.どちらも遺留分侵害額請求の対象となる
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている相続割合をいいます。

遺贈や死因贈与の結果として法定相続人の遺留分が侵害された場合は、遺留分に満たない財産しかもらえなかった相続人は、財産を譲り受けた相手方に対して遺留分相当額との差額の支払を求める遺留分侵害額請求をすることが可能です。
優先順位に注意
遺留分侵害者に「遺贈の受遺者」と「死因贈与の受贈者」とがあるときは、受遺者が先に侵害額を支払い、それでも遺留分に不足する場合に受贈者が支払うことになります。この支払義務の順序は、遺贈、死因贈与、生前贈与と定められています。
05.どちらも相続税の対象となる
遺贈で財産を受け取った場合も死因贈与によって財産を受け取った場合も、相続税の対象となります。贈与税ではありません。いずれも被相続人の死亡を原因として権利を取得することから相続税の課税対象となるのです。
相続税ですから、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に相続税申告書を提出し相続税を納付しなければなりません。また、受贈者が配偶者及び一親等の血族でない場合には2割加算があります。
目的財産が不動産の場合には要注意
遺贈や死因贈与によって不動産を譲り受けた場合、受贈者には相続税のほか不動産取得税や登録免許税(所有権移転登記の手数料)も課税されます。

法定相続人が遺贈で不動産をもらう場合、不動産取得税は非課税となりますが、死因贈与では法定相続人であっても課税されてしまいます。また、法定相続人以外が不動産をもらう場合には、遺贈でも死因贈与でも不動産取得税が課税されます。
また、登録免許税の税率についても差が生じます。法定相続人に対する遺贈の登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%ですが、法定相続人以外への遺贈に基づく登記と死因贈与に基づく登記では2.0%となります。
遺贈と死因贈与は共通点が多いですが、財産を譲りたい相手が法定相続人である場合、税負担だけを考慮するなら遺贈のほうが割安になります。

死因贈与を実現させる方法
死因贈与契約の実現させるための方策について確認していきましょう。
01.相手方との合意
先述のとおり死因贈与は契約によって成立しますので、受贈者との合意は必須不可欠です。受贈者に説明し、合意を取り付けましょう。
なお、負担付死因贈与の場合は、贈与者が死亡しただけでは贈与の効果は発生しません。契約で定めた一定の負担を受贈者が履行することが必要となります。
02.公正証書の作成
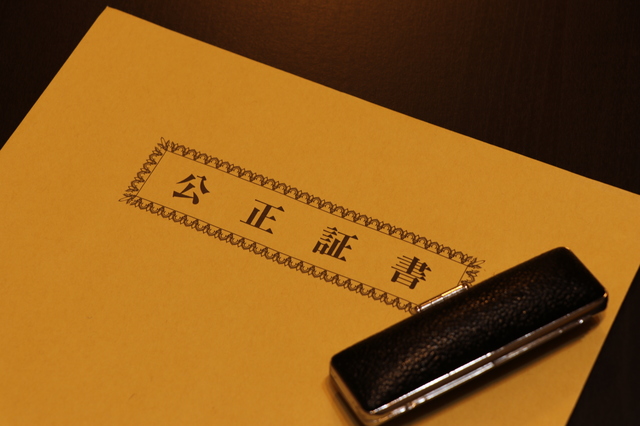
死因贈与は口頭による合意だけでも成立しますが、口頭の合意だけだと証拠がないことから後にトラブルが発生することが想定されます。トラブルに備えて契約書を作成しておくことが有益です。
また、公正証書として契約書を残しておくと、契約の存在と内容が一層強固なものとなります。記載内容次第では後述の仮登記や本登記が容易となりますので、死因贈与の合意内容は公正証書として残しておきましょう。
03.不動産の場合は仮登記をしておく
不動産を死因贈与の対象とする場合には、生前に仮登記(始期付所有権移転仮登記(始期贈与者死亡))をつけておくと良いでしょう。仮登記とは、登記の優先順位をあらかじめ保全するために行う登記です。
贈与者が心変わりして目的物を他に譲渡した場合は、前述のとおり撤回になりますが、仮登記を付けておくと受贈者の権利を保全することができます。遺贈の場合には仮登記することはできませんから、受遺者が権利を保全することは問題になりません。
仮登記手続は贈与者と受贈者の共同申請となります。もっとも、死因贈与契約を公正証書で作成し、その中で「贈与者は受贈者のために仮登記をなすものとし、受贈者が仮登記手続を申請することを承諾した」旨の文言を記載しておくと、受贈者が単独で申請することが可能になります。
04.執行者の指定
受贈者は、将来贈与者が亡くなって死因贈与の効果が発生したときに本登記をすることで、第三者に対して所有権取得を主張することができます。この本登記手続は、受贈者と相続人全員とが共同で申請を行うことになります。
もっとも、死因贈与契約を公正証書で作成し、その中で執行者を指定しておくと、受贈者と執行者の共同申請となります。さらに受贈者は執行者を兼ねることができるので、その場合には受贈者兼執行者として単独で本登記手続きを行うことができます。
さいごに
遺産相続においては、生前贈与、遺言、遺贈、死因贈与といった様々な選択肢があります。それぞれについてメリット・デメリットがありますので、ご自分の意思や相続する側の利害、財産の種類等を考慮してもっとも適切な方法を選択すべきといえます。
この点について最善策を取るためには、弁護士や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、相続問題に注力しており、相続に関する疑問や質問、財産や相続人の利害関係を踏まえての相続対策の提案まで広く受け付けております。相続についてお悩みの方は是非一度お気軽にご相談ください。





















