公務員は、国や地方自治体のもとで公共の利益のために働いております。
その公務員が盗撮や痴漢、万引き(窃盗)などの刑事事件を起こしてしまった場合、無条件で免職となってしまうのでしょうか?
今回の記事では、公務員が刑事事件を起こした場合のリスク、被る不利益を最小限にとどめるための対処方法を解説します。
典型的な犯罪
公務員であっても気の迷いや酔った勢い等により以下のような犯罪を犯してしまう可能性があります。
- 暴行
- 傷害
- 器物損壊
- 窃盗(万引き)
- 痴漢
- わいせつ行為
- 児童買春(18歳未満との援助交際)
公務員が上記のような犯罪で逮捕され立件されてしまった場合、内容や状況によっては職を解かれる可能性があります。
以下、状況別にみてみましょう。

逮捕された場合

「公務員は逮捕されると失職する」とお考えになっている方が多くいらっしゃいますが、逮捕されただけでは公務員の職を解かれることはありません。
逮捕された段階ではあくまで被疑者にすぎません。罪を犯したとは確定していないからです。
国家公務員法や地方公務員法においても『逮捕されたら懲戒や免職となる』と規定されてはおりません。

起訴された場合

01.起訴では失職しない
起訴された段階でも公務員として免職されることはありません。起訴段階では罪を犯したとは確定していないからです。
02.起訴休職処分が下されることがある
逮捕された公務員が起訴された場合、所属の官公庁から起訴休職という処分が下される可能性があります。起訴休職とは、起訴された公務員について仕事をさせずに休ませる制度です。
起訴休職は、国家公務員、地方公務員を問わず適用されます。また、身柄事件(被疑者が身体を拘束されたうえで取り調べを受ける事件)の場合だけではなく在宅事件(捜査上必要なときに捜査機関にて取り調べを受ける事件)になったときにも起訴休職処分が行われます。
起訴休職による休職期間は起訴されてから判決が確定する日までとされています。また、起訴休職中も給料が支払われますが通常の60%程度に減額されます。
03.略式起訴の場合は起訴休職処分とはならない
略式起訴となった場合には起訴休職処分は行われません。
略式起訴とは、書類上のみで審理する刑事裁判手続きです。100万円以下の罰金刑や科料の刑が適用されるケースで、本人が罪を認め略式起訴に同意していれば、略式起訴となる可能性が可能性があります。
略式起訴の場合は、自宅宛てに起訴状や罰金の納付書が届きます。罰金の支払いをすれば刑罰は終了したこととなります。
なお、略式起訴であっても有罪には変わりありませんので前科がつくこととなります。

有罪判決が出た場合

刑事裁判において有罪の判決が出た場合には、公務員はその職を解かれる可能性があります。
01.刑罰の種類
日本の刑罰は、下記の6種類に分けられます。数字が小さいほど重い刑罰となります。
- 死刑:生命を奪う刑罰
- 懲役:刑務所に拘置され刑務作業を強制される刑罰
- 禁錮:刑務所に拘置される刑罰
- 拘留:拘留所に最長29日まで拘置される刑罰
- 罰金:1万円以上の金額を国庫に納付させる刑罰
- 科料:1万円未満の金額を国庫に納付させる刑罰
02.公務員の職に就くための要件
公務員の職につくには一定の資格要件を満たさねばなりません。在職中であっても資格要件を満たしておく必要があり、要件を満たさなくなった時点で当然に失職します。不服申立てをすることもできません。
03.禁固刑以上の場合
国家公務員法においても地方公務員法においても「禁錮刑以上の刑に処せられた」ことが欠格事由と定められております。そのため、公務員に禁錮刑(③)や懲役刑(②)、死刑(①)が下されれば、当然にその資格を喪失し免職されることとなります(以下、「当然失職」という)。
実刑となった場合、刑期が終了するまでは公務員になることはできません。執行猶予付き判決が出た場合であっても執行猶予期間が終了するまでの間は資格は喪失したままとなります。
なお、地方公務員の場合は当然失職を免れることができる可能性があります。というのも都道府県によって失職要件が異なることがあるからです。
たとえば東京都の場合「過失かつ執行猶予付き判決」であれば公務員の資格を失いません。従って、東京都の職員が人身事故を起こしたとして、罪状が過失運転致傷罪及び器物損壊罪、執行猶予付き判決を得られた場合には失職を免れる可能性があります。
」で成立する犯罪とは?逮捕された時の対処方法-320x180.jpg)
04.拘留未満の刑罰の場合
「禁錮刑以上の刑に処せられた」ことが欠格事由となることから、逆の「拘留以下の刑に処せられた」場合については欠格事由に該当しません。すなわち公務員に拘留(④)や罰金(⑤)、科料(⑥)が下されたとしても、当然失職の要件を満たさないので公務員としての資格を失うことは無いのです。
なお、欠格事由を満たさないケースであっても後述する懲戒処分によって免職される可能性は否めません。

禁錮刑や懲役刑になる犯罪
下記の犯罪を犯した場合、禁錮刑や懲役刑が下される可能性があります。すなわち当然失職となる可能性があるということです。
- 盗撮
- 痴漢
- 窃盗
- 暴行・傷害
- 名誉毀損
- 器物損壊
- 人身事故
- 強制わいせつ
なお、上記の犯罪の中には罰金刑が存在するものが多数含まれています。たとえば盗撮や痴漢、窃盗、名誉毀損、交通事故などは罰金刑が選択される可能性のある犯罪類型です。
このような犯罪で逮捕されたケースで当然失職を避けたいのであれば罰金刑となるように動く必要があります。
懲戒処分による免職
当然失職とはならなくとも、懲戒処分によって免職される可能性があります。
懲戒処分とは、非行のある公務員に罰を与える制度です。非行の内容や程度に応じて以下の4つの処分から選択されます。
- 戒告
- 減給
- 停職
- 免職
01.戒告
戒告は、将来を戒めるために行なわれる厳重注意のことです。懲戒処分の中ではもっとも軽い類型です。給料や職務内容等に対する実際の影響はありません。
02.減給
減給は、一定期間基本給が減額される処分です。
03.停職
停職は、一定期間の出勤停止が課される処分です。停職期間中は仕事をすることができず給与の支給もなされません。
04.免職(懲戒免職)
免職(懲戒免職)は、職を解かれる処分です。懲戒処分の中ではもっとも重いものとなります。
先に説明した公務員としての資格欠格事由をみたさない場合であっても、懲戒処分で免職とされてしまえば職を失うこととなります。
懲戒免職になりやすい犯罪類型としては、以下のものが挙げられます。
- 公文書偽造、変造、虚偽公文書作成
- 談合への関与
- 強制わいせつ罪(セクハラなど)
- 公金横領
- 詐欺・窃盗・恐喝
- 放火・殺人・強盗などの重大犯罪
- 淫行
- 薬物犯罪
- 飲酒運転(事故を起こさなくても免職の可能性があります)
- 飲酒運転で人身事故
- 飲酒運転の同乗
- 飲酒運転で事故を起こしひき逃げ
他方で、暴行や傷害、遺失物横領や賭博、通常の人身事故などの犯罪であれば、懲戒免職までには至らないケースが多いといえます。
逮捕された公務員が職を失うケース
上記の内容をまとめましょう。犯罪を犯した公務員が職を失うケースは、以下の2パターンです。
- 刑事裁判で有罪判決となり懲役刑または禁錮刑が科された場合(当然失職)
- 懲戒処分として免職処分が行われた場合(懲戒免職)

逮捕された事実は職場に知られてしまうのか

公務員においては、犯罪を犯した事実が職場に知られてしまうと懲戒処分が行われるリスクが高まります。それでは、どのようなケースで職場に犯罪行為を犯した事実が知られてしまうのでしょうか?
01.職務と関係する犯罪の場合
収賄罪、公金横領、虚偽公文書作成罪といった職務に関係する犯罪であれば職場に知られてしまうことがほとんどでしょう。
職場での度を超えたセクハラ行為について同僚や部下から強制わいせつ罪で訴えられたケースでも職場に知られてしまうといえます。
02.逮捕勾留された場合
痴漢や盗撮、交通事故などのような私的な犯罪であれば、その事件が報道されない限りは職場の人間が知る由はありません。とはいえ逮捕後の身柄拘束が長引いてしまった場合は、長期に渡って出勤できなくなりますので、長期欠勤の理由を説明しっかりと行なう必要があります。うまく弁解弁明できないようであれば刑事事件で逮捕勾留されていることを知られてしまうのはやむをえないでしょう。
03.マスコミ報道された場合
公務員が逮捕された場合、一般人が逮捕された場合よりもマスコミ報道される可能性が高いといえます。テレビのニュースで報じられてしまった場合は職場バレは避けられないでしょう。
04.職場に知られにくいケース
以下のようなケースでは職場に知られにくいといえるでしょう。
- プライベートな犯罪だった
- 在宅捜査となった
- マスコミ報道が一切なされなかった
- 早期に示談が成立し不起訴になった
万引きや暴行、盗撮などで逮捕されたとしても、すぐに被害者と示談を成立させ早期に身柄を解放してもらい、不起訴を獲得することができれば職場に知られず穏便に解決できる可能性が高くなります。
不起訴となれば前科もつきませんし、もちろん職を失う危険も発生しません。

失職しても再度公務員になれる?
当然失職や懲戒免職によって職を解かれた公務員が、再度公務員になることはできるのでしょうか?
再度公務員になること自体は、制度上は可能です。禁錮刑や懲役刑を科せられても、執行猶予期間の満了、刑の執行の終了によって公務員になる資格を取り戻すことができるからです。
しかし、公務員になるには国や自治体に採用されなければなりません。
再就職ということであれば年齢は高いでしょうし、前科が付けられている、免職された経緯があるわけですから採用されるのは困難といえます。
再度公務員になることは制度上不可能ではありませんが、非常に難しいものであることには違いありません。

逮捕された場合の対処方法
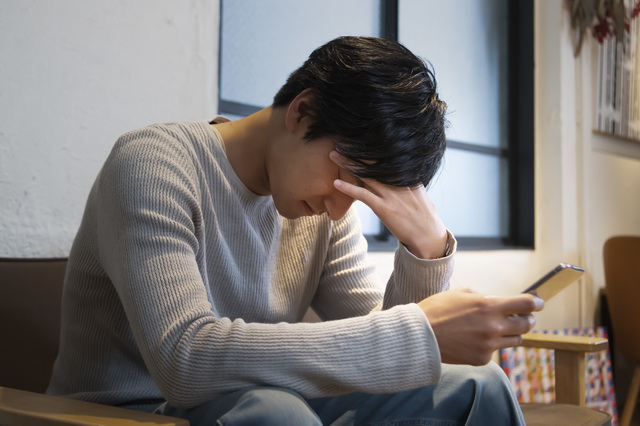
公務員が刑事事件を犯してしまったら、どのように対応すればよいのでしょうか?
01.被害者がいる犯罪
被害者がいる犯罪であれば一刻も早く示談を成立させましょう。
示談を成立させることができれば非常に良い情状として斟酌してもらえるからです。逮捕前であれば逮捕される可能性が低くなりますので、職場に知られたり懲戒されたりするリスクも大きく低下します。
また、逮捕された後であっても被害者との示談を成立させることができれば、検察官が不起訴にしてくれる可能性が高まります。不起訴処分になれば有罪判決は出ないので、資格喪失による当然失職となるリスクはありません。前科がつかないので懲戒免職される可能性も低くなるでしょう。
02.被害者のいない犯罪
被害者のいない犯罪で逮捕された場合はできるだけ早期の身柄開放を目指すべきです。
家族に身元引受書を書いてもらい、本人が普段真面目に働いている公務員であって逃亡や証拠隠滅のおそれもないことを示すことで勾留請求しないようにはたらきかけましょう。勾留されなければこれまで通り出勤できるので、職場に犯罪を知られる可能性が低下します。
次いで不起訴を目指して活動しましょう。不起訴になれば前科はつかないので当然失職の可能性がなくなるからです。
不起訴処分にしてもらうには被疑者にとって良い情状を示さねばなりません。反省文を書いたり普段はまじめにはたらいていること、初犯であり再犯可能性が極めて低いことなどを示すことで検察官へ説得的にはたらきかけましょう。
03.職場への対応
職場への対応についても考えておかねばなりません。特に勾留請求されて身柄拘束が長く続いてしまう場合には、職場への説明方法に工夫が必要です。事件を知られないのがベストなのですが、知られるとしても予断や偏見を与えないようにしなければなりません。
弁護士に刑事弁護を依頼しよう
公務員が刑事事件の被疑者となってしまったら、早期に弁護士に依頼して刑事弁護人を選任するようお勧めします。できれば「逮捕前」に相談しましょう。
01.逮捕前に依頼する
痴漢や援助交際など被害者がいるケースでは、逮捕前に弁護士に依頼しておけば弁護士が代理人として被害者と示談交渉してくれます。示談を成立させることができれば逮捕を避けやすくなるでしょう。
また、弁護士が間に入れば被害者側も冷静に対処することができます。当事者同士だと感情的になったり犯罪行為への恐怖心から示談を拒絶される可能性が高いという点も弁護士に依頼するメリットの一つと言えます。
また、示談を成立させることによって被害届や刑事告訴状を提出される危険はなくなりますし、一切口外しないという約束をして職場に知られず穏便に解決することも可能となります。
02.逮捕後に依頼する
逮捕後だと、身体拘束されて動けなくなってしまうことが多いため、なおさら弁護士に依頼する必要性が高まります。何もせずに放っておくと起訴されて有罪判決が出てしまう可能性があるので早期に刑事弁護人を選任しましょう。
被害者のいない犯罪であっても、弁護士に弁護を依頼すれば本人にとって良い情状を集めて検察官へ勾留請求しないように申し入れたり不起訴にするよう意見書を提出してくれます。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、刑事弁護に注力しております。盗撮や痴漢、暴行などの犯罪行為をしてしまった方、犯罪行為により逮捕されてしまった方はお早めにご相談ください。






















