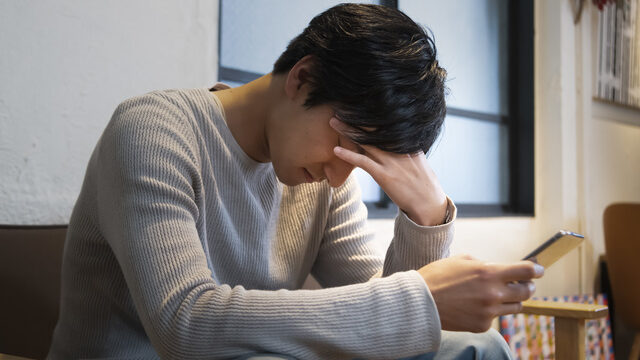膨れ上がった借金やリボ債務等を清算する方法として破産手続きがあります。
裁判所に破産手続きを申し立て、免責を得ることができれば借金(債務)を支払う義務を免れることができますが、一定以上の財産を保有している場合は、その財産を換価処分して債権者への配当原資に充てなければなりません。
それではどのような財産が換価処分の対象となって、どのような財産が換価処分の対象とならないのでしょうか?
今回の記事では、破産手続きに関し、破産しようとしている人が持っていることができる財産(自由財産)、換価配当に回さなければならない財産について解説します。
破産手続とは?
皆様は、破産手続きをどのようなものとお考えでしょうか?
大多数の方は、『借金やローンに苦しんでいる人が取りうる手段であり、自身の負っている借金や負債を無くす(チャラにする)手続き』とお考えかもしません。
ですが、上記の内容はこと自己破産において破産者個人に付与される「免責」という効果(借金を支払う責任を免除される効果)に着目したものであり、破産手続きの内容としては適切ではありません。
では、破産手続きとは何なのでしょうか?

破産とは破産者が有する財産を換価処分する手続

破産手続をかみ砕いて説明をすると、「破産者(破産しようとしている人)が有する財産を換価・処分して、債権者に平等に配当する一連の手続き」です。
ここでいう『破産者が有する財産』が何を指すかというと、その人に属する金銭や財物(所持品)、他者に貸し付けている金員等の債権の一切です。
これには預金残高のみならずお財布に入っているお札や小銭、自宅にある家具家電はもちろん着用している洋服や肌着等もすべて含まれます。
金や物品だけではなく、例えば「他人に貸し付けたお金」や「将来受け取ることができるであろう退職金(の所定の割合)」「保険の解約返戻金」といったものも財産に含まれます。

自由財産とは

『持っているすべての財産を換価処分の対象とする』を文言通り徹底してしまうと、破産しようとする個人には自分の身体以外は何も手元に残らないいわゆる「素寒貧」の状態となってしまいます。
そのような状況ではその後の生活をまともに送ることは不可能であることは容易に想像できますし、そのような事態に陥るのであれば誰しもが破産申立を行おうとは考えなくなってしまいます。
この不合理を解消するために「自由財産」という考え方が出てきます。
自由財産とは『破産者の財産のうち破産財団に属さない財産』と定義されております。なじみのない言葉で説明がなされているため、何を示しているのかよくわかりませんね。
自由財産をかみ砕いて説明すると『破産手続きにおいて、換価処分の対象とはしない財産』すなわち『換価処分せずに持っていることができる財産』となります。
先ほど、破産手続を「破産者が有する一切の財産を換価・処分して債権者に平等に配当する手続き」と説明しましたが、自由財産と認められた財産については換価処分せずに所有を継続することができるということです。
それではどのような財産が自由財産として認められるのでしょうか?
自由財産として認められる財産
法律上認められているものは下記のとおりです。
- 新得財産
- 差押禁止財産
- 99万円以下の現金
- 裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産
- 破産管財人によって財団債権から放棄された財産
01.新得財産
新得財産とは、破産手続きの開始決定が出たあとに新たに取得した財産のことです。
開始決定のタイミングで破産者が有する財産とその価値を確定させるので、開始決定以後に新たに取得した財産は自由財産となります。
02.差押禁止財産
差押禁止財産とは、法律上差押えが禁止されている財産のことです。生活に必須な衣類や家具家電、備蓄食料などの動産、年金の受給権等の債権が挙げられます。
なお、衣類や家具家電等の動産について、必要以上に高価である場合は自由財産と認められず換価処分の対象となることがあります。
03.99万円以下の現金
これはイメージしやすいかと思います。なお、ここでいう現金には預貯金は含まれません。
04.裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産
これは、上記01~03で規定される本来的自由財産では破産者の保護が不十分と認める場合において、裁判所が特別に自由財産の枠を拡張するものです。各々の破産者の事情を勘案したうえで特別に認められるものであり無制限に認められるものではありません。
例えば高齢の方の保険解約返戻金等がこれにあたります。
05.破産管財人によって財団債権から放棄された財産
財産の換価処分権限を有する破産管財人が換価困難としてこの財産は換価処分の対象から外します(放棄します)と決定した財産も換価処分の対象とはなりません。
例えば、知人に貸し付けた5万円を未回収のまま破産申立をした場合、破産者は知人に対し5万円の債権を有することとなります。本来であれば知人から5万円を回収して配当財源に回さなければならないのですが、現在音信不通で、弁護士権限(破産管財人権限)で調査しても連絡先も住所もわからないとなった場合はそもそも回収することが困難です。
このような場合、破産管財人は当該債権を換価処分の対象から外すと決定することがあります。
01~03までの財産が本来的な意味での自由財産で、04及び05は自由財産の枠を拡張して特別に認められるものです。

自由財産の拡張が認められる財産

01.東京地方裁判所の場合
東京地方裁判所においては、原則として、下記の財産に関しては自由財産の拡張が認められております。自由財産として扱われるわけですから換価処分の対象にはならないということです。
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
- 処分見込価額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を越える退職金債権の8分の7相当
- 家財道具
裏を返せば、前章の01~05及び上述の財産に該当しない財産については、自由財産とはなりません。そのため破産手続きにおいて換価処分の対象となります。「残高が20万円を超過する預貯金」「就業先で積み立てている積立金」「不動産」等は換価処分の対象となるのでご注意ください。
02.東京地方裁判所以外の裁判所の場合
東京地方裁判所以外の地裁においての自由財産の拡張の判断指針は、地裁によってまちまちです。
「東京地裁の運用に準ずる」という地裁もあれば、「現金を含めて総枠(総額)で99万円までは自由財産としてみなす」とする地裁もあったりと、地方裁判所によって異なります。
自由財産の範囲については、依頼する弁護士にしっかりと確認することをお勧めいたします。
さいごに
今回の記事では、破産手続において換価処分の対象とすることなく手元に残すことのできる財産(自由財産)について大まかに説明いたしました。
この記事をお読みになられている方の多くは、負債や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えていらっしゃるかと思います。東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、借金問題の解決に注力しております。自己破産の申立経験も豊富です。
債務や負債に関するトラブルをお抱えになっている方はお早めにご相談ください。



、DV離婚.jpg)