家賃の支払がない、貸付金に対する返済がなされないといった債務者による債務の不履行があった場合、保証人がいるのであれば保証人に請求することができます。
ところが、事情や状況によっては保証人に請求しても支払を拒否されるケースがあります。これは法律において保証人が支払拒否をすることができる場合が定められているためです。
今回の記事では滞納家賃や貸付金などの債務の支払いを保証人に請求したときに拒絶される理由や請求の手順、注意点を弁護士が解説します。
用語の確認
まずは法律用語を確認しておきましょう。
01.債務者(主債務者)
債務者とは、債務を負担する本人のことをいいます。例えば以下のような人たちです。
- ある人からお金を借りたことで、これを返済する義務を負う人
- ある人からアパートを借り、この賃料を支払う義務を負う人
02.債権者
債権者とは、債務者に対し一定の給付を請求できる権利を有する人のことです。例えば以下のような人たちです。
- ある人にお金を貸し、その人からお金を返してもらう権利を有する人
- ある人にアパートを貸し、その人から賃料を支払ってもらう権利を有する人
03.保証人
保証人とは、債務者による債務の履行を保証する人のことです。債務者が「お金を返す」「賃料を支払う」といった債務の履行をしない場合には保証人が債務の履行を果たす義務を負うこととなります。
なお、保証人は、保証人と連帯保証人とに分類されます。


保証人の言い分
保証人に請求した際に、保証人が主張してくる支払を拒否する言い分(弁明)をみてみましょう。
01.自分も主債務者と連絡が取れなくて困っている
「自分としても主債務者と連絡を取れないので困っている」と主張してくることがあります。
保証人が主債務者と連絡をとれているかどうかは債権回収、保証人の義務には全く関係がありません。主債務者との連絡が取れないことが支払い拒否の理由にはなりませんので、保証債務の履行を請求することが可能です。
02.勝手に保証人にされた
「知らないうちに勝手に保証人にされたから払う必要がない」と弁明する方も多くいらっしゃいます。自分は契約書に署名押印していないのに主債務者が勝手に印鑑を持ち出して署名押印したんだなどと主張してきます。
保証人の言い分が本当であれば、保証契約は無効となり保証人に対して請求ができないこととなりますが、これを疎明するのは非常に難しいです。事実関係を判断するには訴訟手続きを経る必要があるでしょう。また、印鑑を持ち出されたことについて保証人に過失があるようであれば請求できる場合もあります。
また、保証人の言い分が嘘である可能性もあります。
無効の立証は保証人側がすべきものであり、当事者の話し合いだけでは保証契約の有効・無効について決着をつけることは困難です。債権者側としては請求を続けてしまって問題ないでしょう。
03.お金がない

「お金がないから支払えない」と主張してくる方も多くいらっしゃいます。ですが「支払うお金がない」という事実は債権回収、保証人の義務には全く関係がありませんので、保証債務の履行を請求することが可能です。
04.先に主債務者へ請求してほしい
「先に主債務者へ請求してほしい」「主債務者に請求したのか」といわれることもあります。
実は、主債務者に先に請求をしていない場合、保証人には請求できないことがあります(催告の抗弁権)。この点については後述します。

保証人に認められる抗弁権

抗弁権とは請求を拒むことができる権利のことです。
保証人にはいくつかの抗弁権が認められており、事情によっては債権者からの保証債務の履行を拒むことができます。
以下、保証人に認められている抗弁権について確認していきましょう。
01.催告の抗弁権
1つ目は催告の抗弁権です。これは「先に主債務者へ請求してほしい」と主張できる権利です。
たとえば家賃を滞納されたとき、借主本人には請求せずにいきなり保証人に請求すると「先に借主本人に請求してください」といわれることがあります。この場合、先に借主へ請求しない限り保証人に請求することはできません。
02.検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、「先に主債務者の財産から強制執行してください」と主張する権利です。主債務者に資力があるにもかかわらず保証人に請求した場合は、検索の抗弁権を主張されてしまう可能性があります。
たとえば保証人に請求したときに「主債務者の○さんは自宅不動産を所有しているので、そちらを競売にかけてください」などと主張されることがあります。この場合、主債務者の有する不動産について不動産競売を申し立てなければならないこととなります。
なお、検索の抗弁権が認められるためには、保証人が「主債務者に資力がある事実」を証明する必要があります。先の例で言えば、主債務者が自宅不動産を持っていることを保証人が証明する必要があります。
03.分別の利益
保証人には「分別の利益」があります。分別の利益とは複数の保証人がいるときに一人ひとりの負担割合が分割されることです。1人の保証人には負担割合を限度としてしか請求できません。
たとえば100万円の負債を4人が保証する場合一人ひとりの負担割合は25万円ずつとなります。
保証人が複数いる場合でその一人に保証債務の履行を請求した際、その保証人から「私の負担部分は25万円なので25万円までしか支払いません」と主張され、残りの75万円については支払拒否されることがあります。
連帯保証人には抗弁権がない
保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」があり、「分別の利益」を主張することで負担部分を超える支払を拒否する権利も認められています。
他方で、連帯保証人の場合には上記のような抗弁権は認められません。
連帯保証人の場合、主債務者に請求せずにいきなり支払いを請求してもかまいませんし、主債務者に資力があっても連帯保証人に請求できます。
さらに連帯保証人には分別の利益もありません。何人連帯保証人や保証人がいても、一人ひとりの連帯保証人が全額の支払い義務を負います。
日本の取引社会において保証人をつける場合、そのほとんどは連帯保証人です。賃貸借契約、事業用ローンの契約、住宅ローン契約など契約において要求する保証人はほとんどが連帯保証人です。
保証人に履行を請求する際にやってはいけないこと
保証人や連帯保証人に債務の履行を請求する際、以下のような方法をとらないように注意しましょう。
01.脅迫
思い通りに債務を支払われないからといって、相手を脅迫してはなりません。
たとえば「支払わなかったら家族に危害を加える」などといったり間接的にほのめかしたりすると、脅迫罪が成立する可能性があります。
02.頻繁すぎる督促、非常識な時間帯における督促
短時間の間に何度も電話をかけたり、深夜早朝に電話をかけ続けたりして、非常識な督促行為をするとトラブルになる可能性が高まります。相手の態度を硬化させる要因にもなるので控えるようにしましょう。
03.保証人の勤務先に押しかける
保証人が支払わないからといって勤務先に押しかけてはなりません。業務妨害や名誉毀損罪が成立してしまう可能性があります。
04.保証人の家族へ督促
支払い義務のない人に対し督促してはなりません。たとえば保証人の家族に「家族なんだから支払え」というとトラブルに発展してしまいます。
05.張り紙をする、ネットに投稿する
保証人の自宅近くに「金返せ」などの張り紙をしたり、ネット上に「○○は支払いを滞納している泥棒野郎」などと書き込むと名誉毀損になってしまう可能性があります。周囲に滞納の事実を知らせてプレッシャーをかけようとすると違法行為となるリスクが高いので控えましょう。

保証人へ支払請求する手順
保証人へ債権の支払を請求する場合は、以下のような手順で進めるのが一般的です。
01.内容証明郵便で督促
まずは内容証明郵便をで保証人へ負債の支払いを督促しましょう。
内容証明郵便を使うと、郵便局と差出人の手元に相手に送ったものと同じ内容の控えが残ります。確実に請求した資料となるので、将来訴訟になったときにも証拠提出できます。また相手にプレッシャーを与えられるので、任意の支払を受けやすくなるメリットもあります。
02.交渉、合意書の作成
次に相手と交渉し、いくらをいつまでに支払うのか取り決めましょう。合意ができたら必ず「保証債務支払に関する合意書」を作成してください。
特に分割払いにする場合には、合意書を「公正証書」にするようお勧めします。公正証書があれば、保証人が将来支払を滞納したときにすぐに保証人自身の給料や預金、不動産などを差し押さえて債権回収できるからです。
03.訴訟
保証人が支払に応じない場合や話し合っても条件面で合意できない場合などには、訴訟を提起して債務の支払いを求めましょう。
ただし保証人に合理的な拒絶理由がある場合、訴訟をしても勝てない可能性があります。たとえば「時効が成立している」などと主張している場合、安易に訴訟提起せず相手の言い分に理由があるかどうか慎重に判断すべきでしょう。
相手の言い分に理由がなければ、裁判所が支払い命令の判決を出してくれます。
について-320x180.jpg)
さいごに
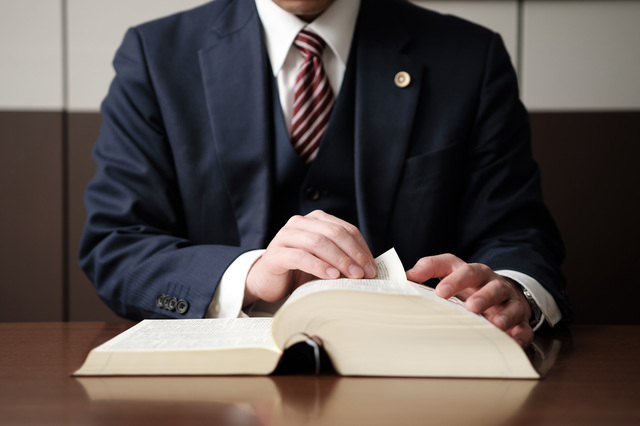
保証人や連帯保証人から確実に債権回収するには弁護士に依頼する方法が効果的です。
弁護士が代理で請求すれば相手に強いプレッシャーをかけて支払に応じさせやすくなります。相手が抗弁を主張してきても、法律的な理由があるかどうかの見極めができて、スムーズに請求を進められるでしょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、家賃や売掛金、貸金などの債権回収業に積極的に取り組んでいます。不良債権の回収でお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。



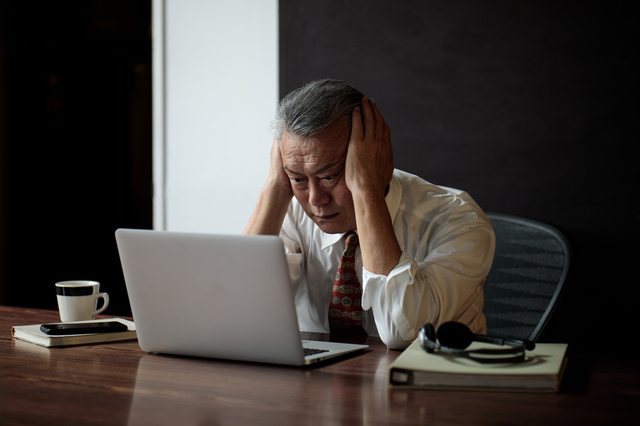
-640x360.jpg)

について-640x360.jpg)















