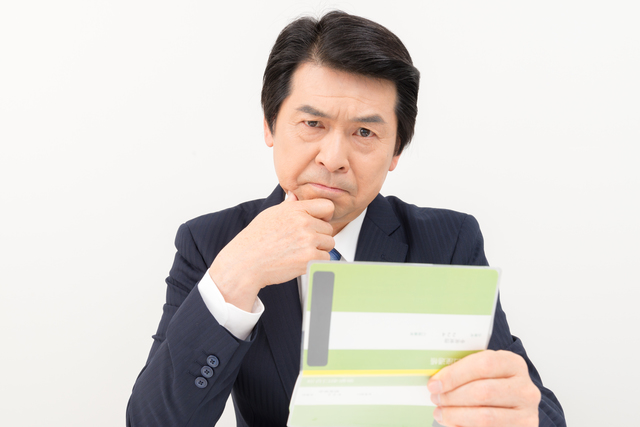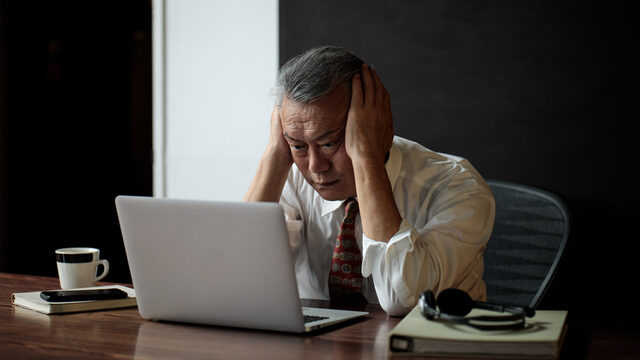取引先が債権を支払わないようであれば積極的に取立てを行なわなければなりませんが、あらゆる手段を尽くしても債権回収できないケースはあります。
そんなときは貸倒損失として税務上の損金算入をしましょう。
今回の記事では債権回収できない場合の対処方法や貸倒損失として計上できる要件、注意すべきポイントについて解説します。
債権回収できないときの対処方法一覧

取引先が不払いを起こし債権回収が難しくなってしまったら、以下のような方法を試してみてください。
| 債権回収方法 | 特徴、方法 |
| 内容証明郵便で督促 | 内容証明郵便で相手方に債権の支払請求の通知書を送付する方法。法的な強制力はないが、相手にプレッシャーを与えられる。 |
| 公正証書で支払を約束する | 相手と支払について合意ができたら公正証書を作成する。公証役場で作成可能。強制執行認諾文言をつけておけば、相手が約束を守らないときにすぐに強制執行(差押え)ができる。 |
| 相殺 | 相手に対して債務を負担している場合、相殺すれば事実上債権回収できる。 |
| 債権譲渡 | 相手の第三債務者に対する債権を当方へ譲渡させる。万一の際にはこちらが直接第三債務者へ取立てを行うことにより債権回収できる。 |
| 商品引上げ | 相手に納入した商品があれば、引き上げることができる。ただし、引上げには相手の同意が必要。同意なしに引き上げると窃盗罪が成立するので要注意。 |
| 債券回収会社へ委託 | 債権回収会社へ債権譲渡したり、回収を委託したりする方法。ただし、委託できる債権の種類は限定されており、手数料もかかる。 |
| 弁護士に依頼 | 債権の取立てを弁護士に依頼する方法。弁護士が相手に内容証明郵便を送って交渉したり、仮差押えや訴訟などの法的手続を利用したりして回収を進める。 |
| 調停申立 | 裁判所で調停を申し立てる方法。調停委員を介して話し合うことが可能。ただし、強制力がないので、相手が合意しなければ解決できない。 |
| ADRの利用 | 交通事故、労働、建築など各分野で「裁判外の紛争解決機関(ADR)」を利用できるケースがある。話合い(調停)だけではなく「仲裁」を利用できるADRでは、最終的な支払条件を決定してもらえる可能性もある。 |
| 仮差押えを申し立てる | 裁判所へ申し立てて相手の資産や債権を仮に差し押さえる決定を出してもらう。仮差押えをすると、相手はその資産を動かせなくなる。相手が仮差押えの解除を求めて任意に支払を提案してくるケースもある。 |
| 支払督促 | 裁判所で支払督促を申し立てる方法。相手が異議を述べない場合、仮執行宣言を得て差押えができる可能性がある。 |
| 訴訟提起 | 他の手段ではどうしても解決できない場合、訴訟を提起し、裁判所から支払い命令を出してもらう。相手が判決に従わない場合には差押え(強制執行)による回収が可能。 |
| 強制執行 | 裁判所に申立てをして相手の資産や債権を差し押さえて債権回収する方法。公正証書や判決書、調停調書などの「債務名義」が必要となる。 |
これらの手法は、難易度や効果、費用、要する時間が異なりますので、状況に応じて適切な方法を選択しなければなりません。コストパフォーマンスも考慮しながら効率的に債権回収を進めましょう。



債権回収を弁護士に依頼するメリット

弁護士に債権回収を依頼すると以下のメリットがあります。
01.最適な債権回収方法がわかる
上記の通り債権回収の方法にはさまざまな種類があるため、自社ではどの手続きを利用してよいか判断しにくいでしょう。弁護士に依頼すれば、状況に応じた最適な方法を提案してもらえますので、方向性が明確になり適切な方法で債権回収を進めやすくなります。
02.債権回収が成功しやすくなる
「回収できない」と半ばあきらめていた債権でも、弁護士に依頼することで回収に成功したケースは少なくありません。
たとえば自社で請求しても相手が無視するようなケースでも、弁護士が内容証明郵便で請求することで相手が応じるケースも少なくありません。債権回収を諦める前に弁護士に依頼してみましょう。
03.さまざまな債権回収の手続きを依頼できる
調停やADR、訴訟などの手続きを自社のみで進めると大きな負担となるものです。専門の債権回収部門がない小さな会社では日頃の業務にも支障が出てしまうでしょう。
債権回収手続きを弁護士に依頼すれば、自社で対応する必要はなくなります。訴訟などの難しい手続きについても労力をかけずに進めることができ、債権回収を成功させられる可能性が高くなります。
貸倒損失とは

さまざまな手法を使ってもどうしても債権回収できない場合、債権回収が完全に不可能となった場合には、債権回収をあきらめて債権を放棄するしかありません。なお、この場合は貸倒損失として税務上の利益を受けられる可能性があります。
貸倒損失とは、債権回収が不能となって発生する損失です。法人の金銭債権が回収不能となって貸倒損失に該当した場合、損金算入することで税額を減らせる可能性があります。ただし、貸倒損失として損金算入できるケースは限定されており、自社の判断で適当に算入することはできません。
債権を回収できなくなったら貸倒損失の要件を検討し、可能であれば損金算入を進めましょう。
貸倒損失で損金算入できる3つのパターン
 貸倒損失によって損金算入できるのは以下の3つのケースです。
貸倒損失によって損金算入できるのは以下の3つのケースです。
01.金銭債権が切り捨てられた場合
以下のような事情によって金銭債権が切り捨てられてしまったら、債権は貸倒損失となります。この場合、損金算入される年度は「切捨ての原因となる事実が発生した年度」とされます。
- 会社更生法や民事再生法、会社法などの規定にもとづき裁判所が下す決定によって債権が切り捨てられた場合
- 法令による整理手続きではない債権者集会の協議決定、または行政機関や金融機関などのあっせんによる協議によって切り捨てられた場合
- 債務者の債務超過状態が相当期間継続し、債権の弁済を受けられないと認められる場合において、債務者に対して、書面により明らかにした債務免除額
①は、相手方が会社更生、民事再生や破産、特別清算などの手続きによって債権回収が不能となった場合です。手続きによって切り捨てられた金額を損金算入できます。

②は破産や民事再生などの法律上の制度は利用していないけれども、債権者集会や金融機関のあっせん、ADRなどを利用して債権が免除された場合です。ただし「合理的な基準」によって切り捨てられたことが必要となります。
③は、たとえば長期にわたって支払がなされず相手と連絡がとれないケースにおいて、債権者が内容証明郵便等で債権放棄を通知した場合には、放棄した金額を損金算入できる可能性があります。
02.事実上債権回収が不可能となった場合
債務者が破産や民事再生などの法的手続をとらず、債権者集会における免除手続きなどもしていない場合であっても、債務者の資産がなく収益性が低下していて債権回収が明らかに不可能な状態になれば貸倒損失として損金算入できます。
算入できるタイミングは、債権回収が不可能であることが明らかになった事業年度です。
なお、債務者へ担保を設定している場合、処分後でないと損金処理できません。また、連帯保証人がいる場合、連帯保証人の資産状況や支払能力を勘案する必要があります。連帯保証人も債務者と同様に支払不能な状況でなければ貸倒損失としての損金算入はできません。
03.取引停止となった場合など
以下の状況に該当する場合には、債務者への売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒として損金処理できます。なお、この条件を適用する場合、対象は売掛債権に限られます。貸付金債権については貸倒処理はできないので注意しましょう。
- 継続的に取引していた債務者の資産状況、支払能力が悪化したために、1年以上取引を停止したとき
- 同一地域の相手先に対する売掛債権の総額が取立費用より少額で、支払を督促しても弁済がない場合
①についてですが、その売掛債権に担保が設定されている場合には、この条件による損金算入は認められません。また、継続的な取引を行っていたことが要件となるため、不動産取引のような単発取引をした相手には適用できません。
②についてですが、同一地域の相手先に対する売掛債権の金額が少額で取立費用のコストの方が高くなってしまう場合には、相手に任意の督促をしても払われないなら貸倒損失として損金算入できます。

貸倒損失で損金算入する際の注意点

貸倒損失として損金算入するときには、以下の点に注意が必要です。
01.損金算入の時期
貸倒れによって損金算入するときには「時期」に注意しましょう。
債務者の破産や民事再生などによって金銭債権が切り捨てられた場合には、切り捨てられた時点の事業年度に損金算入します。
事実上債権回収できないことが明らかになったために貸倒処理をする場合、債権回収できない事実が明らかになった時点の事業年度に処理を行います。
相手の資産状況が悪化して取引を停止してから1年が経過したために損金算入するなら1年が経過したタイミングで損金算入します。
時期がずれると税務調査の際に問題となる可能性が高くなるため注意しましょう。
02.損金経理が必要かどうか
貸倒損失を損金算入する際、経理処理としての損金計上が必要な場合とそうでない場合があります。
破産や民事再生などの法的事由によって金銭債権が切り捨てられた場合には、自社で損金経理をしていなくても当然に損金算入可能です。他方で事実上債権回収が不能となった場合や取引停止、回収コストがかかるので債権放棄する場合などには、損金経理をしない限り損金算入できません。
経理処理が必要なケースであるにもかかわらず適切に処理されていなければ、税務調査が入ったときに損金算入を否定されるリスクが発生します。貸倒損失を計上するのであれば経理処理方法にも注意しましょう。
03.資料を残しておく
貸倒損失を損金算入する場合には、必ず関係資料を残しておきましょう。後に税務調査が入ったとき、証拠がなければ貸倒れによる損金算入を否認されるリスクがあるためです。
資料としては、以下のようなものを保存しておきましょう。
- 裁判所や弁護士からの通知(法的整理が行われたケースなど)
- 相手に送った内容証明郵便による通知書、その他の催告書
- 相手からの回答書
- 請求書や納品書、契約書
- 担当者からの報告書
- 相手の資産状況を示す資料
- 相手の支払能力についての調査資料(信用調査会社から受け取ったレポートなど)
さいごに
自社では債権回収できないと思われる債権であっても、弁護士に依頼することで取立てが可能となるケースは少なくありません。債権回収をあきらめてしまう前に弁護士に相談してみましょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、債権回収に注力しております。債権回収でお悩みをお抱えの方は、是非一度ご相談ください。