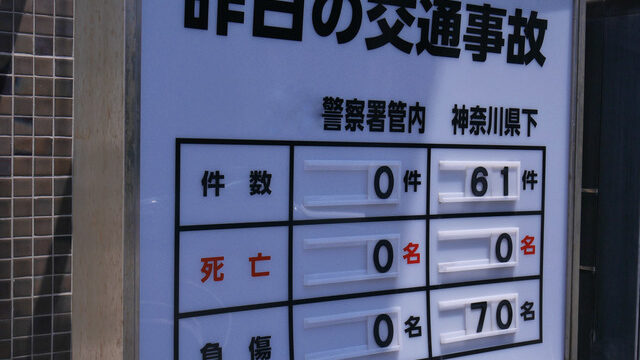交通事故で人が亡くなった場合、遺族が加害者に対して請求できるのは慰謝料だけではありません。交通事故に遭ったことで発生した費用やその人が亡くなったことで得られなくなったお金についても請求することができます。
今回の記事では、死亡事故の被害者遺族が相手方に何を請求できるのかについて解説します。
死亡事故の慰謝料
交通事故で人が亡くなった場合、「遺族に対する慰謝料」と「本人に対する慰謝料」の2種類の慰謝料が発生します。
01.遺族に対する慰謝料
交通事故で人が亡くなった場合、被害者の遺族は加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料を請求できる遺族は下記のとおりです。
- 被害者の父母
- 被害者の配偶者
- 被害者の子
なお、上記以外の続柄の人、たとえば兄弟・姉妹や祖父母、孫などであっても、上記の遺族と実質的に同視できるような関係にあり、大きな精神的苦痛を受けた場合には遺族としての慰謝料請求ができます。
02.本人に対する慰謝料
死亡事故の場合、亡くなった本人にも加害者に慰謝料を請求する権利があります。
そもそも慰謝料とはその事件や事故により受けた精神的苦痛を補完するために支払われるお金です。亡くなった人には事故以降の未来もあったはずであり、それを失ったことによる精神的苦痛は計り知れません。当然に慰謝料を請求する権利が発生します。
とはいえ亡くなってしまった人には慰謝料を請求する手続きができませんので、死亡者本人の慰謝料請求権は相続人に相続され、相続人が加害者に対し慰謝料を請求します。
なお、相続人の決め方には優先順位があり、具体的には次のように決まります。
【相続人の優先順位】
- 配偶者と子は共に必ず相続人になる
- 子がいなければ、配偶者とともに孫が相続人になる
- 子も孫もいなければ、配偶者とともに両親・祖父母が相続人となる
- 両親・祖父母もいなければ、配偶者と共に兄弟・姉妹が相続人となる

慰謝料の相場

死亡事故の慰謝料を求める際の基準は、下記の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
01.自賠責基準
自賠責保険は車に乗る人すべてに加入が義務付けられている保険です。
自賠責基準の慰謝料は3つの基準の中で最も低く、一律で次のように決まっています。
| 死亡者本人に対する慰謝料 | 400万円 |
| 慰謝料の請求権を持つ人が1名の場合 | 550万円 |
| 慰謝料の請求権を持つ人が2名の場合 | 650万円 |
| 慰謝料の請求権を持つ人が3名以上の場合 | 750万円 |
| 死亡者に被扶養者がいる場合 | 別途200万円 |
※慰謝料の請求権を持つ人とは、「父母」「配偶者」「子」のことです
02.任意保険基準
任意保険は、本人の自由意志で加入するかしないかを決めることができる保険です。任意保険では、各保険会社それぞれが独自の慰謝料算定基準を定めています。
なお、その基準は自賠責基準とそこまで変わらないことがほとんどです。
03.弁護士(裁判所)基準
弁護士(裁判所)基準の慰謝料は、被害者本人の立場で変わります。また、亡くなった本人と遺族の慰謝料を合算して計算されます。
具体的には、次のように決まっています。
| 被害者の立場 | 弁護士基準 |
| 一家の支柱(家計を主に支えている人) | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| 独身の男女・子ども | 2000~2500万円 |
弁護士基準は、上述の2つの基準(自賠責基準・人保険基準)と比べて高いものとなっております。
慰謝料が増額されるケース

事故の内容や加害者側の態度によっては、死亡事故の慰謝料が増額されることがあります。慰謝料は精神的苦痛を補完するお金であるので、被害者側の精神的苦痛が大きければ大きいほど慰謝料は上がることになるのです。
次のような場合、増額される可能性があります。
- 加害者が違法な運転、極めて危険な運転をしていた
- 事故の状態が残酷なものである
- 複数人が死亡している
- 加害者側の態度が悪い、不誠実である
- 加害者側の主張が著しく不当なものである
- 死亡した本人が著しく幼い
- 被害者の死亡により、遺族の健康や仕事、学業に悪影響が出た

慰謝料以外に請求できるもの

交通事故で人が亡くなった場合、遺族は慰謝料のほかに以下のものを請求できます。
- 死亡した人の逸失利益
- 死亡までの入通院慰謝料
- 葬儀に関する費用
- 死亡までにかかった治療費
01.逸失利益
交通事故で人が亡くなった場合、遺族はその人が本来得られるはずだった利益を加害者に請求することができます。この利益のことを「逸失利益」といいます。
逸失利益の基本的な計算方法は、「死亡した本人の1年あたりの基礎収入 × 本来稼動可能だった期間」です。
たとえば年収400万円で向こう30年間は働く予定であった人が死亡した場合、単純計算で1億2千万円の損害が発生したことになります。
なお、逸失利益を請求する場合、利息にあたるものを考慮する必要があります。先の例で言えば30年間かけて手にするはずだった1億2千万円を一度に得ることになりますので、いわば利息相当ともいうべき利益が発生すると考えられ、その分を控除されます(ライプニッツ係数)。
また、人が亡くなった場合、収入が発生しなくなる代わりに生活費もかからなくなります。逸失利益を計算するときは、本来かかるはずだった生活費分を控除することになります(生活費控除率)。
なお、昇給の可能性を考慮に入れることは困難とされています。昇給の可能性を考慮に入れるには相当の証拠が必要であり、仮に認められるとしてもその金額は控えめに計算されております。
上記の内容を考慮し、逸失利益は次のように計算されます。
【逸失利益の計算方法】
年間基礎収入額 × (1 – 生活費控除率) × 稼動可能期間に対応したライプニッツ係数
【一般的な基礎収入額の求め方】
給与所得者:源泉徴収票により算出
事業所得者:死亡前年もしくは数年前まで遡った確定申告所得により算出
年金受給者:老齢年金、障害年金により算出
家事労働者(主婦・主夫):賃金サンセスの女子労働者の平均賃金により算出
【一般的な生活費控除率】
一家の支柱(被扶養者1人):40%
一家の支柱(被扶養者2人以上):30%
女性:30%
男性:50%
【一般的な稼動可能期間の計算方法】
18歳~66歳の人:67 - 死亡時の年齢
67歳を超えても就労する可能性の高い人:平均余命年数 - 死亡時の年齢 × 0.5
18歳未満の人:49年(18歳から働き始め、67歳で働くのを辞めると仮定)

02.死亡までの入通院慰謝料
交通事故の被害者がすぐに死亡せず、治療の末に亡くなってしまった場合、遺族は被害者の入通院慰謝料を請求できます。
【自賠責の場合】
自賠責基準の場合、慰謝料の金額は治療日数で計算されます。治療日数は「治療期間」と「実治療日数の2倍」の短い方を慰謝料の計算に用います。
- 治療期間:初診日~治療終了日までの日数
- 実治療日数:治療期間の間で通院した日数
それぞれの治療日数をカウントし、短かった方を「治療日数」として次の計算式に当てはめて算出します。
4,300円 × 治療日数 = 慰謝料額
【任意保険基準】
任意保険の慰謝料基準は、保険会社により異なります。
【弁護士基準】
弁護士基準の入通院慰謝料は、次のような目安となります。
| 入院期間 | 治療費 |
| 1ヵ月 | 53万円 |
| 2ヵ月 | 101万円 |
| 3ヵ月 | 145万円 |
| 4ヵ月 | 184万円 |
| 5ヵ月 | 217万円 |
| 6ヵ月 | 244万円 |
慰謝料や逸失利益を請求する方法

死亡事故の慰謝料や逸失利益は、次のような方法で請求します。
- 示談交渉
- 訴訟
- 調停
- 交通事故紛争処理センター
ほとんどは示談交渉で請求されていますが、中には訴訟で請求するケースもあります。訴訟は避けたいという場合は、調停や交通事故紛争処理センターを活用します。
さいごに
交通事故で大切な人を失い気力が奪われているときに、本記事で解説したようなことを調べるのは容易ではありません。加害者側と適切な交渉をするのも正当な金額の賠償金を受け取るのも極めて困難でしょう。
だからこそ死亡事故の示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。難しいことは法律の専門家に任せ、自分のそしてほかの家族の心のケアに集中してください。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故トラブルの解決に注力しております。死亡事故における相手方(相手方保険会社)との交渉についても広く受け付けております。
交通事故で大切な方を失ってしまい、やるべきことに手を付けられなくてお困りの方はご相談ください。